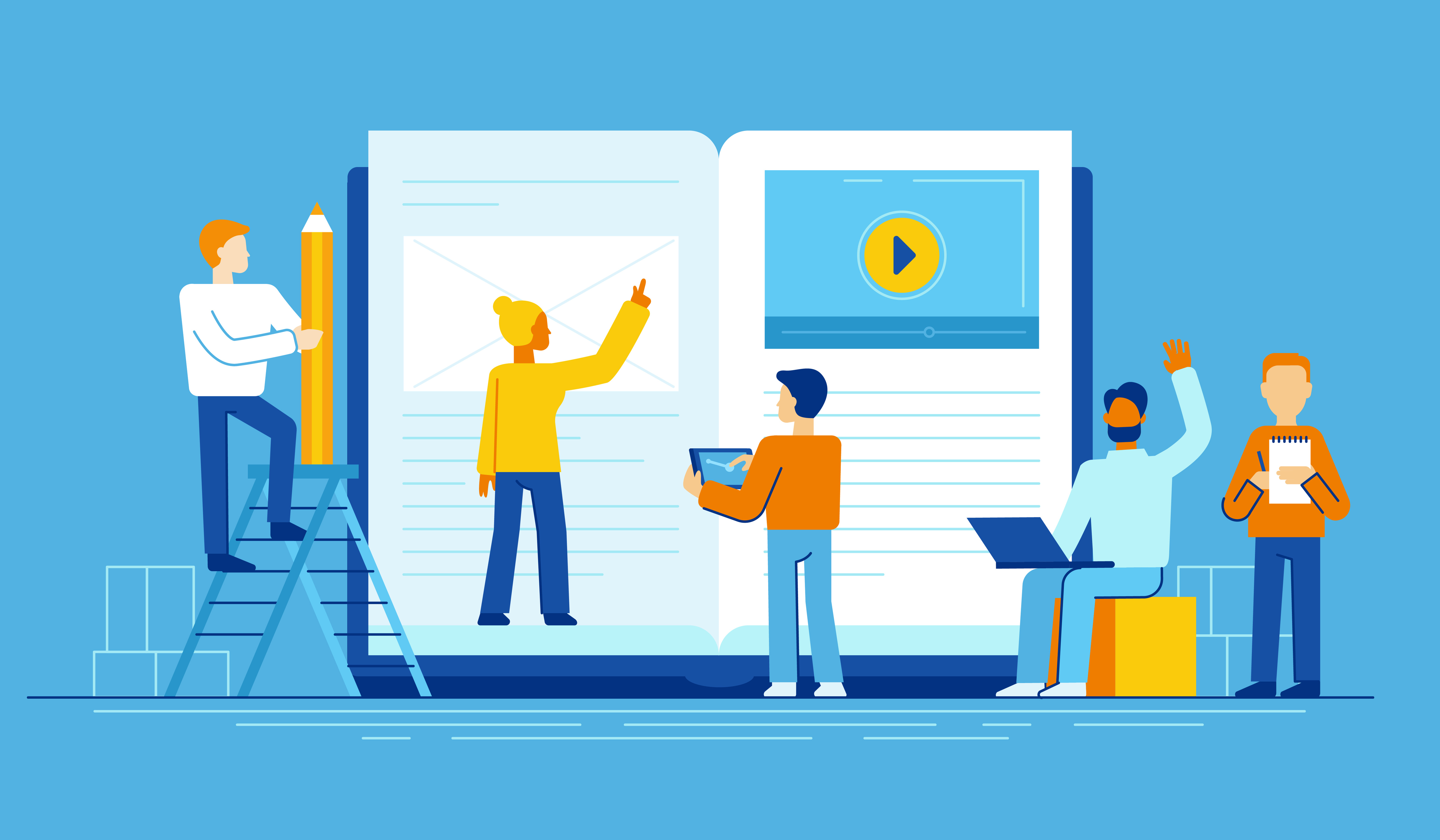2023.07.10
人材開発とは?人材育成との違いやポイント、これからの人材開発に必要なことを解説
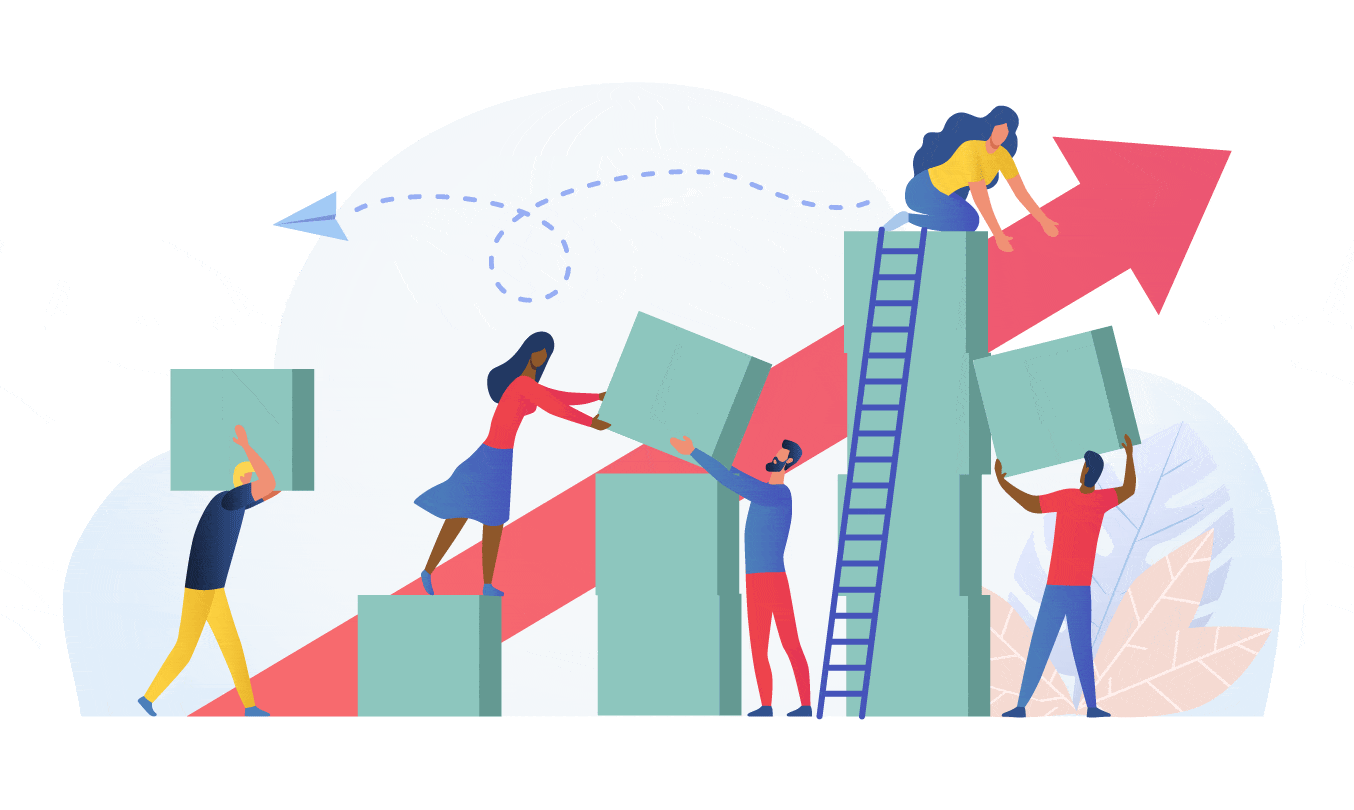
目次
人材育成と聞けば、新入社員教育・集合研修・管理職昇格試験などさまざまな人事施策や現場のOJTや部下育成を連想するでしょう。一方で「人材開発」に対しては、あまりイメージが湧かない方が多いかもしれません。また、人材育成と人材開発は同じもの、と思っている方も多いでしょう。しかし実は、両者には本質的な違いがあります。
この記事では、「人材開発」について人材育成との違いを含めて全体像を明確にしたうえで、組織開発と同時進行で取り組む必要性や、人的資本の情報開示時代の費用対効果に見える研修手法やPBL(プロジェクト・ベースド・ラーニング)などについて解説します。
人材開発とは
均質性から多様性へと変化が段階的に進む中で、「人材開発」は個人のスキルや知識を向上させ、根本的な個性や強みを開発するなど、人材一人ひとりにアプローチして能力や素養を伸ばすことが主軸になっています。
21世紀に入る前後まで、ビジネス経験の全くない大卒者を採用し退職まで面倒をみるという「就社」が基礎にありました。日本企業の人事施策は「知らない人」に「一から教育」する「人材育成」を軸として展開されてきました。具体的には新入社員から上級幹部迄の階層別の集合研修、定期的なジョブローテーションによるゼネラリストキャリア、新卒採用と終身雇用を前提とした社内キャリアアップなど、均質で緊密な職場環境によるOJTが、高度経済成長期と連動した成功モデルであり、すべて人材育成を基本思想としていました。
一方で、人材開発と呼ばれるコンセプトに注目が集まり始めたのはここ20年くらいのことです。日本企業が多角化、国際化し、産業構造も高度化する中で、事業や部門毎に必要とされる能力やスキルは多様化していきました。それと同時に全社員に共通するスキルや能力、さらには個別に専門性の高いスキルも必要になってきたのです。
また、変化のスピードに対応するため、権限は事業や部門に落とされ、課題設定やアイディアの創出など業務は変容し、それに伴い必要とされるスキルも変容してきています。しかし、個々の総和は全体のパフォーマンスを向上させるという単純な構造ではなく、組織やチームとして共通均質性と多様性をどのようなバランスを取るべきかという問いをなしにして設計はできません。
人材開発の定義
そもそも人材開発とはどのような意味の言葉なのか、定義を確認しておきましょう。人材開発とは、教育や訓練を通して従業員のスキルを高め、業務に関する姿勢や態度を改善させてパフォーマンスを向上させる行為です。具体的には、社内研修や外部講座などを受けることで実現します。従業員一人ひとりにアプローチして知識やスキルを身につけさせることで、自社の課題を認識し、解決していきます。
人材育成との違い
「人材開発」よりも「人材育成」という言葉のほうが、耳馴染みがいいという方もいるでしょう。「人材育成」という言葉は一般的ですが、「人材開発」も、企業が採用した社員の能力を最大限引き出すことを目的としています。しかし人材開発とは、人材育成とは違い、従業員それぞれがすでに持っているものを活用してスキルを伸ばすという考え方です。つまり「人材を自社の求める姿に染めていこう」という考えは、開発ではなく人材育成にあたります。人材開発では全員に同様の学習をさせるのではなく、より複雑で細かい学習を用意し、これにより、個々のスキルと組織の目的をすり合わせていくのです。
人材開発は人材育成と比較すると、短期投資に近いものがあります。しかし、人材開発も人材育成も、採用、育成、活躍という投資サイクルを回す期間が従来に比べて短くなっているのが事実です。変化の激しい世の中においては、人材戦略を綿密に立て、その通りに動くというよりは、短期的な目線でアジャイルに育成を繰り返すイメージでいたほうが企業にフィットするのです。
ただし、人材育成に注力しても、短期間で大きな成長を期待することはできません。もちろん育成にかかる労力を軽減したいなら、採用の段階ですでに必要スキルを備えた人材を招き入れるという方法もあります。しかしながら、都合のいいスキルを持った人材が来て、カルチャーにもフィットするというのは稀なケースです。
従来は、企業は学生を採用して一から育て、特定のマニュアルや行動パターン、思考方法を教えることで、一定の業績を支えてきました。しかし、バブル崩壊や製造業からサービス業への産業変化により、作業内容が単純なものではなくなりました。顧客や環境の要求に応じて、現場で思考しコミュニケーションを取り、即座に判断して対応しなければなりません。このような流動的な業務に対応するためには、従業員の思考力やコミュニケーション能力など、個々の持っている能力を活用する必要があります。そのため、従業員の能力開発が重要となっているのです。
また、最近では、育成や開発だけでは迅速な対応が難しくなってきたため中途採用やフリーランスの活用が増えています。彼らは早く成果を出せることが求められており、そのためには適切なオンボーディングが必要です。こうした課題に対応するために、HRBP(Human Resources Business Partner)の存在が重要となっています。HRBPは、人材戦略の立案と実行を支援し、組織と人材のニーズを調整する役割を担っているのです。
組織開発と人材開発との違い
人材開発に取り組む際に忘れてはならないのが、組織開発です。個々の総和は全体のパフォーマンスを向上させるという単純な構造ではない事は自明の理で、組織やチームとして共通均質性と多様性をどのようなバランスを取るべきかという問いをなしにして設計はできません。社員一人ひとりと職場の関係性や組織との関係性を整理する必要があります。
組織開発は、その言葉のとおり組織をより良くするためのアプローチ(開発)を行うものです。具体的には組織の構成員、企業であれば社員同士の関係性を改善し、組織の活性化を図ることを目的とするので、個々の従業員の能力を伸ばす「人材開発」とはアプローチする対象が異なります。
しかし、組織のパフォーマンスは組織や職場と人材が相互に関係しながら発揮されるものであるため、両者を切り離して考えることはできません。社員が優秀であっても、人材への投資や育成に努めるだけでは成功することはありません。重要なのは、その人材を取り巻く環境や組織文化との連携です。組織との相互作用がなければ、人材は十分に力を発揮できないのです。
組織開発の進め方や手法については、以下の記事を参照ください。
企業が抱える人材育成の課題
2020年1月に日本経団連が実施した「人材育成に関するアンケート調査結果」によると、人材育成施策の環境変化への対応状況について、9割を超える企業が「対応できていない部分がある」と回答しました。
対応が必要となっている要因(複数回答)としては、就労意識の多様化(ダイバーシティ経営の推進)、デジタル技術の進展、事業のグローバル化の進展、オープンイノベーション(外部との連携)の広がりなどが挙がっています。
また、2021年6月に改定が行われた東証のコーポレートガバナンスコードの改定によって人的資本の情報開示について義務化されています。投資家から人的資本の活用度合いが株価に影響する時代になってきています。
人材開発からHRBPへ
従来の日本企業の人材育成は、長期的な視点に立ち、人材戦略・人事制度・研修体系を整えながら成長を促すものでした。しかし上記でも説明しているように、これらの手法は理屈上の正しさだけを残しつつ、すでに崩壊しつつあります。企業は、より細かい事業単位レベルで人材問題を解決する必要性に直面しています。採用時に求める人材の理想を変えたほうがいいケースもあるでしょう。
そこで注目すべきなのは「HRBP」です。上記でも少し触れましたが、HRBPは、「Human Resource Business Partner」の頭文字をとった言葉で、日本の企業で一般的となっている「事業部人事」とは異なる概念です。「事業部人事」は、事務的な人事業務を中心となって行ったり、さまざまなサポートを行ったりと、細かい実務を担います。一方でHRBPの目的は、人事という仕事を通して、事業にインパクトを与えることです。変化が激しく複雑化する現代の世の中の情勢を読みながら、企業活動を人事面から最適化させていきます。
HRBPは、現場と経営の間に立ち、現場からやってくる課題感やニーズについて経営層に伝えます。しかしながら、経営全体と橋渡しをすると言いつつも、行うのはあくまでの事業側であり、現場で目線に立っていることが多いのが現状です。
この現状を踏まえ、人事部門はオペレーション上の役割だけでなく、人的資源を戦略的に管理しなくてはなりません。脱工業化し、人的資源がより重要になる現代社会において、人材はもはや事業のコアと言っても過言ではありません。人材の細かい問題は現場主導で解決していかなければなりませんが、同時に経営層とともに全体最適化を目指すためにも、より強力に指揮をとる必要があります。

株式会社EPクロア:ラーニングエクスペリエンスデザインの手法を生かした社内研修の内製化支援
在宅勤務やテレワークの導入が進み、研修のスタイルも変わりつつあります。医薬品開発のさまざまなプロセスにかかわ…
人材開発が必要となる背景
なぜ今人材開発が必要なのでしょうか。6つの視点から、その背景をより詳しく紹介していきます。
日本企業の雇用と組織の変化
高度経済成長期に、日本企業は新卒採用・年功序列・終身雇用などのシステムを定着させました。これにより優秀な人材を囲い込み、長いスパンをかけて人材を育てていくことに成功してきました。しかし、現在は当時とは状況が異なります。従来の雇用システムは業績が右肩上がりであることを前提に組まれていましたが、経済状況を鑑みても、その前提が揺らいでいます。しかも従業員が会社に対して抱く帰属意識も、昔と比べて希薄化しています。
このような状況の中で、いかに若手の人材を確保するかという視点に立ち、成果主義を積極的に取り入れる企業も増えています。成果主義が浸透してきたことは、終身雇用の崩壊において見逃せないトリガーになるでしょう。
ビジネスのデジタル化やIoTの導入
従業員に求められる知識の種類も、従来とは大きく変わっています。昨今の企業は、インターネットやネットワークの知識を必ずといっていいほど求めています。また業務を効率良く進めるためにはWebアプリケーションの知識も重要ですし、業務の種類によってはデータ解析などのITスキルも少なからず求められます。IoTなどの専門知識も、今では幅広く知っておくことが求められます。
それらに加え、グローバル化、人材の多様化などを理由に求められるコミュニケーション能力やマネジメント能力のレベルも高くなっているといえるでしょう。このようなハイレベルな人材を育てていくことが、自社や顧客に価値を提供するために重要視されるようになっています。
スキルの変化
スキルの変化を細かく把握するために、古いモデルですがあえて「カッツモデル」で説明します。
「カッツモデル」とは、役職やマネジメントにおける立場を3つにわけ、さらにそれぞれに求められる能力を「テクニカルスキル」「ヒューマンスキル」「コンセプチュアルスキル」の3つで分類した図です。
従来では、マネジメントにおける最下層は「テクニカルスキル」がもっとも問われ、「コンセプチュアルスキル」はそこまで問われないという図でした。反対にマネジメントにおける最上層は「テクニカルスキル」はもっとも必要とされないものの、「コンセプチュアルスキル」は問われるとされていました。つまり3つのスキルの階層を分ける線は、ナナメ線で区切られています。しかし現在のカッツモデルを作るなら、この斜め線はもはや縦になっていると言えそうです。すべての階層が等しく3つのスキルを持っていることが重要になっているのです。ただしテクニカルスキルは日々変化するものであり、コンセプチュアルスキルを大事にしてきたトップ層は、テクニカルスキルを正しく理解していないことが多く、改善の余地があります。
テクニカルスキル
業務を遂行するにあたって必要なのがテクニカルスキルです。たとえば1980年代に入社した人は、PCで仕事をしたことがない人が大半でしょう。企画開発も紙ベースで行われていましたし、製品設計におけるCADなども存在せず、紙で図面を描いていたはずです。
しかし今やテクニカル面の知識は多くの企業で少なからず求められます。製品を扱う仕事では、製品データや設計データを扱い、マーケティングに連携させるのが主流です。ビジネスの軸自体がそこまで変わっていないという業界であっても、業務単位でフォーカスすれば、どの業界も変化を経験していると言えます。
ヒューマンスキル
ヒューマンスキルは、マネジメントスキルとも表現されます。コミュニケーションスキル、つまり人と人とをつなぐスキルと言い換えてもいいでしょう。コミュニケーションスキルは、コミュニケーションの相手が個人なのか集団なのか、はたまた組織なのか、状況によって多種多様な性質を持っています。
従来から企業はコミュニケーションスキルの大切さを謳い、大卒採用の現場でも重視してきました。しかし、古くからの日本的なコミュニケーションは「阿吽の呼吸」です。従来の日本企業は、OJTや通常業務を通して、新入社員に阿吽の呼吸を叩き込んできたと言えます。
教育機関でもコミュニケーションスキルをしっかり教えているところは少ないので、現状の日本的な従業員は、コミュニケーションをとることに課題を抱えているケースも多いのです。とくに雇用形態や業界、職種、専門分野が異なる相手、もっと言えば世代や国籍が違う相手とのコミュニケーションを非常に難しく感じる人が多いのではないでしょうか。
「以心伝心」「いわずもがな」で気持ちが通じる組織に身をおいていては、コミュニケーションスキルは向上しません。社会は変化している一方で、、組織内のコミュニケーションスキルは変化していないのです。
このような課題の多いヒューマンスキルを改善に導くには、外部や他業界とコラボレーションするのが効果的です。自社の言葉では意思疎通ができないような相手と関わるなど、人材開発にも新しいエッセンスを取り入れる必要があります。
コンセプチュアルスキル
コンセプチュアルスキルは具体を抽象にして、問題を捉えるという、いわば概念化のスキルです。産業の成熟化に伴って大手企業の業務は多角化が進みました。上部がすべてを司ることが困難になり、ある程度の意思決定の権限・責任は現場に移譲されるようになっています。よって現場の従業員が企業を超え、地域を超え、業界を超えて密に連携を指揮することも増えました。
そのため、経営上の問題を特定したり、解決したりと、コンセプチュアルスキルはもはや現場の管理者や担当者に必要なスキルになっています。大規模組織に長くいる人からすれば、若いころとは様変わりした現場になっているかもしれません。
そのような大きな主語に対して、具体的に対処し続けるのは現実的には難しく、効率も悪いものです。そこで、具体状況から正確に情報を習得し、抽象化しながら問題を洗い出して判断するというスキルが大切になるのです。
前出のカッツモデルの項目でも説明しましたが、脱工業化されたビジネス環境では、カッツモデルの斜め線はどの階層でもまっすぐになり、まるでマトリクスのような形態になっています。
人材開発を行う前に
人材開発において、人事施策は全体の中のほんの一部にすぎません。より大切なのは、事業ニーズに合った人材像を設定し、社員への適切なアプローチ方法を検討することです。
事業ニーズにあった人材像を定める
まずは経営戦略から、あるべき組織体制に基づいて配置すべきコア人材はそれぞれどのような役割を持ち、どのような知識やスキルを必要とするのかを具体化します。同時に、タレントマネジメントに基づいて、将来会社の中核を担うべきコア人材候補者のキャリア形成プランを策定しなければなりません。社外から中途採用で充足する場合もありますが、社内からの輩出を基本とします。
もちろん経営環境は変化するので、タレントマネジメントにも柔軟性・機動性を持たせる必要があります。また、人材開発を行う際には、人事部門の戦略性も要求されます。コア人材候補者の選出や異動・昇格の際に、会社の業績を支えている声の大きい部門の声に押されるようでは戦略を貫徹できません。人事戦略に基づいてコア人材の当事者や上司などの関係者を説得し、計画的に人材開発を進めましょう。
社員一人ひとりに適した人材開発の動機と能力をベースにアプローチする
もし、社員にスキルや知識が足りないだけなら、不足を補えば事足ります。これは、あくまで人材育成の領域です。
一方、人材開発で取り上げるのは、社員の意識や考え方の問題です。たとえば営業マンなら、「上位者(営業部長や支店長)は普段の仕事において何を考えるか」を知ることは大切です。上位者の考え方を知り、その思考パターンを身に着けることで、より高い次元で業務を遂行でき、営業スキルも効率的に活かせるようになります。
抜擢人事で若手を高いポストにつけるのも、人材開発のアプローチの一つです。上位者として資質のある人間を起用するのではなく、その人材が持つ実際の能力よりもストレッチしたポストを与えることで、上位者としての資質を身に着けさせるという考え方です。
キャリア面談やサポートを充実させることも大事ですが、パルスチェックなどで社員の動向を見ながら、適切なタイミングで施策を打つということも大事になってきます。また、後述するタレントマネジメントシステムの活用が進めば、人事部門が人材開発のアプローチを決める時代は終わり、ゆくゆくは社員一人ひとりが自分で自分の目指すキャリアに適した人材開発方法を選ぶような時代になっていくでしょう。
昨今多くの企業はデジタル先行、概念先行で話を進めがちです。まるで教育ママ(人財)と子供(社員)の関係のようになっていて、社員の明確な動機もなければ、活用する場もそもそもの意味すら不在なままでリスキリングが促されます。個人の動機が無視されている状態では、学習効果は著しく下がってしまうものです。そのため、企業は、客観的に自社の状況に注意するべきです。
人事データを統合し、タレントマネジメントシステムを整備する
タレントマネジメントシステムをしっかり活用できている人材開発部はまだまだ多くはありません。そもそも人材に関するデータがちゃんと管理されていなかったり、バラバラだった人事データを一元化したとしても活用できていなかったりするケースがほとんどです。
人材開発に取り組む際は、アンケートの実施後やオンボーディングの前後、昇格前や面談など、社員一人ひとりに対してその時々に必要なアプローチ(Eラーニング、上司との対話、集合研修、産業医との面談など)を行います。そして、これを実現するには、社員個人やその上司、人事担当者などが、人材に関するデータをきちんと入力する必要があります。これらのデータを統合して一元管理するのがタレントマネジメントシステムです。
しかし、人材開発の担当部が、そのデータを社員にとって価値あるものに変えることができなければ、タレントマネジメントシステムは役に立ちません。データを入力しても使われないのであれば、誰も入力しなくなってしまうでしょう。
人材開発と組織開発を同時に進める必要性
ここまで、さまざまな人材開発のアプローチについて説明してきました。しかし、これらのアプローチを通じて個々の社員がどれだけスキル・知識を身につけても、職場ですぐに活かせるわけではありません。
これは、いわば人材開発の永遠の課題です。
たとえばロジカルシンキングを勉強しても、現場が非論理的に考える人ばかりで、論理的な考え方が評価されないのであれば実践は難しいでしょうし、イノベーティブな提案をしたとしても、それを受け入れる職場でなければ、新たな提案をしようという人材も出てはこないでしょう。
現場で実践できる環境になっていなければ、学んだ内容もすぐに忘れてしまいますし、いくら動機付けされていても、やがて元に戻ってしまいます。もし、組織の全員に全く同じ人事施策を一斉に施すことができれば、環境自体を変えることができるかもしれませんが、規模の大きい組織では現実的に不可能です。
そこで、人材開発の成果を出すためには、人材開発と組織開発を連動させて、組織風土やワークスタイルの変革も同時に進めていけるかどうかがカギになってくるのです。
これからの人材開発に必要なこと
では、今後人材開発に取り組む上では具体的にどのような点に留意する必要があるのでしょうか。3つのポイントについて説明します。
組織開発と人材開発を同時に進める
繰り返しになりますが、人材開発を成功させるためには、組織開発と同時に取り組む必要があります。人材開発の効果が発揮できる組織を作るためには、人材開発の担当部が積極的に関わり、組織のメンバーが主体的に社内風土を改善していかなければなりません。
たとえば「ロジカルコミュニケーションを組織風土として定着させていく」とすると、部単位でロジカルコミュニケーション研修を実施したうえで、部内改善提案等を通じて組織にムーブメントを起こしていくなどの段階的な施策が必要です。これらの施策を進める際には、対面やオンラインツール、社内メディアなどを介したインターナルコミュニケーションが欠かせません。
インターナルコミュニケーションを重ねながら組織開発を推進し、その結果として組織が変わることではじめて、人材開発の成果も活きてくるのです。
社員が主体となって経験し、考えることのできる仕組みを作る
これも繰り返しになりますが、一斉に研修等を実施する人材育成とは異なり、人材開発は社員一人ひとりに対するアプローチが中心となります。人材開発においては、知識やスキルの向上につながるような教育・指導を施すよりもむしろ、必要な知識・スキルの習得につながる実践の機会を設け、経験を通じて社員が学ぶことのできるような仕組みが必要です。
そして、その実践が成功したのか、そこにどのような意味があったのか、そこから何を学んだのか、社員自身が考えて気付く機会を設けるためには、上司やメンターによるコーチングも欠かせません。
成果や課題解決の現場と教育施策を同時に遂行する
ビジョンや理念の浸透や関係構築など、マインドセットや思考の開発には、中長期的な階層教育など、全社員に対して継続的な取り組みが必要です。しかし、現在のビジネス環境では、仕事が急速に変化しているため、学んだことを即座に活用する必要があります。加えて、教育の効果や成果は、時間や場所の制約によって損なわれる可能性があります。
そのため、課題解決や目標達成に向けた活動と並行して、教育と学習を組み込んで取り組むと良いでしょう。これにより、教育の成果を実践的な行動に直結させることができます。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
スキルアップのサポートができる仕組みを作る
人材開発の対象となる社員が行きづまったときの相談相手となるメンターや、社員自身がさまざまなキャリアの可能性を検討できるような制度など、サポート体制の充実も欠かせません。
ここでも、会社がひとつの選択肢を社員に押し付けるのではなく、社員が自分に必要なものを自主的に選択できるようにしておくことが重要です。たとえば、専門家やコーチャーの監修によるスキルアップメニューを多数用意するといった施策はその一つといえるでしょう。
【PBL】人材開発と組織開発を同時に推進
これらを踏まえ近年注目されているのは、人材開発と組織開発を結合させた人材開発手法です。これは問題解決型学習、PBL(プロジェクトベースドラーニング)と呼ばれ、従業員自らが問題を発見して、具体的に解決していくまでを学んでいく行為です。人材開発においてより実践的な効果が期待でき、同時に自社の課題解決、組織開発にも効果が期待されます。
問題解決の過程が学習のポイント
PBLにおいて重要なのは、主体的に学習を実践することです。なぜなら、学習が深まるかどうかは、問題解決の過程に受講者がいかに没頭できるかにかかっているためです。主体的に問題解決にあたれる内容になるよう意識しながらフレームワークを作っていきましょう。テキストを用いずに自ら学んでいく手法なので、実践的なスキルアップが目指せます。
ビジネスにおけるPBLの実施
PBL には、大きくわけて2種類の手法があります。「チュートリアル型」と「実践体験型」です。
「チュートリアル型」とは架空の状況を設定して行う PBL であり、「実践体験型」とは、実際に自社や社会に起きている状況を題材に据える PBL です。後者の場合、売上減少時における問題解決、チーム・組織力が低下した際のコミュニケーション問題など、実際の自社の課題を研修のテーマに据えられるため研修と同時に課題解決・組織開発にも直結するのです。そのため、 PBL は「実践体験型」で行うことをおすすめします。
PBL の効果
PBL によって、人材開発の面では、仮説設定・検証などの自ら考える力が身につきます。組織開発の面では、業務に即した課題設定がうまくなるなどの実践的な成果が見られるでしょう。さらに「実践体験型」の PBL を行えば、組織で実践できる解決策が見つかり、組織の問題解決にもつながります。
まとめ
「人材開発」は個人のスキルや知識を向上させるなど、人材一人ひとりにアプローチして能力を伸ばすことを目的としています。自社の求める姿に染めていこうという「人材育成」とは異なり、より短期間で個々のスキルを成長させられるのが特徴です。
人材開発の成果を出すためには、人材開発と組織開発を連動させて、組織風土やワークスタイルの変革も同時に進めていけるかどうかがカギとなります。そこで注目されるのが PBL です。人材開発においてより実践的な効果が期待でき、同時に自社の課題解決、組織開発にも効果が期待される手法であるため、自社の成長のために、実施を検討してみましょう。
ソフィアでは、人材開発に欠かせない研修やインターナルコミュニケーションの支援を行っています。お困りのことがあれば、ぜひ一度ご相談下さい。
関連事例
よくある質問
- 人材開発とは何ですか?
個人のスキルや知識を向上させるなど、人材一人ひとりにアプローチして能力を伸ばすことを目的としています。ロングターム、つまり長い目でスキル・知識を伸ばすことに主眼を置き、一人ひとり違うゴールを設定します。
- 人材開発と組織開発を同時に進める必要性とは何ですか?
現場で実践できる環境になっていなければ、学んだ内容もすぐに忘れてしますし、いくら動機付けされていても、やがて元に戻ってしまいます。人材開発の成果を出すためには、人材開発と組織開発を連動させて、組織風土やワークスタイルの変革も同時に進めていけるかどうかがカギになってくるのです。

株式会社ソフィア
先生
ソフィアさん
人と組織にかかわる「問題」「要因」「課題」「解決策」「バズワード」「経営テーマ」など多岐にわたる「事象」をインターナルコミュニケーションの視点から解釈し伝えてます。
株式会社ソフィア
先生

ソフィアさん
人と組織にかかわる「問題」「要因」「課題」「解決策」「バズワード」「経営テーマ」など多岐にわたる「事象」をインターナルコミュニケーションの視点から解釈し伝えてます。