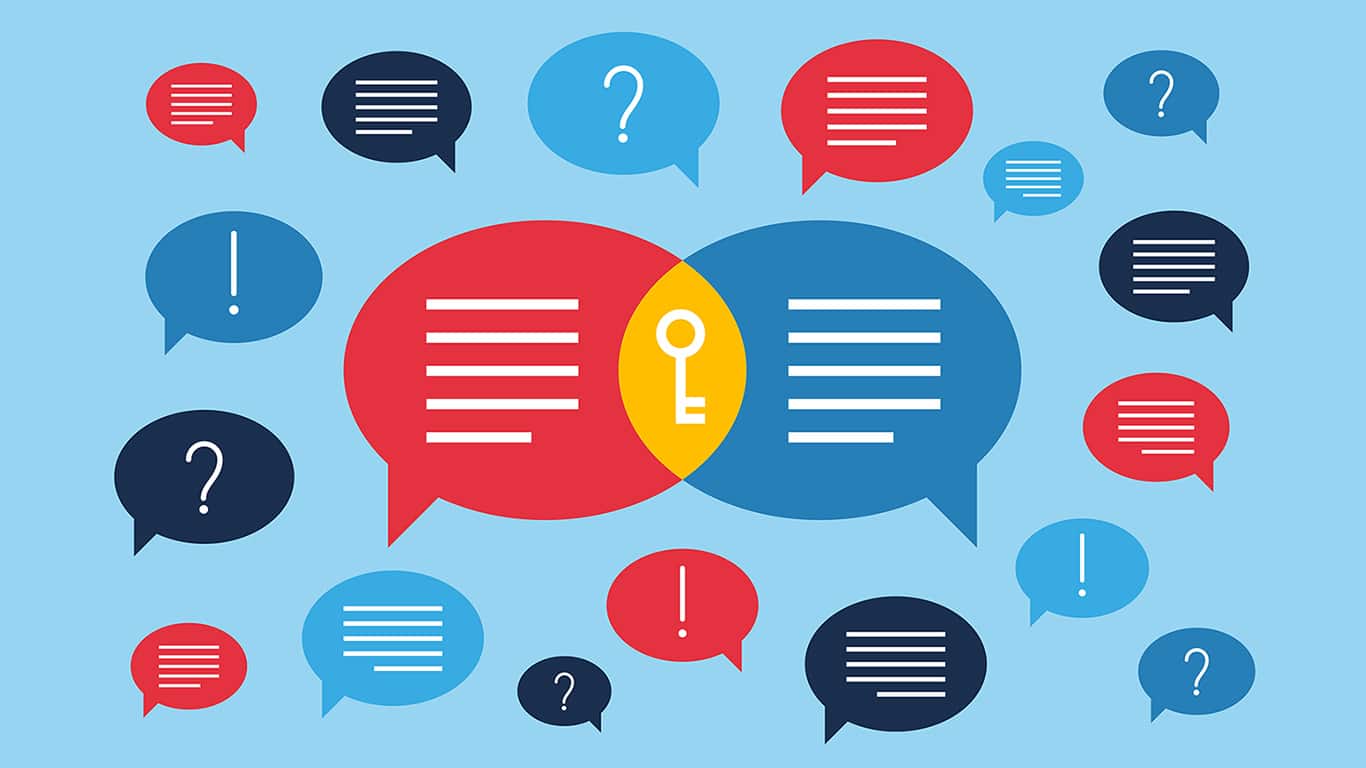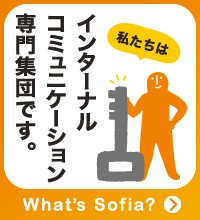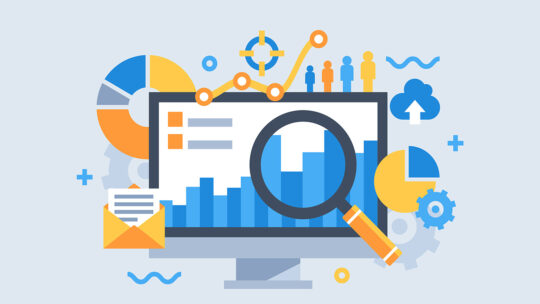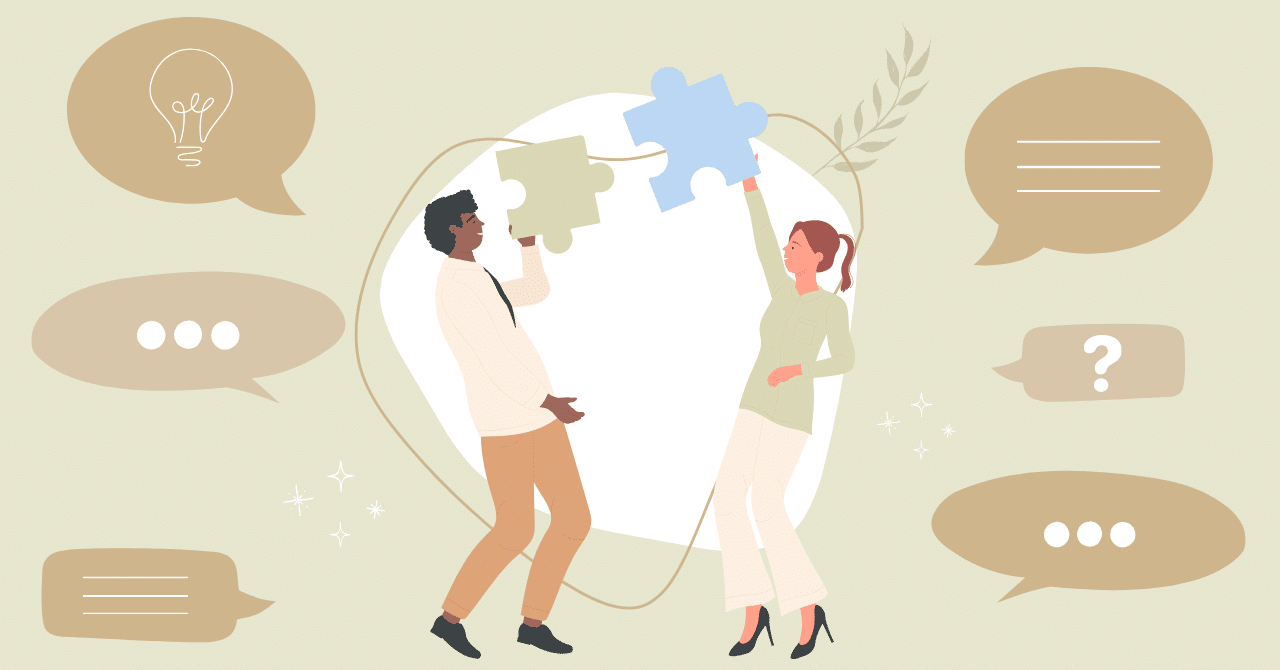
2022.09.22
傾聴とは?意味や使い方、ビジネスで効果を出す方法を紹介

目次
ビジネスにおいて「相手の話に耳を傾けて注意深く聞くこと=傾聴」が重要であることは、皆さんすでにご存知のことと思います。話をしっかり聞いて理解できる能力が高い人材は、関係者と信頼関係を築き、仕事を円滑に運ぶことができます。
そのため、コミュニケーションスキルの中でもとくに傾聴スキルを採用活動で重要視する企業も多いのではないでしょうか。
この記事では、企業組織を構成する人材を育成する上での傾聴スキルの重要性について、「傾聴」という言葉の意味やスキルの使い方、傾聴スキルを身に付けてビジネス現場で効果を発揮する方法などをご紹介します。

これは共感的理解の講義のアイスブレイクでよく用いられる題材の一例です。
一見すると仕事の優先順位とプライベートが天秤にかけられているようにも見えますが、根本的な原因はそもそも二人の時間がとれず、不満を抱えているという状況をどうにかしてほしいということを訴えているということを理解しなければなりません。
言葉の裏にある気持ちを察することを例に挙げたケースです。相手のことを思いやり、聞いたことから想起して潜在的な思考をくみ取る傾聴の題材としてご存じの方も多いのではないでしょうか。
傾聴とは?
冒頭でも述べましたが、傾聴とは「耳を傾けて注意深く相手の話を聴くこと」を指します。ここでは傾聴という言葉の意味や、傾聴スキルが用いられるシーンについて解説します。
[linkid=9594]
「傾聴」の意味
傾聴(積極的傾聴/アクティブリスニング)という言葉は 、単に相手の話を聞くのではなく、相手の立場に立って共感しながら、相手の話に積極的に耳を傾けることを意味します。
これは、米国の心理学者として有名なカール・ロジャーズによるカウンセリング理論の実践から広まり、ビジネスやスポーツ、医療などさまざまなジャンルで応用されています。
こと日本においては 家族、職場、地域の近隣のコミュニティでそれらを構成するメンバーの多くは日本人です。
なかにはごく少数の外国人コミュニティや、世代間のギャップこそありますが、多民族で構成された環境とは比べものにならないくらい互いに共通点を持っています。
かたや多民族で形成されている国や地域にいたっては共通点と呼べるものが極端に少ないため、相手の言っている事や背景を想像するために文化や言語体系への理解を深めようとより多くのコミュニケーションを重ねます。
現在の日本は、多文化や多民族といったほどではないにしても、職場同僚は転職することが当たり前になり、ジェネレーションギャップによる問題がこれに近いものがあります。そのため相手のことを理解するために聞く、そして知ってもらうために話すという前提に立って、お互いのギャップを埋めていくことが大切です。
傾聴の目的
傾聴を行う目的は、相手が話したいことに注目し、対話の理解を深めることです。傾聴では耳だけで話を聞くのではなく、表情などの非言語からも情報が読み取れます。
そうしたコミュニケーションから、相手もこちら側を理解してくれるようになり、良好な人間関係構築につながっていきます。
傾聴の背景
急速なテクノロジーの進化やグローバル化・多様化の波を受け、競争が激化している現代のビジネスシーンにおいて、時代に適合した優秀な人材を育成することは、すべての企業の急務です。
現在、私たちをとりまく労働環境は多様な人々のさまざまな価値観が交わるデジタル空間にあります。そのため、相手の状況を理解することは難しくなるばかりです。
さらに、グローバル化・多様化が進むなかにおいても、急速な変化に現場は対応しきれておらず、多様なビジネスパーソン同士が相互理解をするための足場が十分にできているとは言えません。
言語としてとらえることはできても、そもそも人物像の理解が追いつかないために、その人の意図をくみ取ることが難しいのです。
そのような状況もあり、物事の見方・考え方・文化圏が違う者同士をまとめ、マネジメントしながら仕事を遂行できる人材が必要とされています。
ビジネスパーソンのマネジメント力に必要とされる要素には、傾聴力・質問力・フィードバック・関係構築能力などがあります。
とりわけ積極的傾聴法とよばれるアクティブリスニングは、質問力と並んで有用とされており、これによりコミュニケーション能力が向上すると、ビジネスパーソン同士の連携が円滑になり業務の遂行が促進されます。
自社の社員同士だけでなく、社外のビジネスパーソンと仕事をする際など、あらゆる人間関係のマネジメント・コミュニケーションにおいて、アクティブリスニングの効力は発揮されるため、多くの企業で取り組みが広がっています。
次の章ではこのアクティブリスニングを提唱した米国の臨床心理学者カール・ロジャーズが提唱したカウンセリングやコーチング技法についてお話しします。
ロジャースの3原則
これは、米国の心理学者として有名な
ロジャーズ氏は、うまくいっているカウンセリングではクライアント(話をする側)から見てカウンセラー(話を聴く側)に以下の3つの条件が揃っていると述べています。
- 自己一致
- 無条件の肯定的配慮
- 共感的理解
とあります。これをビジネスシーンに置き換えてみると、上司がチーム内にむけて「このプロジェクトは大事だ」と言いつつも実際の行動や態度で示さない場合、矛盾が生じ自己一致ではなくなります。部下はその矛盾を敏感に感じ取り、コミュニケーションロスや生産性の低下に発展します。たとえネガティブな要素があっても適切に表現することで、率直な対話が生まれ、チームのパフォーマンス向上につなげることが重要です。
これをチームに適用したとき「成果を出した者だけが評価される」環境を作るのではなく、メンバーの個性や能力の違いを受け入れ、「このチームにいること自体が価値である」に理解を深め、一人ひとりが本領を発揮できる継続的な風土醸成が必要です。
たとえば同僚が「自分はこの仕事に向いていないかもしれない」と悩んでいるとき「そんなことはない」と励ますだけではなく、「そう感じる理由を教えてほしい」と相手の内面に寄り添うことで、同僚の悩みを理解しようとしていることを伝えます。一人で抱え込む状況から脱し、自分の感情や課題に気づきを促します。
この3つの条件は、「傾聴の3要素」「ロジャーズの3原則」などと呼ばれています。
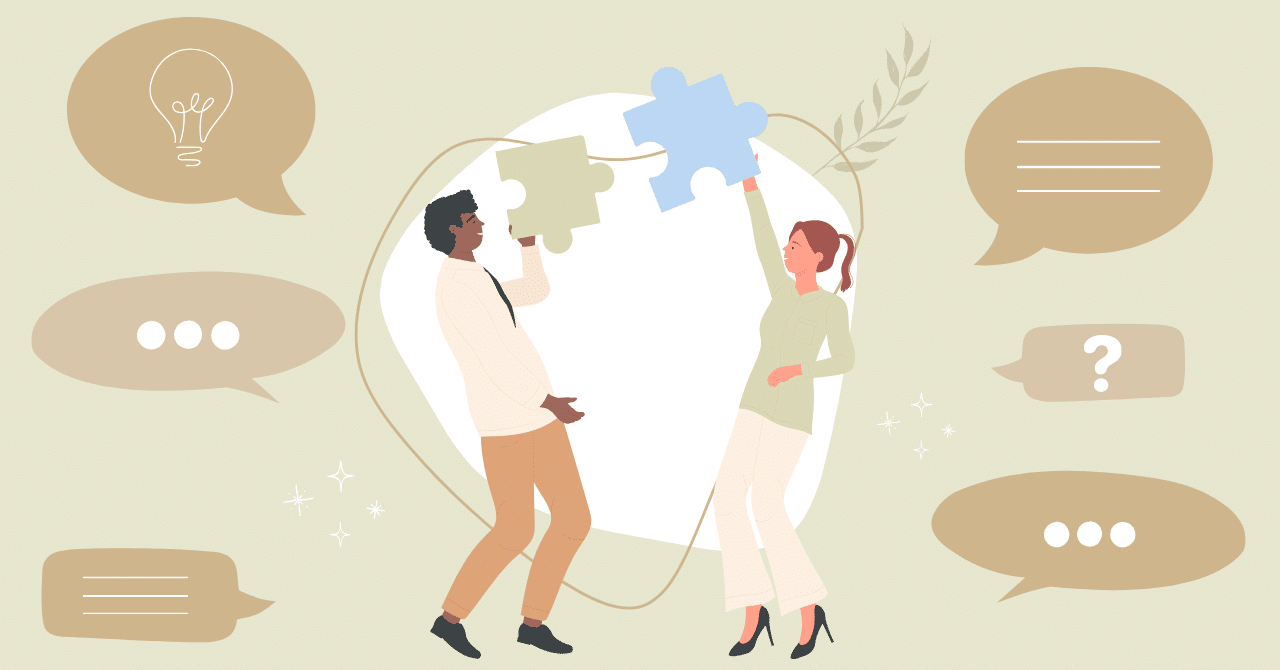
1on1(ワンオンワン)とは?目的やメリット、部下の成長を促すテクニックや話題例を紹介
最近は米国シリコンバレー由来の「1on1(ワンオンワン)」という新たなミーティングの手法がトレンドになっています…
傾聴はどんな場面で使われるのか
その答えは大きな意思決定をするときです。例えば離職などにみられる心理的不安定な場面を取り上げて考えてみましょう。
ビジネスパーソンの悩みのひとつが人間関係です。なかにはそれが原因で転職したという人もいるかもしれません。そのようなかたちで同僚や部下を失う前に、回避することができていたらと思う人も多いのではないでしょうか。
傾聴は、もともとカウンセリングの技術ですが、ビジネスシーンにおいても、顧客と従業員、上司と部下、同僚間といった関係性におけるコミュニケーションに応用されています。
傾聴は相手の感情や心理を相手の発言から傾聴を通して、想起し、相手と同じ感情を共有するという行為です。
しかし相手から見たとき、感情を理解しそれらを互いに共有したかというと疑問です。ここにコミュニケーションを重ねる意味があります。
より深く相手の感情を理解するためには、相手の感情に同期し、価値観や相手のナラティブに寄り添うことで効果が発揮されます。このナラティブとは物語です。人間関係に悩む部下や同僚に対し、現時点に至るまでのストーリーを聞きながら、ケアや改善、問題解決の糸口をナラティブの世界から見つけます。
このような傾聴スキルはナラティブ・アプローチと呼ばれ、社内における人間関係の構築や、仕事へのストレス軽減、社員のモチベーションアップなどにも良い影響を与えます。
ここでもう一つ、イソップ物語の『アリとキリギリス』からナラティブ・アプローチに関する解説を紹介します。
『アリとキリギリス』は、2匹の昆虫を擬人化した昔話として有名ですが、アリの描写=計画性が優位、キリギリスの刹那的な行動が劣位というふうに、わかりやすい対立構造を描いています。小さな子どもたちに読み聞かせることで、大人になるころには「計画は重要である」「刹那的な生き方は好ましくない」というナラティブが根付いています。
日本社会や資本主義の中、あるいは組織や職場の中においても、このような思い込みやバイアスが存在し、そのドミネート(支配)の一面からドミナントナラティブと呼ぶことができます。
ドミナントストーリーとは、当事者が抱える問題を認識し感じる物語です。ドミナントストーリーは、当事者が過去から連綿と受け継いできた物語であり、問題が染み込んだ物語です。
反対に、個人の経験や背景、価値観によって、このドミネートされ固定化されたナラティブに異議を唱えることもあるでしょう。このような異議や異なる解釈は、「カウンターナラティブ」や「オルタナティブナラティブ」とも呼ばれることがあります。これが、オルタナティブストーリーを創り出します。
思い込みやモヤモヤがあったり、物語が同じであったりしても、「オルタナティブナラティブ」という視点を加えることで、未来においてオルタナティブなストーリーを想像することができます。これは、大きな問題解決につながります。
この視点をもってして『アリとキリギリス』の寓話を改めて見てみると、勤勉であれというドミナントストーリーに対し、それとは真逆の解釈ができます。
不確実な未来に怯えて現在を犠牲にするのではなく、勇気をもって今のこの瞬間を燃焼させたキリギリスは堕落とは違った一面が見えてきます。
刹那的に見えていたことから一変して、音楽をこよなく愛し、今しかできないことをやって後悔のない人生をおくるというメッセージに感情移入し、大胆不敵なキリギリスを思い浮かべる人もいるのではないでしょうか。
ここから言えることは、ドミナントストーリーが組織や個人の抑圧的な心理を産み出していたとしたら、オルタナティブストーリーによって抑圧から解放されるという動機と衝動を生み出すということです。
つまり、新しいナラティブは、新しい解釈を生み、新しい可能性と方向を示すことにつながり、あらゆるビジネスシーンにおいて有用であると言えます。
この別の観点を浮かび上がらせる事こそ、オルタナティブナラティブの目的であり、柔軟な発想や多面的な視点が社員にそなわって行くことが重要です。
アリとキリギリスの刷り込みように固定観念で固められた人材は、これまで多くの日本の職場で量産されてきました。変化したことで必ずしも明るい未来とも限りませんが、現代において変化しないことは退化であり、成功とは無縁の選択肢です。
上司・部下分け隔てなく対話できる環境を整え、その時々の最適解をチーム全体で導き出すというのが傾聴のその先にある世界線ではないでしょうか。
傾聴をビジネスに取り入れるメリット
傾聴のスキルは、ビジネスの場で活用することで、さまざまなメリットにつなげることができます。ここでは、以下の2点について詳しくご説明します。
- 信頼関係を築くことができる
- 業務が円滑に進む
信頼関係を築くことができる
傾聴は相手の立場に立って、その状況や感情を理解することです。繰り返しになりますが、自分の存在をありのままに受け止めてもらえたという経験は、話し手に安心感を与え、聞き手に対する信頼感を醸成します。それによって、相手から「またこの人に相談したい」と思ってもらうことができるのです。
こういった相互関係を築くことができれば、顧客や取引先だけでなく、上司・部下間や同僚との間でも意思の疎通を図りやすくなるでしょう。
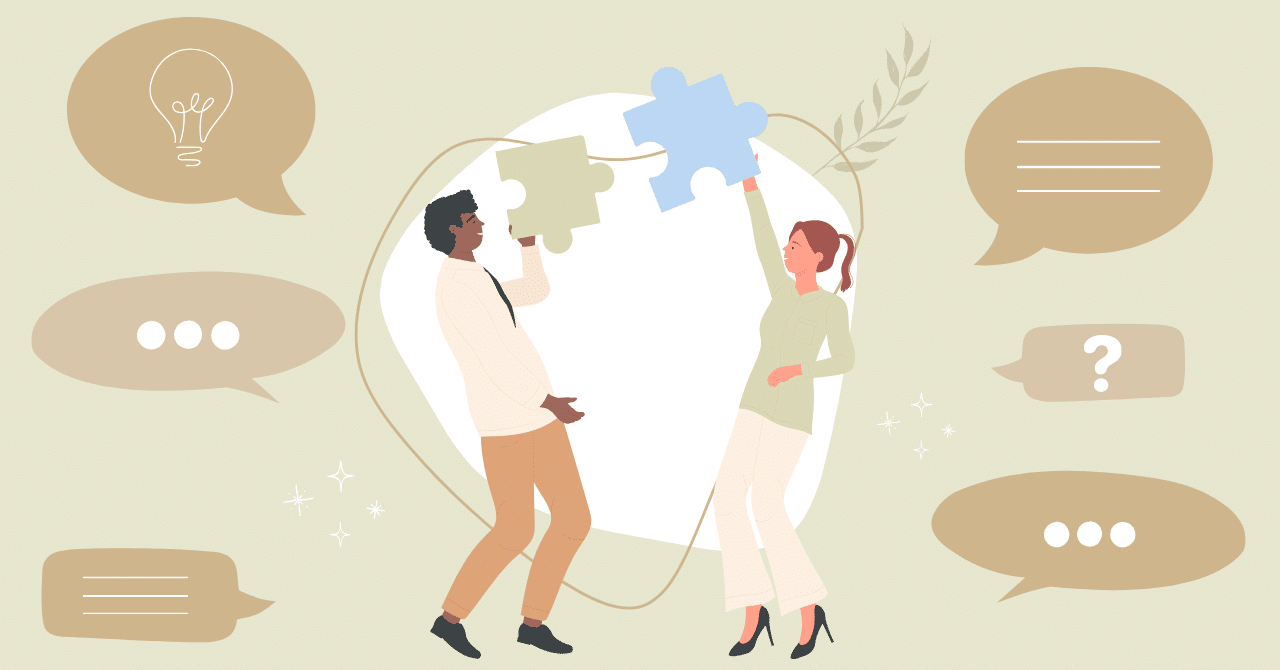
1on1(ワンオンワン)とは?目的やメリット、部下の成長を促すテクニックや話題例を紹介
最近は米国シリコンバレー由来の「1on1(ワンオンワン)」という新たなミーティングの手法がトレンドになっています…
業務が円滑に進む
傾聴における、相手を受け入れて共感・理解するというプロセスは、業務の円滑化にも寄与します。
業務を円滑に進めるにはさまざまな方法がありますが、話し合いながら進めていく業務の場合は、双方が信頼し合っていることが重要です。
例えば上司・部下間であれば、よく知らない上司からいきなり指示されたり、指導されたりするのは、部下としてはあまりいい気分にはならないものです。
しかし、あらかじめ信頼関係を構築できていれば、「あの人の言うことなら信頼できる」「あの人に協力しよう」という気持ちになります。
さらに、傾聴スキルを身に付けるということは、相手の望んでいることを理解し、それを叶えるために動けるようになるということです。そのため、傾聴のスキルを磨いていくと、痒い所に手が届くような人材になっていき、業務を円滑に進めることができるようになることが期待できます。
傾聴を高める具体的なやり方
ここでは、ビジネスシーンにおいて傾聴を行う際に意識したい、具体的なやり方をご紹介します。
- 問題を明確にする
- 相手の気持ちに注意を払う
- 聞いていること、理解していることを相手に伝える
- 状況に応じて適切な問いを立てる
- 聞くが8割、話すが2割
- 傾聴を学ぶ方法
問題を明確にする
ビジネスの文脈におけるコミュニケーションは、その背景に「進めるべき業務」や「解決すべき課題」が存在し、相手に対して何らかの意識や行動の変化を促すために行われます。傾聴の場面においても、相手をありのままに受け止めつつ、解決すべき問題は何なのかを具体化していくことが重要です。
話を聞くとき、こちらから尋ねなくても相手が1から10まで話してくれる、などということはなかなかありません。事情は伝えても心境は伝えないというケースや、自分が抱える悩みのどこに問題や課題があるのかわからないまま相談してくるケースなども多々あります。
より具体的な話を引き出し、解決すべき問題を明確にするためには、会話の中に以下のような問いを挟むことが有効です。
- 「その後どうなったのですか?」
- 「その行動に、どんな気持ちになりましたか?」
- 「話をもっと聞かせてくれませんか?」
このような質問で相手の話を促すことで、話し手は「自分の話に興味を持ってくれている」「寄り添ってくれている」「力になってくれそう」という気持ちになり、話しやすくなります。そして、聞き手はより具体的な話を引き出すことで、問題を明確化しやすくなります。
また、現在にビジネスにおいては、「バズワード」「専門知識が必要な言葉」「レトリックの強い表現」「異文化」など、言語レベルでも聴く側も話す側も共通理解をしているつもりでも、ミスリードしている場合があります。聴いている情報の解像度を上げ正確性を求めれば求めるほど、質問も難しくなりますし、聴かれる相手に心理的なプレッシャーを与える可能性すらあります。
「医者」と「患者」のコミュニケーションを想像するイメージしやすいです。医学的論理を前提に、医者は「質問」と「傾聴」という問診行為から体の「問題」を明確化しています。医師は権威が前提にある為、信頼関係はすでにあります。しかし、問診の段階では、患者を不安にさせるような「詰問」をする医者は存在しません。医師は心理的安全性を確保し、医学や論理を前提に質問し、傾聴することが求められます。傾聴の初期段階では、早急に質問攻めや一問一答に至らないよう留意する必要があります。質問する前に、論理的背景を考慮し、相談者のペースを合わせて、様子を見ながら質問していくべきです。
相手の気持ちに注意を払う
傾聴の際は、
- 相手がどんな気持ちで話をしているのか
- 相手がどんな精神状態なのか
という点に細心の注意を払いましょう。特に日本人は、自身の内面に関して積極的に話さない傾向があります。それだけデリケートな部分であることをあらかじめ認識し、無理に踏み込まず、相手のペースで徐々に徐々に話を深めて行きましょう。そのためには、相手をよく観察して状況を見極めることが重要です。
また、相手が話をしているときは、相手の話を聞くことに集中し、ほかのことは考えないようにしましょう。聞き手が上の空だったり、相槌や返しが適当だったり、心にもないことを言っていたりすると、そのことは必ず相手に伝わります。「話を聞いていない」「信頼できない」という印象を相手に持たれてしまうと、コミュニケーションの目的を達成できなくなってしまいますので、気をつけてください。
聞いていること、理解していることを相手に伝える
話されている内容に加え、相手の声色や表情、しぐさ、スピード感などにも注目し、頷きや視線・手の動きなどのボディーランゲージやジェスチャーを生かして、聞いていることが相手に伝わるようにしましょう。
相談者が発した気持ちを聞き手が繰り返したり(オウム返し、パロット)、言い換えて伝え直すこと(パラフレージング)で、相手に対して「しっかりと理解してもらえている」という安心感を与えることができます。たとえば、「〇〇が辛くてなんとかしたい」と言われたられば、「〇〇でお辛い思いをされているのですね」と繰り返したり、や「〇〇で□□のような影響が出ているため、どうにかしたいということですね」と、これまでの文脈を踏まえて言い換えたりします。
このように、聞き手が話を振り返ったりまとめたりして話し手に伝えることで、伝えた情報が正確に伝わっているか、自分の気持ちやニーズをしっかり理解してもらえているか、という話し手の不安要素を払拭することができるでしょう。
状況に応じて適切な問いを立てる
傾聴の場では、まず相手への関心を示しながら相手の話に耳を傾け、共感的理解によって信頼関係を構築していくプロセスが必要です。
話し手の言葉を引き出す中で、話し手自身が気付きを得て問題解決にたどり着くことができれば一番よいのですが、状況によっては、「具体的にどうしたいのか」という思考へ相手を導くために、適切な問いを投げかけながら問題解決をサポートすることも必要です。
傾聴を必要としている相手は、自分の本心と実際の言動が一致していない状況にあり、それが何かしらの解決困難な問題につながっています。
そのため聞き手は、相手をありのまま受け止め、相手の立場に立ちながら、相手のどのあたりに葛藤(コンフリクト)があるのかを探る必要があります。
そして、繰り返しになりますが、聞き手が話し手と向き合う際には、聞き手自身の感じていることや考えていることと、話し手に対して表現している態度や言葉が一致していることが大切です。率直な気持ちや態度が相手にストレートに伝わるのと同様に、取り繕った態度や演技も相手に伝わってしまいます。相談者の気持ちになって、「自分が逆の立場だったらこう扱ってほしい」という視点で対応しましょう。
もし、相手の発言に矛盾や偏った考えが含まれていたとしても、否定的な態度を取るのは禁物です。なぜ相手がそのような発言をするのか、その背景を深堀りできるような問いを立て、問題の本質に徐々に近づくようにしましょう。
聞くが8割 話すが2割
対話における聞き手の姿勢は相手の話を7~8割聞き、残りの2~3割程度で自分の意見を述べることが望ましいとされています。相手の発言に共感し、共体験者として適切なリアクションによってこちらの理解度も伝わります。相手が黙っている場合や考え事をしている場合は、その様子に同調しつつ、時には待つことも必要です。
この考え方は非常に重要なコミュニケーションの原則を反映しており、対話や人間関係において、話すことよりも聞くことが圧倒的に重要だということを強調しています。 以下にポイントを2つまとめます。
相互理解: 相手が自然と話せる状態にあるということは、相手の意図や感情、立場をよりよく理解してくれるという信頼があってこそできるものです。
呼応と共感: こちらからの問いかけに対し、相手が安心してオープンな対話がなされることで共感が生まれます。また相手に質問を投げかけ、相手の話に基づいて考えを発展させることで、誤解や行き違いが少なくなり深い対話ができるようになります。
傾聴を学ぶ方法
学びといっても特別な研修を受講せずとも、業務中の実際のコミュニケーションや、課題が発生した場面で傾聴を意識するだけでも変化があります。日常のコミュニケーションの中で、相手に自分の聞く姿勢やコミュニケーションについてフィードバックを受けるなどして振り返りを行い、うまくいった点や反省点を次に活かしたり、ロールプレイングを用いて、効果的に傾聴力を高めることもできます。
まとめ
傾聴は、話をただ聴く というだけではありません。耳だけでなく心を傾けて相手の気持ちに寄り添い、共感や理解を繰り返し、言い換えなどの表現を用いるなど、多くの工夫が必要です。そして、実践を重ねることで傾聴スキルは向上していきます。
傾聴によって対顧客や職場内の関係性が良くなると、意思疎通を図りやすくなり、業務の円滑化につながります。そのため、組織においても積極的に取り入れることをお勧めします。
傾聴は、積極的傾聴(アクティブリスニング)とも呼ばれ、聞き手が受け身ではなく積極的な姿勢で相手を理解しようとすることが特徴です。受け身のコミュニケーションにおいて、人は聞いたことの大半を忘れてしまいますが、アクティブに聞くことで、内容をしっかり把握することができます。社員がアクティブリスニングのスキルをつけることで、社内の話し合いがスムーズになったり、会議や打ち合わせの席で積極的に発言できたりといった効果も期待できるでしょう。
傾聴を組織で実践したいという方は、ソフィアまでお問合せください。
関連事例
よくある質問
- 傾聴とは何ですか?
単に相手の話を聞くのではなく、相手の立場に立って共感しながら、相手の話に積極的に耳を傾けることを意味します。
- 傾聴をビジネスに取り入れるメリットとは何ですか?
・信頼関係を築くことができる
・業務が円滑に進む

株式会社ソフィア
先生
ソフィアさん
人と組織にかかわる「問題」「要因」「課題」「解決策」「バズワード」「経営テーマ」など多岐にわたる「事象」をインターナルコミュニケーションの視点から解釈し伝えてます。
株式会社ソフィア
先生

ソフィアさん
人と組織にかかわる「問題」「要因」「課題」「解決策」「バズワード」「経営テーマ」など多岐にわたる「事象」をインターナルコミュニケーションの視点から解釈し伝えてます。