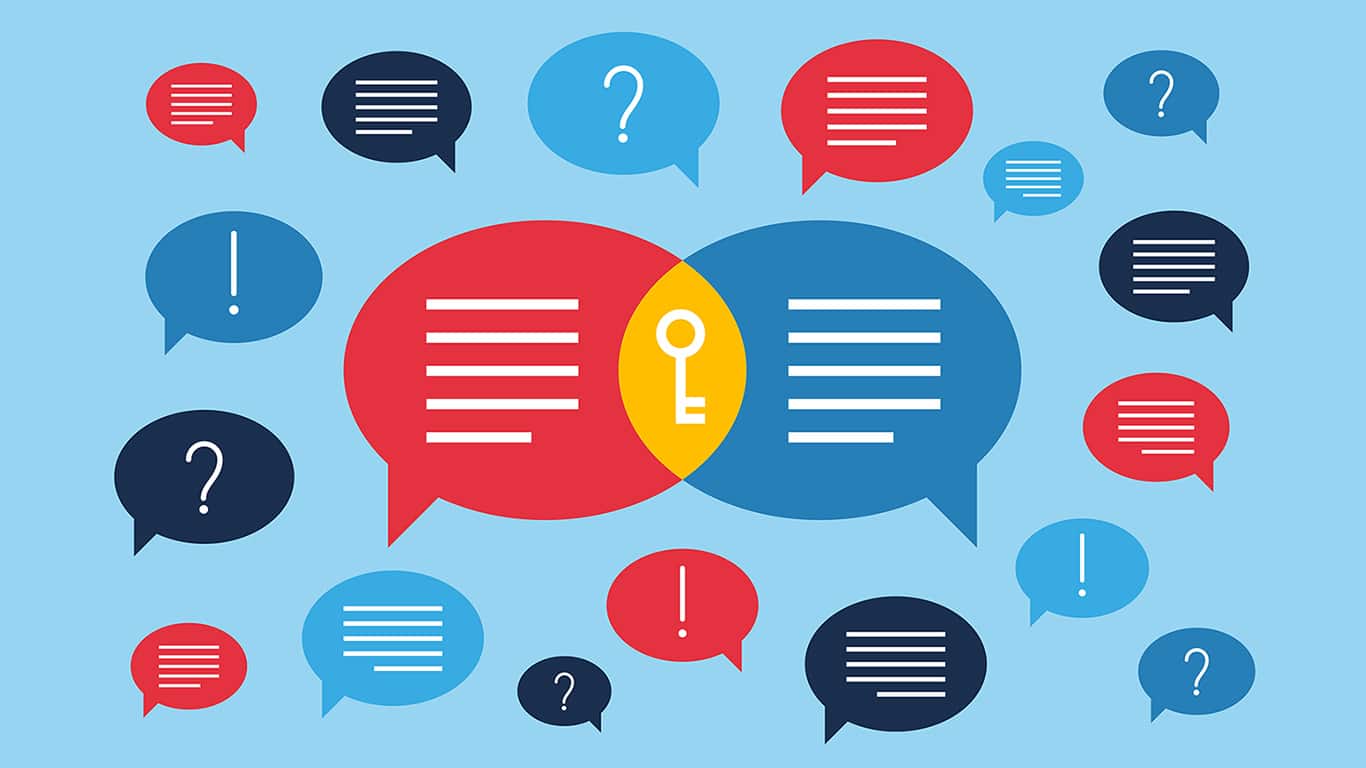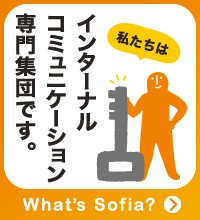2025.01.24
職場の人間関係の悪化を招く原因と起こり得る問題とは?改善する方法も解説

目次
職場における人間関係は、仕事の成果に影響するものです。関係性が悪化すると、社員のモチベーションの低下、精神的なストレスや疲労などにより生産性が低下することが懸念されます。ここからは、職場で人間関係の悪化が起きる要因と悪化した人間関係が組織にどのような影響を及ぼすのか解説します。さらに、人間関係が悪化した場合の改善方法も紹介するので参考にしてみてください。
職場の人間関係に悩む人はどのくらいいるのか?
職場の人間関係に悩みを抱えている人はどのくらいいるのでしょうか。
日本労働調査組合が行った調査によると、職場での人間関係に疲れ・悩み・ストレスを感じている人は、全体の29.2%にのぼることがわかっています(2021年7月実施のアンケート)。さらに同調査では、職場の人間関係に悩んだ結果、退職を検討した経験がある人の割合は、全体の約6割であることが明らかになりました。
社員が職場の人間関係に悩むことは、モチベーションの低下、精神的なストレスにつながり退職を検討する要因になります。
社員が働きやすい組織づくりや離職率を下げるためには、職場で良好な人間関係を築くことが重要です。
職場の人間関係の悩みやストレスが心身に及ぼす影響・症状
職場での人間関係は、その会社に勤めている限りほとんど毎日続いていきます。
人間関係がうまくいかないと慢性的にストレスが溜まり、心身に影響を及ぼしてしまうでしょう。
ここでは、人間関係に悩みやストレスを抱えた場合に考えられる影響や症状について解説します。
精神的影響
まず考えられるのは、精神的な影響です。人間関係に悩みを感じているのに毎日同じ人と関わり続けなくてはならないことは、大きなストレスにつながります。
場合によっては、強い恐怖感や焦燥感を感じるケースもあるでしょう。
日頃からストレスを感じていれば、次第に職場に行くのが嫌になり、職場に対する貢献意欲や、モチベーションの維持が難しくなります。悩みを抱えたまま無理をしてしまうと、うつ病や適応障害に陥る可能性もあります。
肉体的影響
人間関係のストレスが原因で肉体的な症状が出現するケースもあるでしょう。
たとえば、動悸が激しくなる、頭痛や腹痛、めまいがするなどの症状が考えられます。
また、具体的な症状として現れなくても、慢性的な倦怠感を感じたり、疲れがなかなかとれなかったりという身体の変化を感じることもあります。ストレスを感じる職場に勤務することで、体調面にも悪影響を及ぼす可能性が考えられます。
行動的影響
精神的・肉体的な影響が起因して、行動にも影響が出ることがあります。
集中力の低下や、思考がうまく働かない結果、仕事上のミスが頻繁に起きることが考えられます。
また、遅刻や早退、欠勤が増えることもあるでしょう。さらに、急に身だしなみに気をつかわなくなったり、周りの人とのコミュニケーションを遮断したりという変化が生じる可能性もあります。
いずれにしても、目に見えて変化がわかるものなので、周囲が変化に気づき対策を取ることが大切です。
職場の人間関係が悪化するほとんど原因はコミュニケーションエラーによるもの
職場の人間関係の悩みは精神的なものだけでなく、肉体的、行動にまで悪影響を及ぼします。
そのような事態を未然に防ぐために、まずは人間関係が悪化する原因について理解を深めましょう。
改善方法として挙げられるのは「コミュニケーションエラー」を防ぐことです。
コミュニケーションとは、人と人とを、言葉でつなぐ道具です。このコミュニケーションが不足していると、人と人とが繋がれなくなってきますので、当然、誤解や行き違いが生じやすくなります。
コミュニケーションエラーは、職場だけではなく、家庭内や学校、友人関係においても、もちろん発生します。
ただし、職場の場合嫌になったからその人と離れるという事が中々できない事が現状です。
であれば、いかにコミュニケーションをエラーを事前に防ぐことができるか?が、重要となってきます。
コミュニケーションエラーに具体的に論じる前に、まず、コミュニケーションができるだけ多い職場やコミュニケーションの方法ができるだけ多彩である職場がより良い職場という事を確認していおきましょう。
私たちのコミュニケーションは、言葉だけで、成り立ってはいません。
服装や表情、態度などこれらも、コミュニケーションの道具です。それらを使いながら、それぞれの社員が、他の社員の対して、何度も多彩に自分の目の前の目標やそれに対する手順、そして達成度を伝えていく必要があります。
コミュニケーションは、くどいほど何度も行い、様々な方法で、それぞれの意図を、お互いに確認し、定着し合うべきです。
これが、行われている職場こそ、風通しの良い職場であり、そこからは自由な発想や相手への思いやり、そして一致した目標への動機付けが自ずと生まれます。
コミュニケーションエラーは、労総生産性を下げ、職場の雰囲気を悪くし、引いて退職率を上げてしまうという非常に厄介な問題です。
この記事で、是非、職場のコミュニケーションエラーを減らし、生き生きとした生産性の高い職場を創り上げていきましょう。
実は、コミュニケーションの達成は、完全に行われることはほとんどありません。
大抵な不完全なコミュニケーションであり、それでも何とかなっているのは、その仕事の重要性がそれほど高くないからです。
一方重要性の高い仕事をするときには、コミュニケーションの完成度は高くなければなりません。
質の高い仕事をし、より多くの利益を上げるためには、互いに何度も確認し合うコミュニケーションが不可欠で、それがどれほど重要なのかを社員一人ひとりが認識し共有されている事が大前提です。
コミュニケーションエラーが起きるものだという前提に立ち、
- どうすればそれを減らすことができるか?
- どうすれば完成したコミュニケーションを達成できるか?
を探っていきましょう。
コミュニケーションエラーとは?
コミュニケーションエラーとは、コミュニケーションがうまく機能していないことを意味します。
たとえば、上司が部下に対して資料作成を依頼したのに、なかなか完成しない状況があったとします。
そこで上司が部下に進捗を確認すると、「わからない点があったため滞っていた」と答えました。
このとき上司は「なぜ早く相談しなかったんだ」と、相談に来なかったことを叱ります。
一方の部下は、自力で解決しようと努めていたのであれば、叱られるのは不本意とに思うかもしれません。
上司から根本的な必要な知識を最初に教えてくれればこうはならなかった、と考えに擦れ違いが起きてしまうこともあります。
もし仕事を依頼する段階できちんとコミュニケーションが取れていれば、このようなすれ違いは回避できたのではないでしょうか。
互いがどのような姿勢で仕事に取り組むべきかを擦り合わせてから業務を始めればよかった、それだけなのです。
しかし、コミュニケーションエラーが生じると、上記のようなトラブルが発生し、その結果、人間関係が悪化する可能性があります。
一度トラブルがあるとその人とコミュニケーションが取りづらくなり、関係の悪化に拍車がかかっていきます。
コミュニケーションエラーが起きる要因
コミュニケーションエラーを防ぐために着目したいのが「可視化できない要素」です。
業務を形成するために必要なプロセスには、業務ステップやタイムスケジュール、タスクの割り振りなどの可視化できる要素と、モチベーションやコミュニケーション、職場の雰囲気や人間関係といった、可視化できない要素があります。
可視化できる要素は、多くの業務現場でケアされています。
しかし、可視化できない要素は把握や改善が難しいためケアが後回しにされがちです。
そもそも職場とは、功利に基づいた契約的な関係と感情にに基づく人間的関係の微妙なバランスの上に成り立っており、組織の建前のようなコミュケーションだけでは、このバランスをとることは不可能です。
時には感情的な思いや嘘偽りのない率直な意見の交換などの詭弁やごまかしのないコミュニケーションが必要になります。
会社から社員に対するコミュニケーションは、多くの情報を多くの社員に届ける必要があるため、抽象的かつ演出的な形式をとります。
そうしなければ、全員の顔と名前が一致するような小さな組織でない限りは、情報を伝達することが困難であるためです。
組織と個人は、物理的に距離があるため、職場と比較して率直さよりも、形式的なコミュニケーションを取ります。
一方で職場の場合、コミュニケーションをその場ですぐに取ることができます。
そのため職場内のコミュニケーションは、具体的かつありのままで、時間的に空間的にも同期化されています。
組織と個人のコミュニケーションと、職場やプロダクトのような小集団では、形式的なコミュニケーションよりも、率直な人間味のあるコミュニケーションが生産性の鍵になっているという事です。
しかし、リモートワークの導入などによって労働環境が大きく変化している現代の職場では、従来は考える事のなかったコミュニケーションに関する問題が多く生じています。
職場は組織内における小さな組織です。そのため、職場の問題は、最終的に組織の問題へとつながっていきます。
特に、現代の多くの職場では、さまざまな業務をメンバーが入れ替わりで行うようになり、新しいプロジェクトが発生するたびに人間関係が新たに構築される傾向が強くなっています。
だからこそ、可視化できない要素についても重要視し言語化ししっかりと、コミュニケーションを図らなければなりません。
現在のようなプロジェクト型の業務などは、大きなリスクに引き起こすきっかけになることは、多くリーダーの既知の事実です。
コミュニケーションエラーを避ける具体的な方法として、確認作業を怠らない事が挙げられます。
現在の自分の目標と手順、そして達成度を絶えず、上司や同僚に発信しておき、それを受信した上司や同僚の方でも、できれば繰り返す形で、了解のサインを返しておけば、後で、こんなはずじゃなかったという事は避ける事できます。
入念な確認作業の例として航空機のパイロットが挙げられます。
機長と副操縦士はコックピットで、席に着いてから離陸して巡航高度となり、着陸して、機体が駐機場に止まるまで、ほぼ全て手順をお互い声に出して確認し合っています。
多くの乗客の生命は預かるパイロットは、分かったつもりは許されません。互いに声に出して、コミュケーションを取る事によって、未然にエラーを防いでいるわけです。
職場のコミュニケーションも、この確認作業を参考に取り入れてみてはいかがでしょうか。
この確認作業は、形式的に確認すれば生産性は上がります。しかし、この機長と副操縦士の関係にひびが入っている状況ではどうでしょうか?
副操縦士の機長に対する形式なコミュニケーションを、機長は慇懃無礼なコミュニケーションと誤った解釈をする事もあるかもしれません。
特に航空機の運航状況が平常に進んでいれば、大きな問題になることはありません。
しかし、この関係性が悪い状況と航空機の運航状況が異常を起こすタイミングが同時に起きたら大惨事につながりかねません。
確認作業とは、仕事の状況を相互に確認するという事だけではなく、仕事をしている人の状況も同じく確認する必要があります。
仕事と人間の感情は相互に連動しているという事は、仕事も悪く、関係も悪い状況が同時に起これば、航空機事故とまではいかないモノの、大きなリスクに発展することは間違いありません。
その事故やリスクは、その職場の人間関係を決定的に破壊するでしょう。
各航空会社は現在、機長と副操縦士の相性ができるだけよくなるように、機長や副操縦士をフライト毎に相手への印象や気づいた事、そして自分との相性の良し悪しを報告させています。
このデータを積み上げていけば、自然と相性の良い相手とペアを組むことになり、会話の行き違いや情報のやり取りのミスという事が、減らせるシステムになっています。
当然職場でもこの方法を導入し、同じチームに相性の良い社員を集める事で円滑なコミュニケーションを図っています。
職場の人間関係が悪化することで起こる問題
コミュニケーションエラーの回避は、円滑な業務運営のために欠かせない要素です。社員が不必要なストレスを感じない職場を目指すためには、目に見えるものだけでなく、目に見えない人間関係や雰囲気についてもケアすることが求められます。
現代の職場は、人間関係が悪化しない方が不思議なくらい、難しい環境におかれています。上記でも解説しましたが、組織のコミュニケーションは、多くの情報を多くの社員に届ける必要があるため、時間的にも空間的にも分離された環境で、抽象的かつ演出的なスタイルをとることになります。一方で職場でのコミュニケーションは、具体的かつありのままのスタイルで、時間的も空間的にも同期された環境の中で行われます。つまり、組織のコミュニケーションと、職場のコミュニケーションは、そもそも大きく違ったスタイルになっているのです。
組織が大きくなればなるほど、スタイルの違いは顕著になります。2つのスタイルに優劣の差はありませんが、双方のバランスを調整する必要があります。バランスが悪くなれば、まず職場に問題が起こり、それが最終的に組織の問題へとつながるでしょう。
特に現代の職場は、社会課題やSDGsなどの複雑で曖昧な課題が多くあり、仕事の目標や意味付けが不明確になりがちです。さらに職場の人間や働き方も多様化していて、自分の役割を把握することも困難になっています。このような難しい環境の中で、GDPの約7割はサービス業であり、人材自体が付加価値になるビジネスが増えているのも事実です。そのため、職場のコミュニケーションや人間関係に、より注力してアプローチする必要があるのです。
職場の人間関係は自分でつくっている?
職場の人間関係が悪くなってしまった場合、その職場について「なぜこんな職場なのだ」と不平不満を感じる人も多いかもしれません。しかし、そもそも職場の人間関係は、いったい誰が形成しているのでしょうか。
ここでは、スペインの哲学者であるホセ・オルテガ・イ・ガセットの考え方を参考にします。彼は、人の存在について「人間とは、人とその周囲の環境である」と定義しています。つまり、人間が環境をつくり、その環境に、人間はまた影響されているということです。人間と環境はどこまでも不可分な関係であり、両者を独立したものとして考えるのは無理があるのです。
オルテガの哲学のキーワードとして、「大衆」があります。オルテガは、大衆が「反逆」するという表現で、現代社会をそれ以前のエリート支配の社会から区別しました。オルテガが「大衆」という言葉を使った背景には、現代においては、個人はバラバラでは存在しえず、絶えずと周囲との相互作用によって存在しているという認識があります。私たちも企業という組織を考えるとき、バラバラな社員ではなく、組織の中の社員や職場の中の社員という視点で、考えるべきでしょう。
職場の人間関係に不満がある場合も、その悪い雰囲気を形成しているのは、職場を構成する一人ひとりであると考えることができます。だからこそ、不満があれば、それを改善するために自らがアクションを取るべきかもしれません。自身が人間関係を改善するきっかけになれるかどうか、検討してみることも大切です。
職場の人間関係を改善する方法
ここからは職場の人間関係を改善する方法について解説します。そもそも、上記で触れた職場の人間関係や雰囲気は、目に見えないものであり、アプローチするのが難しいものです。そのため、可能であれば組織を作る初期段階から「職場の設計」にこだわっておくことがおすすめです。職場の設計が悪いと、どんなに優秀な人たちで構成されたチームであっても、目的を達成できない、成果が上がらない場合があります。
また、人間関係が悪化する要因にもなりかねません。すでに組織の人間関係が悪化してしまっている場合は、人事改革に着手するのも手段のひとつです。特にリーダーは職場にとって大きな存在であり、雰囲気やチームカラーにも影響を与えます。職場のリーダーが変わることで、組織が良い方向に向いた事例は多くあり、リーダーをはじめ、構成員を変更することは、組織の業績向上につながる可能性があります。また、リーダーは、下記の要素に注意しながら職場に改革を起こしていかなければなりません。
共通言語を作る
同じ組織にいても、一人ひとりは違う人間です。価値観の違いや、考え方のズレがあるのは当然のことです。価値観が違うことで理解の擦れ違いが起こることもあり、擦れ違いが慢性化すれば、互いに憤りを持った関係性へと発展しかねません。
異なる価値観の人同士が円滑に意思疎通をするためには、組織内に共通言語を設けることが効果的です。共通言語を持っておくと、コミュニケーションの際にあれこれ相手の意図や反応について考える必要がなくなり、心理的なハードルも下がるでしょう。結果、効率的に気持ちや情報を伝え合える関係になれます。
共通言語は同時に、社員同士の団結心や忠誠心をも醸し出してくれます。外には、理解できなくても、内輪で理解し合える共通言語は、その組織に入る為の、言わば、「会員証」みたいな役割を果たし、共通言語を操れる人が、仲間であるという連帯が産まれます。
業務以外のつながりの場を作る
業務上の人間関係が行き詰まった場合は、雰囲気を変えて業務以外のつながりを深めるのもいいでしょう。勉強会や社内レクリエーションなど、業務とは離れた場所でコミュニケーションが取れる場を設けましょう。業務から離れた環境であれば、仕事上の上下関係や立場を忘れてコミュニケーションを取ることが可能になるかもしれません。一度フラットなつながりを作ることができれば、業務に戻っても心置きなくコミュニケーションが取れる関係になるきっかけになります。
レクリエーションや飲み会は、業務とは関係ないので必要がないという考え方もあるかもしれません。しかし、企業には、短期の目標だけではなく、長期の目標もあります。短期目標ならば、達成するために、業務上の円滑さが保証されるだけで良いかもしれません。一方、長期目標の場合、長い時間が掛かる故に、社員同士の多様なコミュニケーションのチェンネルが、不可欠となります。目標が大きく、長期的であればあるほど、一見無駄に見える、業務以外の交流の場が、大きな意味を持ってきます。
理想的な方法としては、レクリエーションや飲み会で、多様なチャンネルを社員同士で創ることにより、実際業務では、それほど、コミュニケーションを取らなくても、円滑に業務が進むという状態が挙げられます。一言で言えば、仕事以外の場所でコミュニケーションを密にすることによって、仕事に向き合うときには、コミュニケーションではなく、仕事そのものに集中できるという事です。コミュニケーションは目的ではありません。あくまでも、業務を最適化する手段に過ぎず、本当に仕事に集中する時には、コミュニケーションなど、必要ないとも言えるでしょう。
コミュニケーションツールを取り入れる
人間関係を構築し直したい場合には、コミュニケーションの頻度を上げることも大切です。気軽に意思疎通できる環境があれば、気持ちの擦れ違いが減り、信頼関係を構築しやすくなるでしょう。コミュニケーションにおける心理的なハードルを下げるためには、コミュニケーションツールを活用しましょう。例えば、ビジネスチャットや社内SNSなどがおすすめです。メールや電話とは違い、些細なことでも意思疎通できるようになり、コミュニケーションの頻度が自然にアップします。
コミュニケーションスキルを向上させる
職場の人間関係の悪化を防ぐためには、コミュニケーションスキルを向上させることも重要です。以下のようなスキルを身につけると、スムーズに人間関係を構築できるでしょう。
- ディベート
- 対話
- ディスカッション
- ファシリテーション
まず、ディベートについては、様々な意見が出てくることになります。ディベートでは、意見の多様性は、あればあるほどよく、アジェンダに対する批判も、広く集められることになります。
批判も含め、ディベートの段階で、議論の幅を大きくしておくことによって、後の段階で、こんなつもりではなかったのに、という想定外の状況が発生する可能性を低くできます。
特に日本社会では、失敗することが、忌避されるので、なおさら、ディベートの段階での意見の多様性は、重要となってきます。
次に、対話が来ます。対話は社員の感情や価値観の違いを、予めすり合わせて、合意や共感をしやすくします。
日本人は感情や価値観のぶつかり合いを避ける傾向がありますが、対話の段階で、その感情や価値観の違いを十分にすり合わせておけば、後にアジェンダの実行段階では、スムーズに業務を運ぶことができます。
面従腹背のような建て前は良いが実は腹の底では別の感情が渦巻いているようでは、業務はスムーズに見えて、成果が出ないことは多くあります。
ディベートで多くの意見を出し、対話で感情のすれ違いを減らした後、ディスカッションの段階に入っていきます。
ディスカッションの目的は、合意形成であり、複数の社員がディスカッションの後に、行動に移れる状態にすることです。
従って、そのディスカッションが成功しているかどうかは、各人が行動できるかどうかになります。
ディベートの段階で、意見が出尽くしていない、曖昧な部分がある、などがあるようであれば、行動には移りません。
各人が本音では、「やりたくない」「自信がない」というような内なる感情のしこりが残っているのであれば、やはりこれも行動には移れません。
つまり、ディスカッションは、ディベートにより論理や理屈の多様性と対話による感情の多様性の集大成です。
ディスカッションができない、合意形成できない、会議の後すぐに社員が行動に移らないような職場の状況がある場合は、ディベートや対話で論理や感情を整理する必要があるかもしれません。
ファシリテーションの目的は、ディスカッションをできるだけ、分かり易くして、合意形成がより容易になることです。
ファシリテーションの役割がなければ、ディスカッション段階で、中々結論が出ず、妥協点を見つけにくくなったりします。
そのような時、第3者として、ディスカッションの方向を決めていくことこそ、ファシリテーションです。第3者であることが望ましいので、ファシリテーターは、場合によっては社外の人物が務める事もあります。
第3者を活用する場合は、ファシリテーターと参加者の情報の非対称がないように事前に、ファシリテーターは情報を把握し、ファシリテーションに望むことが重要です。又、ファシリテーターは、その場に対して大きな影響力を持つことにもなるので、中立的なスタンスが必要となります。
まとめ
職場の人間関係は、企業の業績を左右するほどの重要なものです。組織のリーダーは、良好な人間関係を作ることに意識的に取り組むことで、組織力を高めていきましょう。職場の人間関係を良くするためには、共通言語を作る、業務以外でつながりの場を作ることが効果的です。また、コミュニケーションツールを取り入れるなどして、社員同士の相互理解を深めていきましょう。
ファシリテーションは、今の多くの日本企業で、導入されつつあります。ディスカッションの方向を各社員にとってできるだけ満足できるものにするためには、ファシリテーションというこの新しい概念を社内コミュニケーションの一部に、取り入れていくことが大きな助けになるはずです。
関連事例
よくある質問
- 職場の人間関係悪化の原因は何ですか?
職場の人間関係が悪化するほとんど原因はコミュニケーションエラーによるもの
互いがどのような姿勢で仕事に取り組むべきかを、擦り合わせてから業務を始めればよい。
- 職場の人間関係を改善する方法はありますか?
共通言語を作る
業務以外のつながりの場を作る
コミュニケーションツールを取り入れる
コミュニケーションスキルを向上させる

株式会社ソフィア
先生
ソフィアさん
人と組織にかかわる「問題」「要因」「課題」「解決策」「バズワード」「経営テーマ」など多岐にわたる「事象」をインターナルコミュニケーションの視点から解釈し伝えてます。
株式会社ソフィア
先生

ソフィアさん
人と組織にかかわる「問題」「要因」「課題」「解決策」「バズワード」「経営テーマ」など多岐にわたる「事象」をインターナルコミュニケーションの視点から解釈し伝えてます。