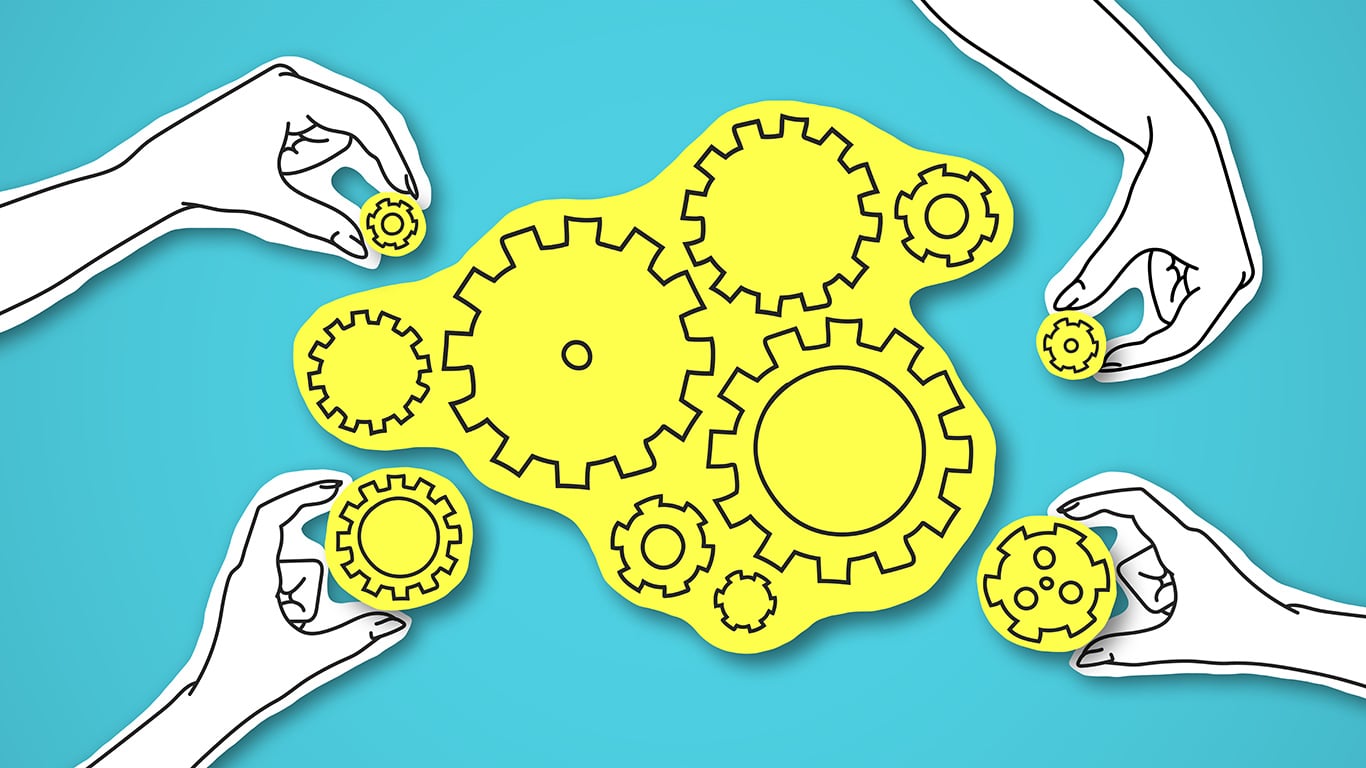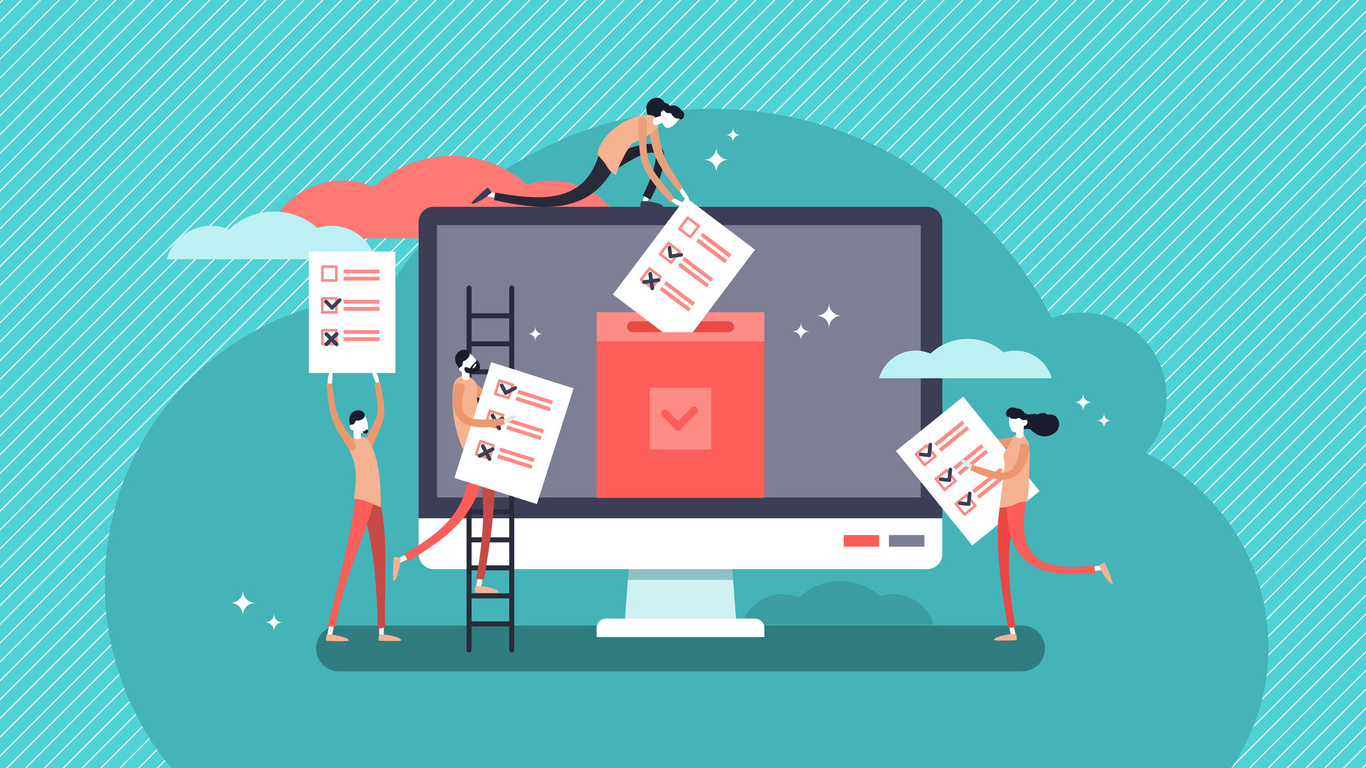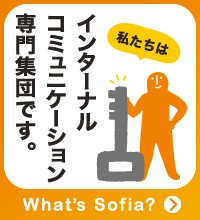2023.05.18
パーパス経営とは?経営理念との違いや策定のポイントについて紹介

目次
「パーパス経営」とは、社会における自社の存在意義を掲げたパーパスを軸に企業経営を行うことです。昨今のビジネスシーンでは、このパーパス経営に注目が集まっています。しかし、そもそもパーパス経営とは何か、なぜ必要なのか、明確に理解できていない方も多いのではないでしょうか。
この記事では、パーパス経営の言葉の意味から重要視される背景、メリットまで詳しく解説していきます。また、類似した概念である「経営理念」との違いや関係性についても整理していきます。
パーパスと経営理念の概要
まずは、パーパス経営と経営理念という言葉について説明しながらその実態を整理していきます。
パーパスとは
パーパスとは英語で「purpose」と書き、「目的」や「意図」などの意味を持っています。ビジネスの文脈で使用される場合は、企業の掲げている目的や、企業運営の意図などを指すのが一般的です。一言でいえば「社会におけるその企業の存在意義」と言い換えることができるでしょう。つまり「パーパス経営」とは、社会における企業の存在意義を軸にした経営のことです。
パーパス経営による企業活動が重要視されるようになった背景には、社会的な課題が関係しています。産業革命以降、企業のさまざまな活動が社会を大きく変革してきました。しかしその活動のほとんどが企業の功利主義に基づくものだったため、環境問題や労働問題、経済格差などを生み出すことになりました。
企業活動によって社会が変革していくにつれて、さまざまな課題も同時に発生してしまったのです。このような課題にアプローチするために、社会における企業の立ち位置を見直そうというのが、パーパス経営の根底にある考え方です。単に金銭的な利益を追い求めるのではなく、社会課題への解決や革新的なイノベーションの創出を意識した企業活動を行おうという目的で、昨今パーパス経営が重要視されています。
パーパス経営について詳しく知りたい場合は、下記の記事をご参照ください。
経営理念とは?
経営理念とは「何のために企業活動をするのか」といった、企業自身が定める経営の在り方を指します。一般的に、経営理念には創業者の信念、企業として大切にするべき考え方、価値観などが表現されていると考えていいでしょう。経営理念の主な機能は、意思決定を下す際の主義であり、原則(プリンシパル)、哲学(フィロソフィー)になります。
どのような企業活動を目指すのか、そのためにどう判断するのかを、経営理念を軸にして考えていくのです。そういったことから、経営理念はパーパスとよく似た概念と言えるでしょう。実際に、経営理念とパーパスを分けて掲げている企業はそう多くありません。
経営理念について詳しく知りたい場合は、下記の記事をご参照ください。
パーパスと経営理念の違い
経営理念とパーパスを一緒のものとして扱っている企業も多いと紹介しました。実際、パーパスは経営理念に近い用語として存在します。しかし厳密には違いがあるので、意味を整理していきましょう。経営理念は、その会社が抱える「価値観」や「想い」を指します。一方でパーパスは、その企業の社会における存在意義を指します。つまり、パーパスの方がより社会的な目線を踏まえたものなのです。
パーパスは、企業が存在する意義や社会的な役割を表し、社会に貢献するための方向性を示します。一方、経営理念は、企業の価値観やビジョンを表し、そのビジョンを達成するための行動指針を示します。経営理念は、経営者が会社のビジョンを実現するための行動指針を示すことが多く、パーパスはより大きな社会的な目的を表すことが多いと言えます。
また、現在では企業が社会や環境との関係性から成果を出すという均衡をとることが必要となっています。その点において、パーパスや経営理念は非常に重要な役割を果たしています。企業が持つべきパーパスや経営理念を策定し、それを社員が共有し、行動指針として実践することで、社会的な信頼を得ることができ、企業の長期的な成長につながります。
経営理念とパーパスの関係性
経営理念とパーパスという2つの言葉には、どのような関係性があるのでしょうか。
会社の経営理念は、会社によって異なる構造で組み立てられていますが、「ミッション・ビジョン・バリュー」の3つの階層に分けられる場合、パーパスはミッションとビジョンのどちらにも含まれます。「ビジョン・バリュー」の2つの階層に分けられる企業の場合は、ビジョンにパーパスが含まれます。
私たちソフィアではこれまで、さまざまな企業のインターナルコミュニケーション・インターナルブランディングを支援してきました。その支援経験から、経営理念とパーパスを明確に分けて運用している会社は上手くいっていないということ、何よりも大切なのはパーパスや経営理念が浸透しているかどうかだということがわかりました。経営理念という言葉には、辞書的な意味だけではなく、組織やステークホルダーがその内容を理解し支持しているという意味も含まれます。
また、企業が外部に発信する際には理念とパーパスを整理し、わかりやすく伝えることが必要です。しかし、社内においては、理念とパーパスを厳密に分ける必要はなく、行動や実務に合わせて解釈を広げることができます。理念とパーパスは、社内においては実務に沿って柔軟に解釈を行うことが重要です。
経営理念とパーパスを明確に使い分ける必要はない?
「パーパス」と「経営理念」は明確に異なる概念ですが、コミュニケーションにおいて明確に意識して発信していない場合が多くあります。これは、組織の上位概念自体において、完全に整合的であるわけではなく、経営環境や課題によって強調される要素が異なるためです。
パーパスや経営理念は、組織の目的を表した形而上の表示です。そのため、コミュニケーションの中で、解釈の幅や奥行きを深めることが重要です。
経営理念においてパーパスが注目される背景
ここまで経営理念とパーパスの関係性を整理してきました。しかし、なぜ経営理念におけるパーパスが注目されるようになっているのでしょうか。主に考えられる2つの理由を紹介します。
企業の社会的意義が重要視される時代
企業というものの在り方が大きく変わっていることも、パーパスが注目される大きな理由です。かつては利益を生み出すための組織であった企業が、今では社会的な課題を解決するために有効な存在として認識されるようになったのです。
実際、オックスフォード大学の教授であるコリン・メイヤー氏は、「企業のパーパス(存在意義や目的)は、単に利益を生み出すことではない。個人、社会、自然界が直面する問題の解決策を企業戦略に組み込み、人々の信頼を増やす努力を踏まえ、利益が出る形で人々の幸福に貢献することだ」と主張しています。
社会課題は国家やそれぞれの地域が解決するものだという認識もありますが、今や企業法人にその役割が期待されるようになっています。企業は軸である主義主張・スタンスからサービスやソリューションを創出して、社会を変えていける影響力を持つため、そのような期待が寄せられるようになったのでしょう。しかし、法人はあくまでも営利集団です。そのため、社会課題をどのように解決していくのかは、明確なイデオロギーを確立した上で、利益の視点も含めた判断がされていきます。このイデオロギーのひとつの軸として、パーパスが必要とされているのです。
多様性が重要視される時代
「多様性が重要視される時代」とは、人の多様性とビジネスの多様性が相まって、複雑化・高度化する現代社会において、企業が生き残るために必要な要素であることを指します。 従来の日本企業は、年功序列や終身雇用といった同質性の高い環境の中で成長してきたため、人々の多様性を反映することができませんでした。しかし昨今、グローバル化により異なる雇用形態や文化を持つ社員が増え、人材の流動化が進む中で、異なるバックグラウンドを持つ人々の協働が求められるようになっています。このような多様性を受け入れ、活かすことが、企業にとっても必要になってきました。
一方で、ビジネスの多様性については、大企業が多角化する中で、意思決定権限や責任が現場に移譲され、企業・地域・業界を越えた連携が増えています。また、前例や経験則では判断できない問題や事象が増え、専門領域・業界・社会をまたぐ複雑な問題を解決することが求められるようになっています。このような状況下で、柔軟性や冗長性が求められ、中心的価値観に基づいたビジネスモデルを構築することが重要とされているのです。
人の多様性があるからこそ、スキルや専門性の多様性が生まれますが、それだけでビジネスが成り立つわけではありません。共通する目的や方向性と言った足場が必要です。そこで、ビジネスにおいてはパーパスが必要となります。パーパスを共有することで、組織内の方向性が統一され、チームワークやコラボレーションが生まれます。
また、パーパスがあるからこそ、ルールを減らして現場に権限を与えることが可能になります。現場の自由度が高まることで、不確実な状況に対応する柔軟性が生まれます。パーパスは、ビジネスにおける原則であると同時に、現場の自由度や柔軟性を高めることができる重要な要素です。
経営理念やパーパスがないと組織は学習も成長もできない
経営理念やパーパスが確立され、それが浸透していればいるほど、組織はその理念・パーパスを基準に意思決定を繰り返すことができます。組織が学習する際に、理念やパーパスを軸に据えることが重要であり、その基盤が整っていれば、反省や見直しを繰り返して、理想の状態を追求することができます。言い換えると、経営理念やパーパスは、企業が組織的に学習をする際の指針となるものです。 しかし、経営理念やパーパスが確立されていなかったり、浸透していなかったり、またはまったく共感を獲得できていないような場合には、過去の成功体験や失敗体験を基盤に学習するサイクルが行われます。これらの学習が、企業の向かうべき方向性と一致していない場合、その学習は無駄になるでしょう。 多様性が重要とされる中で、現場に意思決定を落とし込むためには、原則論が大切です。ただし、古い原則論に囚われることなく、詳細な既存の枠組みを持ちながら現場が学習することも重要です。理念やパーパスを軸に学習を行うことで、組織全体の目標達成に向けた一体感や協調性が生まれます。
パーパス経営により得られるメリット
ここまでは、パーパス経営の背景や必要性について詳しく見てきました。以下では、パーパス経営を行うことが企業にとってどのようなプラス要素になるのかを整理していきます。
企業が目指す方向性を示せる
企業はパーパス経営を行うことで、社員全体に目指すべき方向性を示すことができ、方向性は社員の行動指針となります。パーパスを社内全体にうまく浸透させることができていれば、スピード感を持った意思決定が実行できるでしょう。従業員がパーパスをもとに同じ方向を見ているので、選ぶべき道は明らかであり、対立する必要がなくなるからです。また、パーパス経営をしている姿勢そのものが、企業のブランディングに直結することもあります。とくに看過できない課題が乱立する昨今、社会課題の改善のために積極的に関わっていくことで、企業の印象がアップします。
ステークホルダーから信頼される
パーパス経営とは、単なる利潤追求という状態から一歩離れて、社会全体に対して企業として貢献していく経営スタイルであり、環境・経済など、喫緊の課題に向き合っていく姿勢を持っていることの証になります。社会課題に対して積極的に貢献していこうという意思を持っていることで、顧客や投資家などのステークホルダーから、信頼を得ることができるでしょう。
信頼を得ることは、企業にとって直接的なメリットにつながります。たとえばブランディングに成功したり、売り上げが向上したりという効果が期待できます。また、投資家からの支援が厚くなるなどのメリットが想定されます。
パーパスがエンゲージメントを産み出す
経営理念やパーパスによって良い文化や風土が醸成された結果、従業員のエンゲージメントが高まるということがあります。経営理念やパーパスは、社員一人ひとりの能力や集団組織におけるシナジーと基礎として、最重要な位置づけをされることがあるため、組織風土や文化に強く影響します。従業員が組織のパーパスに共感し、自己正当化できる場合、組織に対しての熱意や情熱が生まれ、エンゲージメントが高まるでしょう。
また、経営理念は、個人であれば組織に所属し、ビジョンに向けて、事業や業務をすることを自己正当化するための機能があります。それとともに、経営者やマネジメントが組織内外の問題を解釈するための前提としての正当性の担保になります。理念が明確であることは、組織内の方向性を明確にし、従業員に対して組織の目標や方向性を共有することができるため、エンゲージメントの向上につながります。とくに、組織のパーパスやミッションが社会的意義を持ち、社会貢献や社会的使命を果たすことにつながる場合、従業員のモチベーションやエンゲージメントはより高まるでしょう。
素早い意思決定につながる
パーパスが明確であるということはつまり、企業の判断軸が明確であり、行動指針が確立されているということです。同じパーパスを共有した従業員同士は、自然に同じ方向を目指して仕事を進められます。つまり、経営者と従業員の間でどこに進めばいいのかという「道標」が掲げられている状態になるのです。パーパスが社内に浸透すれば、従業員は円滑に、かつ正しく意思決定を下すことができます。
昨今は、変化の激しい時代であり、さまざまな判断を早急に下さなければ、状況が変わってしまったり、機を逃してしまったりする環境です。素早い決断を繰り返す俊敏性(アジリティ)の高さが重視されています。ここでいう「アジリティ」という言葉は、「速度(速さ)」を単に表す言葉ではありません。アジリティは、素早く状況判断をし、適切な行動を取る能力を示す言葉です。つまり、速度だけでなく、その状況に適した正しい行動を素早く行うことができる能力を表しています。パーパスが共有されている組織は、素早く状況判断をし、適切な行動を取ることができるでしょう。
経営理念やパーパスは個人のアイデンティティにつながる
経営理念やパーパスを明確に持つことは、個々のアイデンティティを確立することにつながります。たとえば「あなたは何者ですか?」と問いかけられたとき、多くの場合、日本人は職業やそれに準ずるものを答えるでしょう。一般的に、アイデンティティは仕事に大きく関係するのです。誰しもが「社会の役に立っていたい」という欲求を持っているからこそ、仕事は仕事、私は私という線引きが難しいのです。
仕事における成功体験や失敗体験は、個人的な価値観を左右します。アイデンティティが企業と完全に一致することはないものの、部分的には必ず重なり合うと言っても過言ではないでしょう。つまり経営理念やパーパスは、社員のアイデンティティと関りある存在なのです。
パーパスは単に経営や合理性にとどまらず、組織が持つ人間味や生命的な部分と、生命組織や社会環境との共存をより明確にします。このため、パーパスは、労働者と経営者という主客が別々に存在する契約概念ではなく、その二つにおいての共通性を生み出すものとなるのです。
まとめ
ビジネスにおけるパーパスとは、企業の持つ目的や、企業運営の意図などを指すのが一般的です。一言でいえば「社会におけるその企業の存在意義」です。パーパスが浸透し、従業員が共通認識を持っている場合、意思決定が速くなり、企業活動がスピーディーに行われるようになるでしょう。結果、ステークホルダーからの信頼も得られます。さらにパーパスは社会的な貢献に関わるものなので、個々のアイデンティティにも結びつきやすいのです。自社に適したパーパスを掲げることで、従業員エンゲージメントの向上や社員が業務に自分ゴトとして取り組むようになるなどの効果が期待できます。
関連事例
パーパス経営とは?経営理念との違いや策定のポイントについてよくある質問
- パーパスと企業理念と経営理念の違いは何ですか?
パーパス、企業理念、経営理念は、企業の目指す方向性や価値観を表す言葉ですが、それぞれ微妙なニュアンスの違いがあります。
パーパスは、企業が社会に対して存在する「理由」や「目的」を指します。企業が社会にどのような貢献をし、どのような価値を生み出したいのか、という根源的な問いに対する答えです。より広範な社会的な視点から、企業の存在を定義する概念と言えるでしょう。
企業理念は、企業が大切にしている価値観や行動規範をまとめたものです。企業がどのような考え方でビジネスを行い、どのような社会との関わり方を築きたいのか、という企業の哲学を表現します。パーパスと比較すると、より企業内部に焦点を当てた概念です。
経営理念は、企業理念をより具体的にし、経営活動の指針となるものです。企業が目指すビジョンや目標を明確にし、従業員が共通の目標に向かって行動するための指針となります。企業理念を達成するための具体的な行動計画や戦略を盛り込むこともあります。
- パーパスの基本理念は?
パーパスの基本的な考え方
社会への貢献: 企業は、単に利益を追求するだけでなく、社会の課題解決や持続可能な社会の実現に貢献すべきという考え方です。
長期的な視点: パーパスは、短期的な利益ではなく、長期的な視点で企業の成長と社会の発展を両立させることを目指します。
社員のモチベーション向上: パーパスは、社員に仕事の意味や価値を感じさせ、モチベーションを高める役割を果たします。
顧客との共感: パーパスは、企業と顧客との間に共感を生み出し、強固な関係を築くことにつながります。
- パーパス経営の代表例は?
パーパス経営の代表例
パーパス経営を実践している企業は、世界中に数多く存在します。それぞれの企業が、自社の強みや社会への貢献を踏まえて、独自のパーパスを掲げています。ここでは、代表的な企業の例をいくつかご紹介します。パタゴニア: 「私たちは、故郷である地球を救うためにビジネスを営む」をパーパスとして掲げ、環境保護活動に積極的に取り組んでいます。製品の品質にこだわり、リサイクル素材の使用や修理サービスの提供など、環境負荷を低減するための取り組みを数多く実施しています。
ネスレ: 「ネスレは、食の持つ力で、現在そしてこれからの世代のすべての人々の生活の質を高めていきます」をパーパスとして掲げ、栄養に関する研究開発や、食料の安定供給に貢献しています。
マイクロソフト: 「地球上のすべての個人とすべての組織が、より多くのことを達成できるようにする」をパーパスとして掲げ、テクノロジーを通じて社会の課題解決に取り組んでいます。
ユニリーバ: 「持続可能な生活を実現し、より良い未来を創ります」をパーパスとして掲げ、健康、衛生、美に関する製品を提供しながら、環境への影響を最小限に抑える取り組みを進めています。
これらの企業は、パーパスを経営の中心に置き、社員一人ひとりがそのパーパスに共感し、行動することで、企業の成長と社会への貢献を両立させています。
- パーパス経営とは何ですか?
パーパス経営とは、企業が単なる産業界に閉じた利益追求だけでなく、社会全体における自社の存在意義(パーパス)を明確にし、そのパーパスに基づいて経営を行うことを指します。パーパス経営を導入することで、企業は従業員のエンゲージメント向上、イノベーションの促進、社会からの信頼獲得など、様々なメリットを得ることができます。
- パーパス経営と企業理念の違いは何ですか?
パーパス経営と企業理念は、どちらも企業の経営方針を語る上で重要な概念ですが、その意味合いには明確な違いがあります。
パーパス経営とは、産業界に閉じた利益追求だけでなく、社会全体における自社の存在意義(パーパス)、そのパーパスに基づいて経営を行うことを指します。
一方、企業理念は、企業が大切にしている価値観や行動指針をまとめたものです。
- パーパス経営のデメリットは?
パーパス経営は、企業が社会への事業を通じて貢献を重視し、長期的な視点で成長を目指す素晴らしい経営理念ですが、一方でいくつかのデメリットも存在します。
パーパス経営のデメリット
パーパスウォッシュのリスク:パーパスが形骸化し、実際の行動と一致しない状態を指します。
パーパスを掲げるだけで、具体的な行動が伴わない場合、従業員や顧客からの不信感を招き、ブランドイメージを損なう可能性があります。
短期的な利益とのバランス:社会貢献を重視するあまり、短期的な利益を軽視してしまう可能性があります。
特に、スタートアップ企業や中小企業にとっては、生存のために利益確保も重要な課題です。
パーパスの測定困難性:パーパスの達成度を客観的に測ることが難しい場合が多く、効果的な評価が困難です。
従業員の満足度や社会貢献度など、定量化できない要素も含まれるため、数値目標を設定しづらい側面があります。
従業員間の意見の相違:パーパスへの共感が得られない従業員もいる可能性があります。
従業員一人ひとりの価値観が異なるため、パーパスへの理解度や共感度に差が生じる場合があります。
外部環境の変化への対応:社会情勢や顧客ニーズの変化に伴い、パーパスを再定義する必要が生じる場合があります。
変化の激しい時代において、パーパスを常に見直し、時代に合った形に進化させていく必要があります。

株式会社ソフィア
先生
ソフィアさん
人と組織にかかわる「問題」「要因」「課題」「解決策」「バズワード」「経営テーマ」など多岐にわたる「事象」をインターナルコミュニケーションの視点から解釈し伝えてます。
株式会社ソフィア
先生

ソフィアさん
人と組織にかかわる「問題」「要因」「課題」「解決策」「バズワード」「経営テーマ」など多岐にわたる「事象」をインターナルコミュニケーションの視点から解釈し伝えてます。