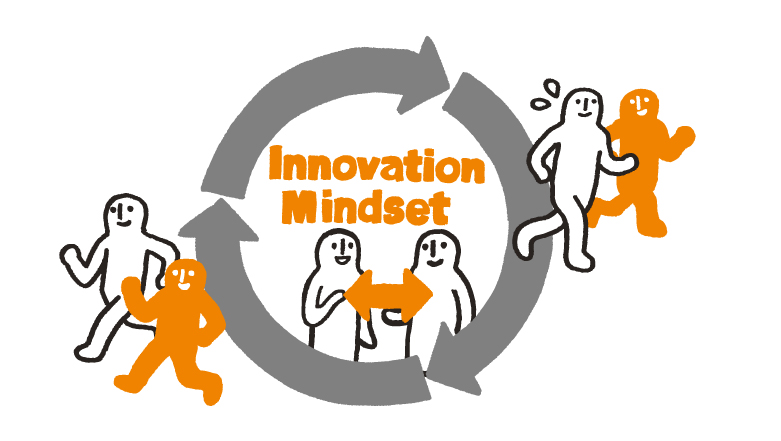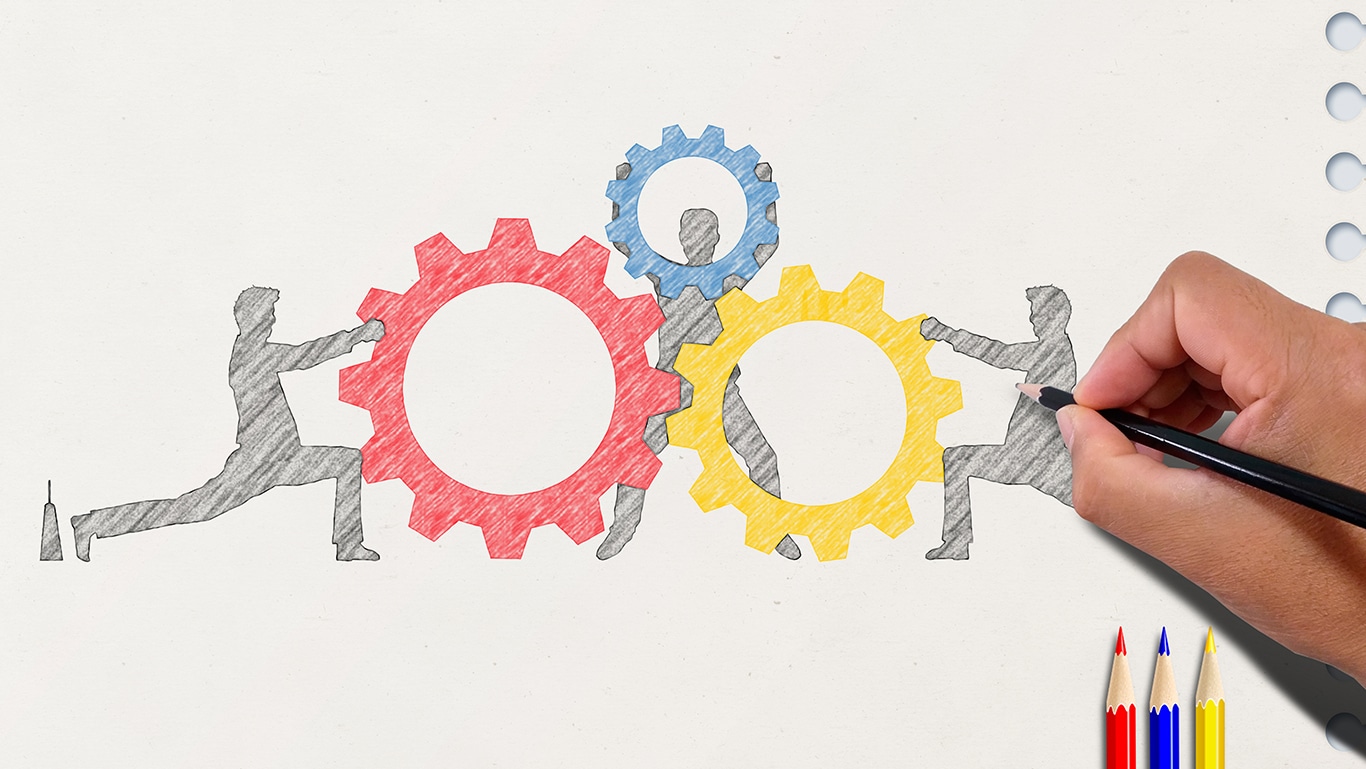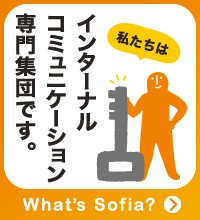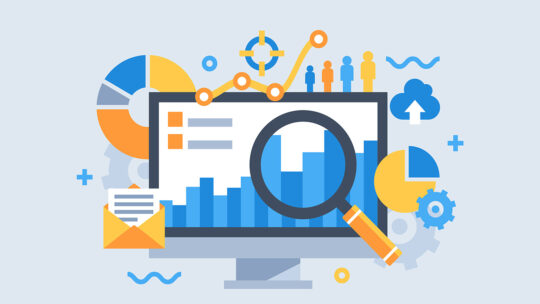2025.02.07
ミドルマネジメントとは?抱えやすい悩みや、具体的な業務内容や求められるスキルを解説

目次
ミドルマネジメントとは、組織内で経営陣と現場の社員をつなぐ中間的なポジションを指します。具体的には、部長や課長などが該当し、経営陣の戦略を現場に落とし込む役割や、現場からの意見や課題を経営陣に伝える橋渡し役を担います。
この役割は組織の円滑な運営に欠かせないものですが、特有の悩みを抱えることも少なくありません。また、上司からの高い期待と部下への責任が交錯する中、適切なマネジメントを行うためには、幅広いスキルが求められます。
現在のミドルマネジメントは、かつて社会学者エズラ・ヴォーゲルが著書『ジャパン・アズ・ナンバーワン』で評価したような、日本の競争力を支えていた優れたボトムアップ型の役割から大きく変化しました。
当時のように産業や業務内容が成長を牽引する時代は終わり、現在ではミドルマネジメントの存在が競争力の源ではなく、時に「罰ゲーム」と揶揄されるような状況に陥っています。
そこで本記事では、ミドルマネジメントの現在地に迫っていければと思い、ミドルマネジメントの具体的な業務内容や、よくある悩み、さらに必要なスキルについて詳しく解説します。
ミドルマネジメントとは?
ミドルマネジメントは、組織内で経営陣(トップマネジメント)と現場(ロワーマネジメント)の橋渡し役として機能する重要なポジションです。
この立場は経営戦略を現場に落とし込む一方で、現場の声を経営陣に伝える役割を担います。
つまり「どっちつかず」でありながら、両方の良い部分を持ち合わせているということです。その曖昧さがミドルマネジメントの問題であると同時に、大きな強みともなっています。
トップマネジメントやロワーマネジメントとの違いを理解することは、ミドルマネジメントの本質を掴む上で欠かせません。ここでは、それぞれの役割や特徴について詳しく見ていきます。
ミドルマネジメントとは?
ミドルマネジメントとは、一般的に部長や課長、係長などの中間管理職を指すポジションのことです。この役割を担う人々は、経営陣のビジョンや戦略を正確に理解し、それを現場で実行に移すための組織運営を行います。
ミドルマネジメントはトップマネジメントと現場をつなぐ重要な橋渡し役であり、組織全体の目標達成に向けた調整を行う責務があります。
以前は、上下の関係を調整することが主な役割で、部門間の調整も少しある程度でした。しかし現在では、縦の階層構造や横断的な組織、社内プロジェクト、マトリクス型の組織など、調整すべき対象が増え、それに伴い調整業務が非常に複雑化しています。
また、どの役職がミドルマネジメントに該当するかは企業ごとに異なり、組織の規模や構造によってその範囲が変わることも特徴です。ミドルマネジメントは、経営陣の方針を現場に浸透させるだけでなく、現場の課題や成果を経営陣に伝える役割も担い、組織全体の円滑な運営を支える中核的存在といえます。
しかし、いくら調整が円滑に行われているように見えても、ミドルマネジメントが個別の課題ごとに対応している場合、全体の状況を正確に把握しながら調整することは難しいのが現実です。
つまり、それぞれが個別の状況を想像しつつ、全体最適を意識して他のミドルマネジメントと調整を取ることは、基本的には不可能と言えるのです。
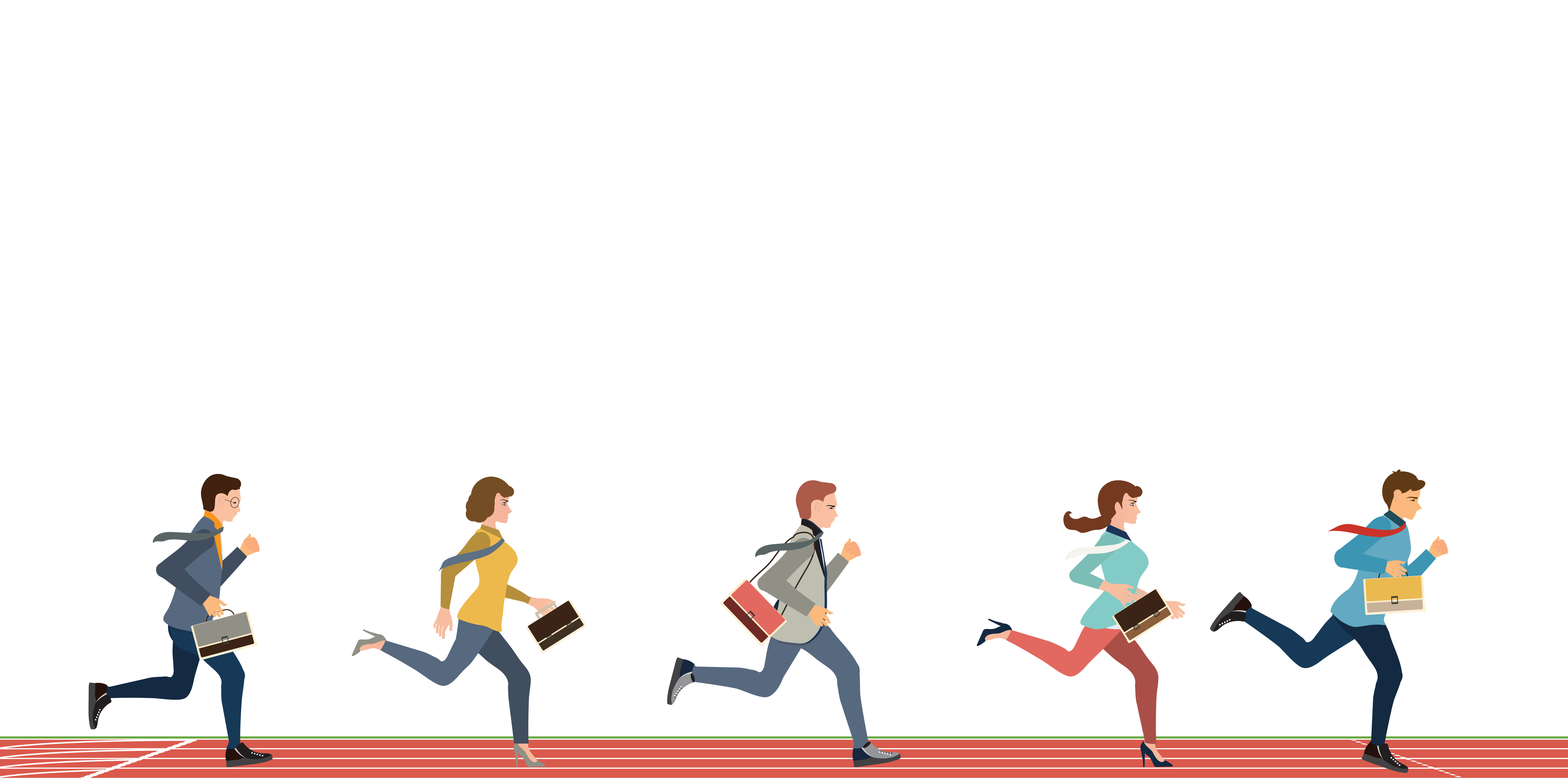
組織や仕事の変革に「伴走者」が求められる理由 ~シリーズ「変革する人には伴走者が必要だ」①
いまビジネスの世界や教育や行政などににおいて注目されている「伴走」という概念。創業以来、顧客企業の課題解決や…
トップマネジメントとは?
トップマネジメントとは、組織の「最高経営者層」を指し、一般的には役員と呼ばれる人々が該当します。この層の主な役割は、組織全体を経営・運営していく上での基本的な方針を定めることであり、組織における最終的な意思決定を行う立場にあります。また、その意思決定に伴う責任を負うことも、トップマネジメントの重要な職務です。
トップマネジメントは、組織の方向性を示し、全体の戦略を策定することで、他の階層が実行に集中できる環境を整える役割を担います。経営ビジョンの提示や資源の配分など、組織全体に影響を与える重要な決定を下すため、高い視座と決断力が求められます。トップマネジメントは組織の成功を左右する中心的な存在といえるでしょう。
現在のトップマネジメントの多くは、かつてミドルマネジメントを経験してきた人たちです。そのため、トップが意思決定を行うことが業務だと理解していても、現場からのボトムアップがなければ機能しません。
さらに、トップが現場の詳細を完全に把握するのは不可能であり、現在のトップがミドルだった時代の現場と、現在の現場は大きく変わっているため、状況を正確に想像するのも難しいのが現状です。このような背景から、ミドルとトップの間で認識のズレが生じつつあります。
また、現在のトップが新卒だった頃のOJTでは、雑務や事務作業が中心でしたが、現在の新卒にはそのような仕事はほとんど存在しません。これらの業務は機械化され、工程は自動化されています。そして、数年後にはAIの進化により、今の新卒が担当している業務も消滅する可能性が高いのです。
ロワーマネジメントとは?
ロワーマネジメントとは、現場の従業員を直接的に管理・指導する役割を担う層を指します。監督者層とも呼ばれ、役職にはついていない場合が多いものの現場業務の円滑な遂行に欠かせない重要な存在です。
ロワーマネジメントは、ミドルマネジメントの指示を受け、それを現場で実行に移すための指揮や監督を行います。また、上層部が描くビジョンを現場の作業に反映させる役割も担っており、現場の課題や状況を把握し、改善策を講じることが求められます。
また、いわゆる「ロワー層」に分類される社員であっても、何のスキルも持たない人材ばかりというわけではありません。新卒一括採用が一般的なのは日本特有の制度ですが、近年では、大学や専門的な学習を経て、一定の技術や専門知識を持つ人材がロワー層として入社するケースが増えています。そのため、組織階層としては下位に位置していても、むしろ高度なスキルを持つ人が多くなってきています。
ミドルマネジメントとトップマネジメント・ロワーマネジメントとの違い
実際のミドルマネジメントの役割は非常に複雑です。「ミドル層よりも高い専門性を持ち、ミドル層が未経験の仕事をこなすロワー層」に、大きく変動する外部環境の中での即時対応を求められ、「現場の状況を理解しきれていない朝令暮改のような指示を出すトップ層」に対して、説明や説得を行う役割が求められるのがミドルマネジメントです。
このように、ミドルマネジメントの重要性はこれまで以上に高まっており、その役割もますます複雑化していることは言うまでもありません。
それぞれの違いを理解することは組織全体の役割分担を明確にするうえで重要です。次に、それぞれの違いを詳しく見ていきます。
ミドルマネジメントとトップマネジメントの違い
ミドルマネジメントとトップマネジメントは、それぞれ異なる役割を担いながらも、組織運営において重要な関係性を持っています。
トップマネジメントは会社全体の経営方針や運営戦略を決定する立場にあり、組織の方向性を示す責任を負っています。
一方ミドルマネジメントは、トップマネジメントが決めた方針を現場に浸透させ、実行に移す役割を果たします。
またミドルマネジメントは現場により近い位置にあり、実際の運営の中心として機能します。現場の状況を把握しながら、トップマネジメントとロワーマネジメントをつなぐ橋渡し役を務める点が、両者の大きな違いといえます。
重要なのは、現在の環境では「ESG」「グローバル」「DX」といったバズワードが多く使われており、それらの曖昧な指示を自分の部門の業務に具体的に落とし込むのが非常に難しいという点です。
ミドルマネジメントは、次々と登場する新しいバズワードに対して「抽象」→「具体」の翻訳を行い、対応していかなければなりません。
ミドルマネジメントとロワーマネジメントの違い
ミドルマネジメントとロワーマネジメントは、それぞれ異なる責任範囲と役割を持っています。ミドルマネジメントは、会社経営に関わる責任を負い、経営方針を実行可能な形で現場に伝え、組織全体の運営を支える役割を担います。
一方で、ロワーマネジメントは、日々の業務遂行に直接責任を持つ立場であり、現場の従業員を管理し、具体的な指示を出す役割が中心です。
ロワーマネジメントは、下級管理職や監督者層、チームリーダーなどと呼ばれることもあり、現場での直接的な対応を通じて業務を推進します。このように、ミドルマネジメントが経営全体に寄与する立場であるのに対し、ロワーマネジメントは現場に密着している点が、両者の大きな違いといえます。
実際にミドル層からの支持を業務に具体的に落とし込もうとしても、個々の業務が専門化しているため簡単には実行できません。さらに、産業構造がサービス業中心になり、肉体労働ではなくホワイトカラー中心の「精神労働」が主流となっています。肉体労働に肉体的な疲労があるように、精神労働には精神的な疲労が伴うため、そのケアは欠かせません。
これを一言で言えば「ウェルビーイング」の推進ですが、具体的な行動やロワー層へのアプローチとなると、一気に複雑で難しい問題になります。このような状況に対応するのは非常に大変です。
ミドルマネジメントの具体的な業務内容
ミドルマネジメントは、チーム内での意思決定や調整を通じて、円滑な業務運営を実現する責任もあります。さらに、部下の育成と評価を行うことで、チームのパフォーマンスを向上させることも欠かせません。次に、具体的な業務内容について詳しく解説します。
経営層と現場を繋ぐ
経営層と現場を繋ぐことは、ミドルマネジメントの最も重要な役割の一つです。中間管理職は、上層部の指示や方針を現場に分かりやすく伝える一方で、現場の状況や部下の意見を上層部に報告することで、社内コミュニケーションの中核を担います。この双方向のやり取りにより、組織内の情報の流れをスムーズにし、上層部と現場社員との間に生じる認識のズレを緩和する役割を果たします。
また、経営層が掲げる戦略やビジョンを、具体的なタスクに分解して現場で実行可能な形に落とし込むことも求められます。こうした役割を通じて、ミドルマネジメントは上層部と現場との摩擦を和らげ、組織全体の円滑な運営を支えなければなりません。
現在の状況では、社内コミュニケーションをミドルマネジメントだけに任せるのは非常に困難です。この問題を解決するには、社内で共通言語を作り、情報を共有する仕組みを整えるといった全社的なサポートが不可欠です。これがなければ、現場と経営はほとんど繋がらないままになってしまいます。
最近では、トップマネジメントが現場に足を運ぶ取り組みが増えていますが、それだけでは不十分です。側面的なサポートを増やさない限り、現場と経営がしっかりと繋がることは難しいのが現状です。
チームにおける意思決定と調整をおこなう
チームにおける意思決定と調整をおこなうことは、ミドルマネジメントの役割の中心的な部分です。経営方針を考慮しながら、部署全体の動きやプロジェクトの方向性を決定する責任を担っています。特に、複数の部署をまたぐプロジェクトでは、部門間の連携やコミュニケーションを円滑にするための調整が求められます。
ミドルマネジメントの意思決定は、現場の業務に直接的な影響を与えるだけでなく、組織全体の業績や将来性にも深く関わります。また、現場の業務が高度な専門性と複雑さを増している現代では、経営層だけで成果を出すことが難しくなっており、現場と経営の間を調整するミドルマネジメントの重要性がますます高まっています。この役割を的確に果たすことで、チーム全体の効率と成果を最大化することが可能となります。
また、対面で集まるグループが専門性を持てば持つほど、多様性が高まります。それ自体は良いこととされていますが、その一方で、意見の一致や議論を進めることが一層難しくなります。つまり、こうした状況では、コミュニケーション能力がより重要になってくるのです。
部下の育成と評価
部下の育成と評価は、ミドルマネジメントの重要な役割の一つです。部下を適切に育成することで、組織全体の生産性を向上させるだけでなく、チーム全体の能力を底上げすることができます。
また、部下に対する適切な評価は、モチベーションを高め、さらなる成長を促すために欠かせません。しかし、1on1などの例を見てもわかるように、OJTを行えば自然と能力が伸びる時代ではなくなりました。今は、それに加えて社員のモチベーションを高める取り組みが必要な時代です。
評価の際には、定量的かつ事実ベースで行うことがポイントです。これにより、公平性が保たれ、評価に対する部下の納得感が向上します。さらに、目標設定から評価までのプロセスを繰り返すことで、部下の成長を継続的な支援にもつながります。
ミドルマネジメントの問題点
ミドルマネジメントの問題点は、組織構造や働き方の変化によって複雑化しています。特に、課長職のようなプレイングマネージャーやフロントラインマネージャーは、労働者と同じ目線で働きながら、育成や評価、実務、コミュニケーションを担うという多岐にわたる役割を求められています。その一方で、肩書きや勤務形態では経営者に近い責任を負うものの、実際の権限は十分に与えられていないことが多いのが現状です。
ミドルマネジメントは、日本企業における組織内の問題解決の中心的な存在となることが多く、「まずは管理職から」という考え方が一般的です。しかし、ミドルマネジメントの能力開発や生産性向上を図るだけでは限界があります。そのため、ミドルマネジメントを支援するための側面的なサポートが不可欠です。
また、プロジェクト型組織への変化や産業構造の進化により、従来の階層型マネジメントが必ずしも必要とされなくなりつつあります。ヘンリー・ミンツバーグが「マネージャーの実像」で指摘したように、管理職の業務の多くは問題解決に集中しており、構造的に業務負荷が過剰になっています。この「負荷のインフレ構造」によって管理職の役割は罰ゲーム化し、リスクが高いポジションと見なされることが増えています。
さらに、短期的な課題の是正や中長期的な施策の推進に加え、自部門の課題解決がすべて管理職に集中する現状は、業務効率の低下を招き、持続可能性を損ないます。こうした問題を解決するためには、管理職の構造そのものを見直し、負荷を分散する仕組みを整える必要があります。それとともに、役割に見合った適切な賃金の見直しも求められています。
参考:リクルートワークス研究所「管理職が「罰ゲーム化」した10の要因」
ミドルマネジメントが抱えやすい悩み
ミドルマネジメントが抱える悩みは多岐にわたります。戦略と現状の乖離や、限られたリソースでビジョンを実現する難しさ、さらには十分な権限や支援を得るための複雑な承認プロセスなど、課題は尽きません。
さらに、コンプライアンスやガバナンスに関する要件の増加も、業務を一層複雑化させています。これらの問題が蓄積することで、責任や業務量からくるストレスが増し、達成感を得る機会が少ない状況が生じやすくなっています。
責任や業務量でストレスが多い
責任や業務量でストレスが多いことは、ミドルマネジメントが抱える代表的な課題の一つです。多くの仕事や役割を任される中で、タスク上の負担だけでなく、組織やチームの成果に対する責任やプレッシャーも重くのしかかります。その結果、日常的に高いストレスを抱えるミドルマネジメントも少なくありません。
特に、管理職という立場は、権限や職責を遂行する機会以上に、役割を果たすためのリスクが高くなりがちです。この状況が続くと、メンタルヘルスの維持が難しくなる場合もあります。そのため、バランスの良い食事や適度な睡眠、運動を心がけるなど、ストレスを軽減するためのセルフケアが欠かせません。また、組織全体でのサポート体制を強化し、負担を分散する仕組みづくりも必要です。
達成感に繋がりづらい
達成感に繋がりづらいことは、ミドルマネジメントが直面する大きな課題の一つです。日々の業務に追われる中で、自身の成果を振り返る余裕を持てないことが、達成感を感じられない主な原因といえます。会社への貢献は大きいものの、振り返りの機会がなければ、その努力が認識されにくく、自己評価が低くなる傾向があります。
また、ミドルマネジメントの業務の多くがリスクヘッジや処理的な仕事に集中しているため、創造的で挑戦的な業務に取り組む時間が限られていることも、達成感の欠如につながっています。
ミドルマネジメントからエンパワーメントへ
ミドルマネジメントからエンパワーメントへの移行は、組織の負担を軽減し、効率を向上させるための重要なステップです。現在、権限と責任が集中していることが、ミドルマネジメントの負担を増幅させる主な原因となっています。しかし、専門性を持つメンバーに権限を共有し主体的に行動させることで、この課題を解決する道が開けます。
権限を共有することで失敗のリスクは増えるかもしれませんが、その分、メンバーの育成が高速化し、動機付けが強まります。また、判断のスピードが上がり、現場での柔軟な対応が可能になります。ただし、このプロセスでは、ミドルマネジメントの影響力が一時的に低下する場合もありますが、透明性の高い情報共有とチーム内のコミュニケーションを強化することで、全員が責任を分担しながら成果を追求できる環境が整います。
最終的な責任はミドルマネジメントが負うものの、チーム全体で力を合わせて課題を解決する姿勢が、組織全体の成長と効率向上を促します。勇気を持って権限を共有し、チーム全体の可能性を引き出すことが求められています。
しかし、実際にはミドルマネジメントによる育成はほとんど行われていません。公式・非公式を問わず、ミドルマネジメントはエンパワーメントの形で権限を付与し、共有しています。言い換えれば、自分の権限をメンバーにどんどん与える一方で、責任だけは自分に残すという状況が生まれているのです。
目標は共有されていますが、役割やチーム内の作業分担については曖昧であり、逆にその曖昧さが効率的であるとも言えます。ただし、これを成り立たせるには、高度なコミュニケーション能力や情報共有が欠かせません。
ミドルマネジメントに求められるスキル
ミドルマネジメントには、多岐にわたる役割を担うためのスキルが求められます。その中でも、チームやプロジェクトを円滑に運営するためのマネジメント能力、複雑な状況や問題に直面した際に迅速かつ適切に対応するための課題解決力、そして、現場や経営層とのコミュニケーションや意思決定を支える論理的思考力は、特に重要な要素です。
これらのスキルを高めることが、ミドルマネジメントとしての成功と、組織全体のパフォーマンス向上につながります。それぞれのスキルについて詳しく見ていきましょう。
マネジメント能力
マネジメント能力は、ミドルマネジメントの中心的な役割であり、組織運営の要となるスキルです。
人材のマネジメント
人材のマネジメントでは、メンバー一人ひとりの知識やスキル、性格を正確に把握し、それぞれが最も力を発揮できる役割やポジションを与えることが求められます。この適材適所の配置により、組織内のリソースを最適化し、さらに高めることが可能です。
また、人材育成はミドルマネジメントに課された重要な課題であり、長期的な組織の成長に不可欠な要素です。
業務のマネジメント
業務のマネジメントでは、現場業務の方法や手順、戦略を決定する責任を担います。目的や目標を組織全体に正しく浸透させ、目標達成のための適切なプロセスやスケジュールを構築する能力が求められます。この采配次第で、現場の業務がスムーズに進むか、高い成果を上げられるかが決まります。
リスクマネジメント
ミドルマネジメントは、組織内のリスクマネジメントにおいて重要な役割を担います。日常的な業務や現場の動向を注意深く観察し、潜在的なトラブルを事前に把握して予防策を講じることが求められます。
また、社員のモチベーション低下や離職リスクを未然に防ぐため、コミュニケーションを通じて問題を早期に発見・解決することが重要です。
不測の事態が発生した場合には、迅速かつ柔軟に対応し、経営層への的確な報告や提案を行う必要があります。情報共有やチーム内の連携を強化しながら、現場と経営の架け橋として組織全体の安定と成長に貢献することが期待されています。
情報・コミュニケーションマネジメント
現代のビジネス環境では、迅速な意思決定と対応力が求められるため、権限移譲が重要です。権限を移譲することで、現場や担当者が自律的に判断できるようになりますが、そのためには正確でタイムリーな情報提供が不可欠です。
情報が不足すると、判断ミスや不公平感が生じる可能性があります。情報の透明性を高め、進捗状況や課題などをリアルタイムで共有することで、全員が同じ認識を持ち、適切な意思決定が可能になります。
情報の偏りは不信感を招き、士気や生産性を低下させる原因となります。信頼関係を維持するためにも、情報共有の仕組みを整えることが組織の成長に欠かせません。
課題解決力
課題解決力は、ミドルマネジメントにとって不可欠なスキルです。チーム内で発生する問題や部下からの相談、組織全体の課題など、さまざまな状況において迅速かつ適切に対処する能力が求められます。このスキルは、リスクマネジメントとも密接に関係しており、トラブルを未然に防ぐための予防策や、発生した課題への対応力に直結します。
課題解決力を発揮するには、まず現状を正確に把握し、課題の原因を深く探る分析力が必要です。その上で、課題を解決するためのステップを段階的に考える論理的思考力と、考えた解決策を実際に行動に移す実践力が求められます。このプロセスを繰り返すことで、組織全体の課題を着実に解決し、チームのパフォーマンスを向上させることが可能となります。
論理的思考力
論理的思考力は、ミドルマネジメントにとって極めて重要なスキルです。この役職では、経営層と現場の間に立ち、多様な課題に対して意思決定を行い、問題解決やチーム運営を進める必要があります。そのため、状況を正確に分析し、課題を明確化して適切な解決策を導き出す論理的なアプローチが欠かせません。
また、論理的思考力とともに求められるのが高いコミュニケーション能力です。ミドルマネジメントは、さまざまな立場やスキルを持つ人々とやり取りする機会が多く、それぞれの価値観や考えをくみ取り、的確に伝える力が必要です。相手の立場や背景に応じて言葉や対応の仕方を柔軟に変えることが、円滑なマネジメントを実現する鍵となります。
論理的思考力とコミュニケーション能力を併せ持つことで、課題の本質を正確に見極め、経営層や現場との信頼関係を構築しながら、効率的かつ効果的にチームを導くことが可能となります。
ミドルマネジメントとして活躍していくために
ミドルマネジメントとして活躍するためには、多岐にわたるスキルや視点が求められます。その中でも特に重要なのが、チーム内外での信頼関係を構築する力や、適材適所で仕事を振り分ける能力、そして物事を客観的に捉えて判断する姿勢です。
これらの要素を意識することで、組織全体の効率向上やチームの結束を強化し、成果を最大化することが可能となります。それぞれの具体的なポイントについて見ていきましょう。
周囲との信頼関係の構築を行う
周囲との信頼関係の構築を行うことは、ミドルマネジメントとして成功するための基本中の基本です。このポジションでは、上司や部下、他部門、チーム全体など、社内のさまざまな人と連携する機会が多く、信頼関係が構築されていないと、業務のたびに余計な連携コストが発生してしまいます。
信頼関係を築くためには、情報共有の場を設けたり、頻繁にコミュニケーションを取ることが大切です。これにより業務の円滑化が図られ、連携もスムーズになります。
また、全員がリーダーシップを発揮できるような職場環境を作ることで、チーム全体のマネジメント力を向上させることが可能です。信頼関係の構築は、組織のパフォーマンス向上にも直結する重要な要素です。
仕事の振り分けを行う
仕事の振り分けを行うことはミドルマネジメントの重要な役割の一つです。適切に仕事を任せる判断ができれば、部下の成長を促すだけでなく、自身の負担を軽減することも可能になります。逆に、仕事を抱え込み過ぎると、部下の成長機会を奪うだけでなく、自身の業務が滞り、ストレスも増大してしまいます。
部下に仕事を任せた後も、必要に応じてアドバイスをしたり、悩みを解決するためのサポートを行うことが大切です。このような適切なサポートを通じて、部下のスキル向上や自主性の強化を図り、チーム全体のパフォーマンスを高めることができます。仕事の振り分けは部下の成長と、業務の効率化を両立させるための鍵となるプロセスです。
客観性を持って仕事を行う
客観性を持って仕事をすることは、ミドルマネジメントが円滑に業務を進める上で重要な姿勢です。
多くの要望や意見を聞き、それらを調整する役割を担うため、物事を俯瞰的に捉え公平に対応するスキルが求められます。このためには、感情的になることを避け、主観ではなく客観的に物事を判断する力が欠かせません。
また、様々な人の立場に立って物事を考えることも重要です。相手の視点を理解することで、より的確な対応ができ、信頼関係の構築にもつながります。
客観性を持つことで、冷静かつ柔軟に状況に対応できるマネジメントを実現できるでしょう。
まとめ
ミドルマネジメントは、経営層と現場の間で重要な橋渡し役を果たし、組織全体の効率と成果を最大化するために欠かせないポジションです。具体的な業務内容としては、戦略の実行、チームのマネジメント、課題解決など、多岐にわたる役割が求められます。そのため、求められるスキルはマネジメント能力、課題解決力、論理的思考力など多岐に渡ります。
また、ミドルマネジメントは責任が重く、ストレスや達成感の低さ、業務の過重負担などの悩みも抱えやすいですが、信頼関係の構築や業務の適切な振り分けを通じて、その負担を軽減することができます。
組織全体を見渡し、部下と経営層の橋渡しをしながら、持ち場で活躍するためには、自己管理やスキルの向上が不可欠です。