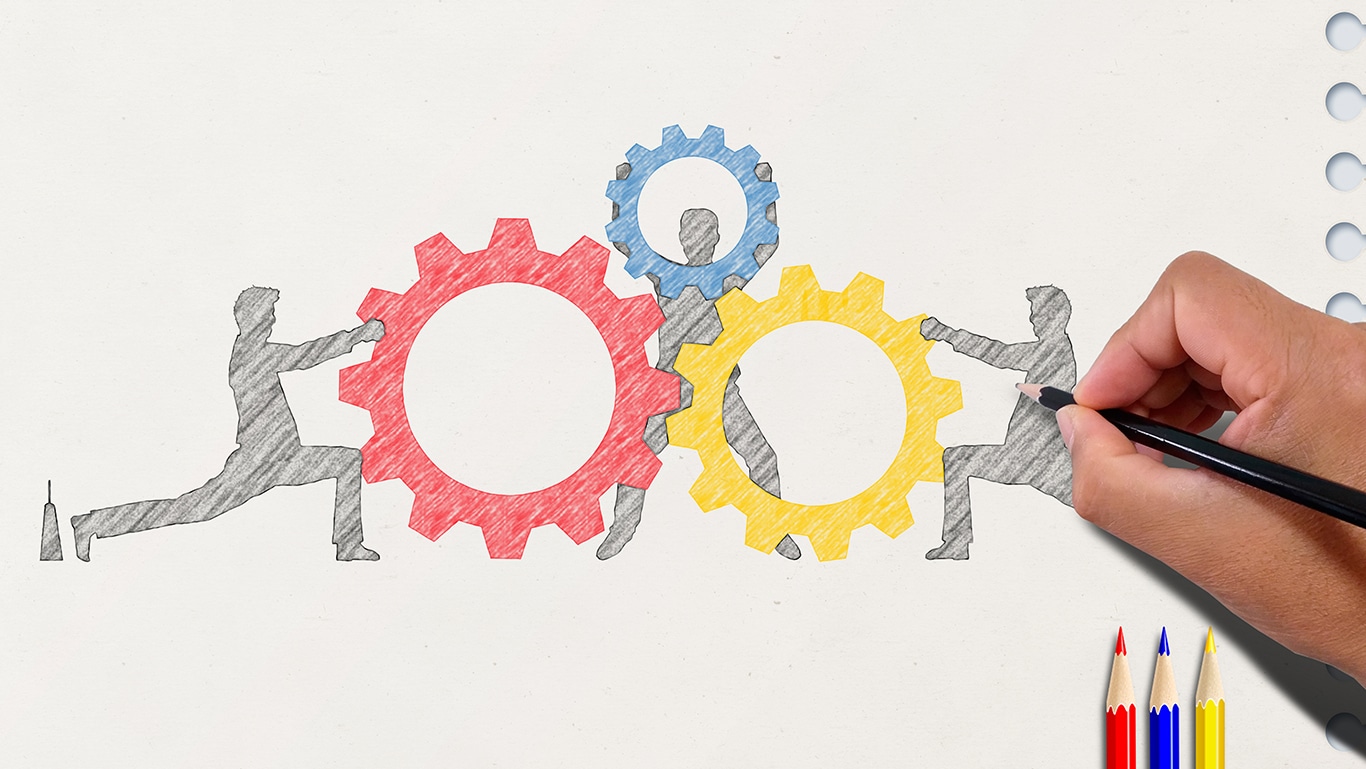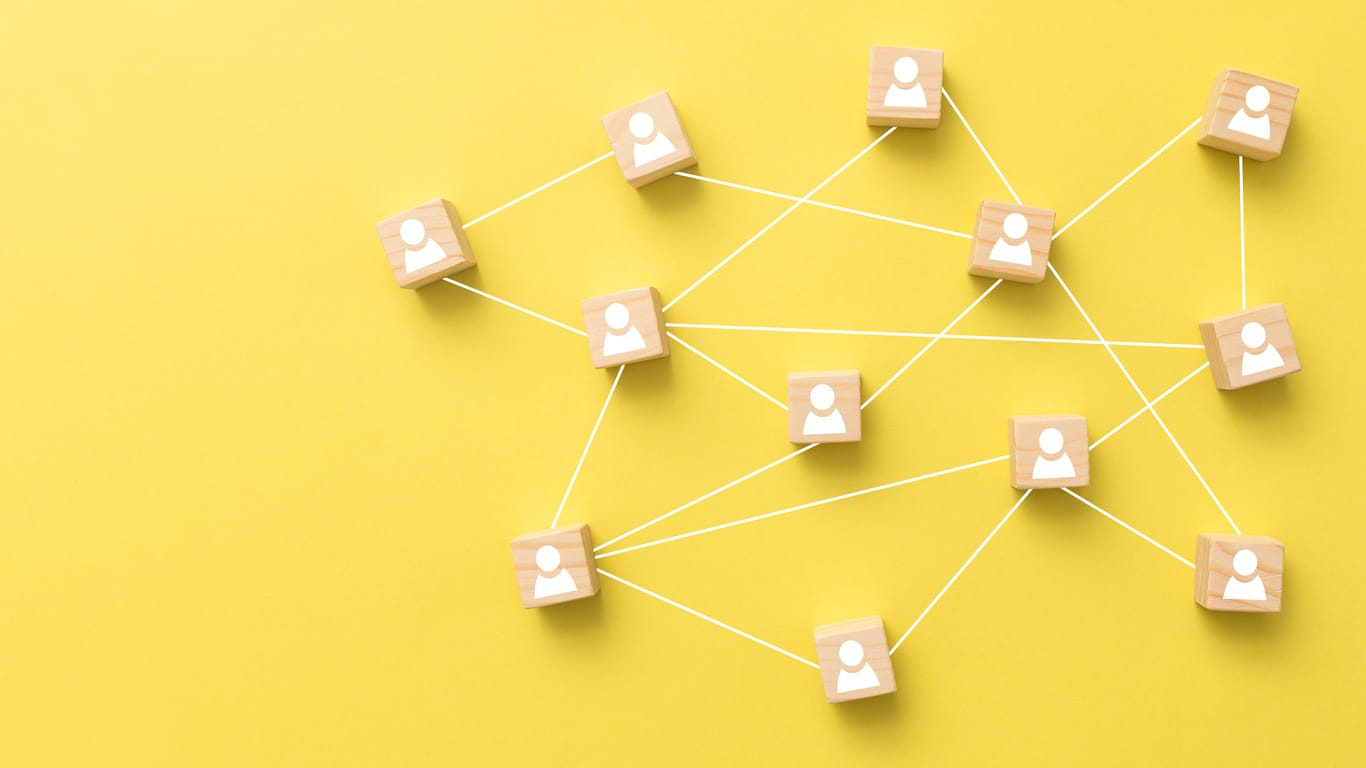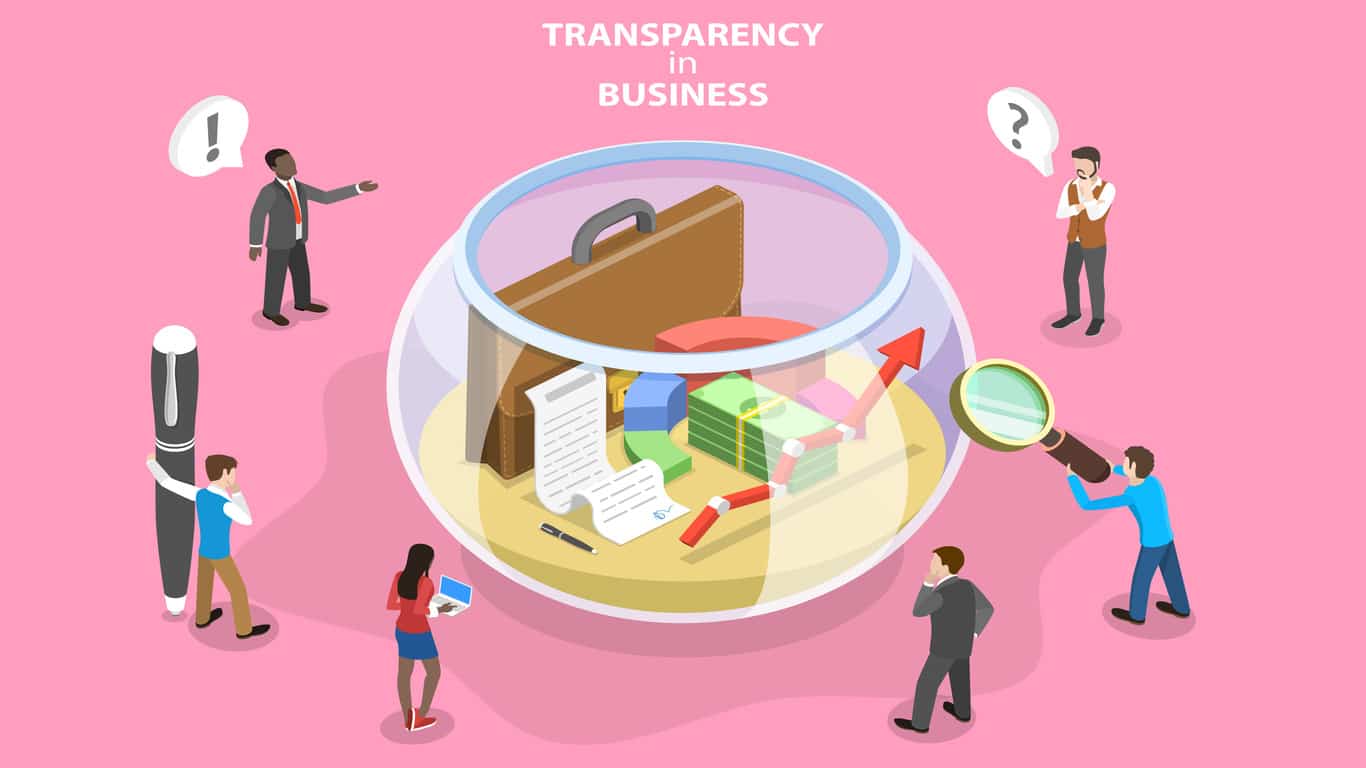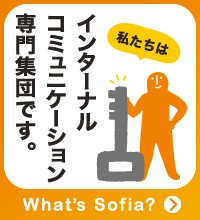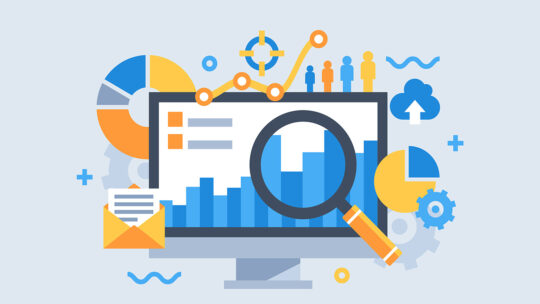2025.02.07
管理職は罰ゲームなの?管理職に問題が集中する理由と解決策を徹底解説!

目次
「管理職になるのは罰ゲームだ」と感じている人は少なくありません。責任が増えるだけでなく、上司の期待と部下の要望に挟まれ、多くの問題が管理職に集中するためです。結論から言えば、現代のビジネス環境において管理職はますます「罰ゲーム」に近い役割になりつつあります。
さらに、成果を求められるプレッシャーや、膨大な業務量に圧倒されるケースも珍しくありません。本記事では、管理職に課題が集中する理由を掘り下げ、実践的な解決策を徹底解説します。
管理職が罰ゲームと言われてしまうのはなぜ?
管理職が「罰ゲーム」と言われる背景には、現代の働き方や組織構造の変化が深く関係しています。人材不足による管理職候補者の減少や、成果主義の広がりによるプレッシャーの増加、さらには現場からの変わらない期待が管理職に重くのしかかっています。また、働き方の多様化による非正規雇用の増加や、働き方改革の影響で求められる役割が増え、社会的責任も大きくなっています。
現在の中間管理職の中心となっているのは、30代から50代の世代です。その中でも特に、43歳前後から55歳前後の世代は、いわゆる「就職氷河期」に該当します。この時期は企業の採用人数が少なかったため、この世代の社員数が全体的に少ないという特徴があります。
管理職を行う人材の減少
日本社会ではバブル崩壊以降、人件費の抑制や「組織のフラット化」の流れが続き、管理職を行う人材の不足が深刻化しています。フラット化は意思決定のスピードを速め、商品やサービスのライフサイクルが短い事業環境においては有効な戦略です。しかし、その一方で管理職1人あたりの負担が増加し、とりわけ課長職などのフロントラインマネジャーに問題が集中しています。
さらに、オフィスワーカーや工場現場を問わず、デジタル化の進展と競争の激化により、創造的な業務以外は機械やデジタルが代替する状況が進んでいます。この中で、権限を現場に委譲する必要性が増す一方、管理職が監督する部下の数は減らず、責任と負担だけが増大しています。
また、課長職という中間的な立場にある人々は、管理職と一般職の雇用形態の違いによるギャップにも直面し、ストレスが集中する原因となっています。その結果、管理職を目指す人が減少し、さらなる人材不足に拍車がかかっています。
成果主義の風潮
成果主義の風潮は、経済の停滞や競争の激化を背景に、短期的な業績を重視する傾向が強まった結果、管理職に大きな影響を与えています。特にプレイングマネージャーの増加により、管理職はチームのマネジメントに加え、自らも現場で業績に直接貢献する責任を担うことが求められるようになりました。そのため、1人あたりの負担が過剰になりがちです。
加えて、現場での成果を求められる一方で、権限移譲が不十分な組織では、意思決定に時間がかかり、競争優位を失うリスクもあります。この状況下では、現場が迅速に動けるようにリソースや権限を下ろすことが不可欠であり、結果的に成果主義のような体制が生まれるのは必然とも言えます。
とはいえ、成果主義そのものが悪いわけではありません。失敗や経験を適切に解釈せず、結果だけを信賞必罰で評価する点に問題があります。
本来、成果主義であってもプロセスを無視するのではなく、試行錯誤を通じて価値を生み出し、そのプロセスから学ぶことが重要です。しかし、現実には振り返りや経験から学ぶための時間が確保されておらず、各個人に任されているのが現状です。
現場への変わらない期待感
現場への期待感は、経済の停滞が続く現在においても変わることなく、中間管理職に大きな責任を求める構造が続いています。経営トップが掲げる理想やビジョンと、現場社員が直面する現実のギャップを埋める「架け橋」としての役割が、中間管理職には常に求められているのです。この原則は、過去から現在に至るまで変わることなく、組織運営の要となっています。
また、経営層からは「現場が大事」「管理職が重要」というメッセージが発信され続けていますが、これは時に戦略性の不足を反映している場合もあります。中間管理職は、階層型組織において効率的なコミュニケーションの中枢を担う「連結ピン」として活用されてきました。そのため、経営層が組織全体の連携を強化するうえで、最も効果的に影響を与えられるポイントが管理職であることも事実です。この状況は、役割が増大する一方で、負担が偏る要因にもなっています。
現在のトップマネジメントは、かつてミドルマネジメントを経験していた人々ですが、現場の詳細を完全に把握することは難しく、ボトムアップの情報なしには意思決定が機能しません。さらに、現在の現場環境は、トップ層がミドル層だった頃と大きく異なるため、認識のズレが生じやすくなっています。
一方で、現在の新卒は高度な専門性を持つ人材が多く、いわゆるロワー層に属していても、その技術や知識は高い評価に値します。このようなロワー層がミドル層が未経験の仕事をこなす一方で、トップ層は急速に変化する外部環境に対応する必要があり、ミドルマネジメントはその間で「橋渡し役」として機能します。
しかし、この役割は単純ではなく、現場を理解しきれないトップ層に状況を説明し、説得する難しい責任を負っています。現代のビジネス環境において、ミドルマネジメントの重要性と業務の複雑さはさらに高まっているのです。
働き方の多様化に伴う非正規雇用の増加
働き方の多様化に伴い、職場には正社員だけでなく、派遣スタッフ、アルバイト・パート、嘱託社員、フリーランス、副業人材など、さまざまな雇用形態のメンバーが共存するようになりました。
一方で、日本企業は従来からチームでの相互依存性を重視した働き方を前提としており、これが雇用の多様化に伴い課題を生んでいます。対面で集まるグループが専門性を持つと、多様な視点が集まります。
それ自体は良いことですが、その分、意見をまとめたり話し合いを円滑に進めたりするのが難しくなります。そのため、コミュニケーション能力がこれまで以上に求められます。
さらに、1on1のような例を見ると、OJTだけで自然にスキルが身につく時代ではなくなっています。能力を伸ばすためには、個々のモチベーションを引き出し、やる気を高める取り組みが必要です。特に、業務の明確な切り分けができていない場合、管理職のマネジメントが複雑化しやすくなります。
さらに、雇用形態が多様化する中で、労働法制や賃金の問題も影響を与えており、管理職にはこれまで以上に広い視野と柔軟な対応が求められています。これは避けられない時代の流れであり、現場ではシニア層や女性、コンサルタント、外部委託(BPO)や派遣労働者など、多様な人材と協力していく環境が当たり前になっています。こうした流動的な状況に対応するためのマネジメントスキルが、中間管理職にとってますます重要になっています。
働き方改革の影響
働き方改革の推進により、非管理職の仕事量が減少する一方で、管理職の負担は増加しています。特に、早く帰る部下の代わりに、残った仕事を管理職が引き受けるケースが多く見られます。このような状況では、管理職が自宅や週末に「隠れ残業」をすることも珍しくなく、過重労働の一因となっています。
さらに、部下を育成し、突発的な問題が起こらないようにすることが解決策として求められますが、育成に割く時間すら確保できないのが現状です。働き方改革の影響が非管理職の業務削減にとどまる一方で、管理職の業務配分や役割の見直しが十分に進んでいないことが、この問題を引き起こしています。
管理職の社会的責任の増大
職場環境の多様性が進む現代では、パワーハラスメント(パワハラ)やセクシャルハラスメント(セクハラ)、さらにはLGBTQ+など、これらの課題への対応がますます重要になっています。これらは、管理職が職場の安心と公平性を保つために避けて通れないテーマです。
管理職は最新の法規制や多様性に関する知識を学び続け、偏見のない柔軟な姿勢を持つことが求められます。
管理職自身が現在感じている問題とは?
管理職が現在直面している問題は、職場の個別対応に追われるあまり、全体を見渡すための情報や時間が十分に確保できないことにあります。
しかし、これに加えて、後任となる人材の不足や管理職への意欲の低下といった課題も、組織全体で解決が求められる問題です。さらに、管理職と人事部門との間で役割や期待の認識がすれ違うことも、マネジメントを複雑化させる要因となっています。
後任の人材不足
後任の人材不足は、現代の管理職が抱える大きな課題の一つです。部下のマネジメントにおいて、メンタルヘルスのケアやジェネレーションギャップへの対応に苦労する声が多く、これが管理職の負担を増大させています。
さらに、経済の流動性が高まる中で、若手の優秀な人材が育成の途中で組織を離れるケースが増えており、十分に次世代の管理職を育てられないまま現場の負担が集中してしまう状況が続いています。
加えて、部下のマネジメントには明確な正解がなく、個々の状況に応じた対応が求められるため、管理職の負担感をより一層強めています。特に、優秀な人材が先に離職することが多い現状では、組織内での人材の持続的な育成が難しく、後任不足が深刻化する傾向があります。
管理職への意欲が世界的にみても低い
管理職への意欲が低下している現状は、日本だけでなく世界的な課題となっています。バブル崩壊以降、管理職の負担が大幅に増加し、それが精神的なストレスや自殺率の増加に直結していることが問題視されています。また、社会的な風当たりの強さや、管理職の厳しい状況が十分にケアされず放置されてきたことも、管理職を敬遠する要因の一つです。
特に、管理職の多くが人間関係や人材の問題に多くの時間を割く必要がある一方で、簡単には解決できない課題が積み重なっています。こうした中、管理職の給与が相対的に見合わない状況も、意欲の低下を助長しています。
一部の企業では賃上げが行われていますが、新卒や一般職に対する賃上げが目立ち、管理職の給与は据え置かれるケースも多いため、課長職以上を目指したいという人が減少しているのが現状です。
参考:日本経済新聞「日本の賃金水準低く 上位の役職ほど海外と差」
管理職と人事とのすれ違い
管理職と人事とのすれ違いは、現場と組織全体の運営に大きな影響を及ぼす課題の一つです。リソース不足に苦しむ現場の管理職は、部下の教育やサポートに手が回らず、日々の業務で精一杯の状況にあります。
一方で、人事部門が提供するサポートや施策が、現場の実態を十分に理解していない場合、かえって現場の混乱を招くこともあります。たとえば、ITツールの導入などが負担を増やす要因となることも少なくありません。
さらに、管理職はコンプライアンスやセクハラ防止、組織改革、デジタル推進など、組織の施策を現場に浸透させるうえで重要な役割を担っています。しかしこうした責任の増加に対して、適切な権限やリソースが付与されていないことも、管理職の負担を増大させる要因となっています。
最近では、ハラスメント問題が複雑化し、管理職が加害者としてではなく、逆に被害者として訴えられるケースも増えています。特定の社員やグループが、ハラスメントの概念を悪用して管理職を糾弾するような行為も見られ、人事部門やコンプライアンス部門が対応に苦慮しています。こうした背景が、人事と管理職のすれ違いをさらに深める結果となっています。
このような現在の環境では、社内コミュニケーションを中間管理職(ミドルマネジメント)だけに任せるのは困難であり、その限界を認識することが重要です。現場と経営をつなぐためには、社内で共通の言語を作り、情報を共有する全社的な支援が欠かせません。
最近では、トップが現場に足を運ぶ取り組みが増えていますが、それだけでは不十分です。全社的なサポートを強化しなければ、現場と経営の連携はほとんど実現できていないのが現状です。
また、HRBP(Human Resource Business Partner)のような役割が注目されており、現場に寄り添いながら人事の支援を行う存在が求められています。これにより、現場と経営のつながりをより強化することが可能となります。
万能なリーダーはそもそもいない
「万能なリーダー」は現実には存在しません。現代の複雑な産業構造の中で、数十人の部下を抱えながら成果を出し、社会的責任を果たし、さらに多様な雇用形態をマネジメントすることは、一人のリーダーに過剰な負担を求めるものです。しかし、多くの職場では、理想的なリーダー像や課長像を押し付ける風潮が残り、それがリーダーに対する不必要な万能感の期待を生み出しています。
この「万能感」の押し付けは、リーダー自身に過剰なプレッシャーを与え、結果としてモチベーションの低下やバーンアウトにつながりやすくなります。そもそも、業績を大幅に伸ばせる人材が社内に豊富に存在するのであれば、その多くが起業家として成功しているはずです。このような非現実的な期待が、組織内の人材を追い詰め、リーダーとしての成長を阻害する要因となっています。
管理職が罰ゲーム化する構造上問題
現在のビジネス環境では、「管理職」というテンプレートがもはや現実に即していない状況にあります。労働人口の減少や管理職の社会的責任の増大、成果のプレッシャーなど、管理職一人が担える範囲を超える負担が集中しており、現場では部下が専門性を持つケースも増えています。
このような状況では、細かい進め方や業務の詳細を管理する「マイクロマネジメント」は不可能であり、むしろ非効率を生む原因になっています。
さらに、社会的責任を管理職に一極集中させることも現実的ではありません。管理職という「管理する役割」に依存する枠組みそのものを見直し、権限と責任を組織全体で分散する必要があります。
管理職が「罰ゲーム」になる状況を脱するには
管理職が「罰ゲーム」と揶揄される状況を脱するためには、これまでの管理職像を見直し、新たなマネジメントスタイルを取り入れることが求められます。
一人で全てを抱え込むのではなく、権限を適切に共有するエンパワーメント型の小集団を活用し、チーム全体で業務を進める仕組みが必要です。
また、組織運営におけるトランスペアレンシー(情報の透明性)を追求することで、意思決定を迅速化し、信頼を高めることができます。さらに、外部との連携を管理職の役割として位置づけ、社内外のリソースを効果的に活用することで、新しい時代の管理職像を構築していくことが重要です。
エンパワーメント型の小集団
エンパワーメント型の小集団は、管理職の負担を軽減し、組織全体のパフォーマンスを向上させるための効果的なアプローチです。この手法では、権限を管理職一人に集中させるのではなく、チーム全体に適切に委譲することで、各メンバーが自分の役割に責任を持ち、意思決定を迅速に行える環境を作ります。
小集団化することで、チーム内のコミュニケーションが円滑になり、問題解決や目標達成に向けた行動がスピーディーに行われます。また、メンバーが主体的に業務に取り組むことで、管理職の負担が分散されるだけでなく、個々の成長を促進する効果も期待できます。
トランスペアレンシーの追求
トランスペアレンシー(情報の透明性)の追求は、現代の組織運営において不可欠な要素です。すべてのメンバーが必要な情報にタイムリーにアクセスできる環境を整えることで、透明なコミュニケーションが可能となり、組織内での信頼関係を築く基盤が形成されます。
このアプローチにより、管理職が抱える情報管理や調整業務の負担が軽減され、各メンバーが自律的に行動しやすい環境が生まれます。また、情報の透明性が高まることで、意思決定のスピードが向上し、無駄な業務や誤解を防ぐ効果も期待できます。
外部連携としての管理職
外部連携としての管理職の役割は、チームの内外をつなぎ、柔軟な組織運営を可能にすることです。
マサチューセッツ工科大学のデボラ・アンコナ教授が著書『Xチーム』で述べているように、生産性の高いチームは内部に閉じることなく、外部との関係を積極的に構築し、相互作用を続けることで成り立ちます。このような開かれたチーム構造は、現代のリゾーム型組織に近いものであり、企業全体をつなぐ力を持っています。
管理職には、チーム内のマネジメントだけでなく、外部からリソースや知識を取り入れ、チームを成長させる役割が求められます。また、年齢や経歴が異なるメンバーが、それぞれのスキルや経験に応じて成長しながら業務を進められる環境を作ることも大切です。
学びはキャリアの初期だけで終わるものではなく、入社から退職まで続くものです。管理職は、その継続的な学びをサポートする中心的な役割を担い、チームと外部をつなぐ橋渡し役として活躍する方向へと変化するべきです。
まとめ
管理職が「罰ゲーム」と言われる背景には、責任と負担が過剰に集中する現状があります。上司と部下の板挟み、成果を求められるプレッシャー、多様な雇用形態や社会的責任への対応など、管理職には多岐にわたる課題が降りかかっています。しかし、この状況を変えるためには、管理職の役割や構造を見直すことが必要です。
具体的には、エンパワーメントによる権限の共有や、小集団化による効率的なチーム運営が有効です。
また、トランスペアレンシー(情報の透明性)を高め、外部との連携を強化することで、管理職の負担を分散させ、より効果的なマネジメントが可能になります。管理職を罰ゲームではなく、やりがいあるポジションに変えるためには、組織全体での改革が不可欠です。これにより、管理職もチームも成長し、持続可能な成果を追求できる環境を作ることができるでしょう。