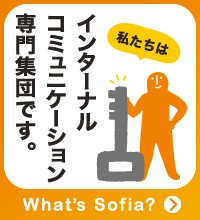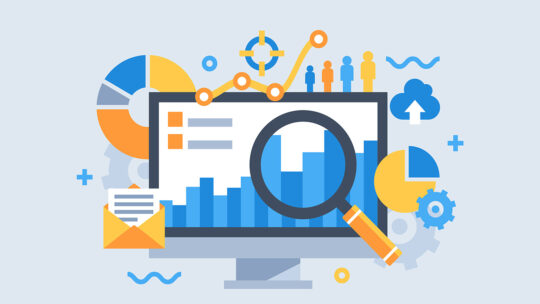2025.03.21
大企業における新規事業失敗の原因分析と“成功を導く鍵”とは?【後編】

目次
変化の激しい現代では、既存ビジネスが成功していても積極的に新規事業を立ち上げなければなりません。今や中小企業に限らず、安定性を有する大企業でも積極的に新規事業開発を進めるケースが増加しています。
今回は前後編に分けて、新規事業創出の重要性や、企業が新規事業創出を推し進める際につまずいてしまう原因などを解説します。
後編では、大企業における新規事業開発が失敗してしまう要因と、成功に導くためのポイントについて説明していきます。
前編の記事はこちら
大企業の新規事業が失敗する要因
新規事業の失敗要因は多岐にわたります。成功には十分な事前準備と正確な想定が欠かせず、不十分な想定や準備が後になって問題を引き起こす可能性があります。大企業においては、これらの問題が様々な形で現れることがあります。
新規事業の失敗につながる主な要因をいくつか紹介します。
大企業ならではの失敗を恐れる風土や社内の動きの遅さ
大企業だからといって、必ずしも新規事業の成功が保証されているわけではありません。失敗を恐れて、新しいことにチャレンジすることをためらう風土が根強い場合、イノベーションは生まれてこないのです。
大企業は、長年の歴史の中で確立された組織風土を持っています。これは安定した事業運営には不可欠ですが、一方で、新規事業の創出を阻害する要因にもなります。たとえば、稟議手続きが複雑化し、意思決定が遅れがちになってしまうと、迅速な判断と行動が求められる新規事業においては大きな足枷となります。部門間の連携がスムーズさを欠いてしまうことも、社員のモチベーションを削いでしまう原因になるでしょう。
既存事業の成功モデルを重視し、新しいアイデアを阻んでしまう
長年つづく既存事業の経験から生まれた既成概念によって、新しいビジネスモデルへの挑戦をためらったり、新しいアイデアや視点を受け入れにくかったりすることがあります。従来の枠組みや価値観に縛られ、新たな市場や顧客ニーズに適応した革新的な発想が生まれにくくなります。また、成功モデルに基づく判断基準が新規事業の評価に適さない場合、潜在的な成長機会を見逃す可能性もあります。
短期的な成果に固執してしまう
新規事業は、短期的な利益よりも中長期的な視点での投資が必要となりますが、大企業は短期的な業績にこだわりすぎて、長期的な視点を持つことが難しい場合があります。
事業計画の段階で経営破綻しないための施策を立てることは必須です。しかしながら、あまりにも赤字を恐れすぎて、成功の機会を逃してしまうことがあるかもしれません。目先の利益のみを追い求め、短絡的な視点に陥ってしまわないためにも新規事業は方向性を定めて計画を立てる必要があります。
新規事業創出に必要なスキル・人材の不足
新規事業の展開に必要とされるスキルや経験は、既存の事業とは異なります。そうしたメンバーが不足していたり、適切な支援体制が整っていなかったりすると、新たな事業を立ち上げる段階で行き詰まることが多いです。 また、イノベーションに欠かせない才能の不足や戦略策定・実行力を持つ人材が足りないなど、適切なスキルや人材が揃っていないと、新規事業の開始や拡大が停滞するリスクが生じます。 特に、イノベーションを起こす人材には、市場を見通す力、素早い決断力、柔軟な思考、そして不確実性に対処できるリーダーシップが求められます。しかしながら、多くの企業では、既存の事業に関連したスキルや経験を重視する傾向があり、新しい事業に活かせる人材育成が不十分なケースも少なくありません。
新規事業を成功させるには
新規事業を成功させるには、市場ニーズの正確な把握、迅速な仮説検証、柔軟な戦略の調整が必要です。また、明確なビジョンの共有、適切なリソースの確保、挑戦を奨励する文化の醸成が重要です。社員の動機付けと部門間の連携を強化し、長期的な視点を持ちながら進めること大切です。ここでは成功の肝になるポイントを具体的に解説していきます。
社員視点のコミュニケーション施策設計
新規事業を成功させるためには、社員視点に立ったコミュニケーション施策が重要です。以下のポイントを押さえた施策設計が求められます。
・ビジョン共有
新規事業の目的や方向性を明確に伝え、社員が共通の目標を理解できるようにします。経営陣からの定期的なメッセージ発信や全社ミーティングの場を活用します。
・双方向のコミュニケーション
社員がアイデアや意見を自由に提案できる場を設けます。ワークショップやアイデア募集イベントを開催し、社員の参加意識を高めます。
・透明性の確保
新規事業の進捗状況や成功・失敗の事例を定期的に共有し、社員が事業への関心と信頼を持てる環境を整えます。社内ニュースレターやポータルサイトを活用すると効果的です。
・部門間連携の促進
既存事業部門との情報共有や協力体制を強化するため、クロスファンクショナルなチームを編成し、交流機会を増やします。
・成功体験の共有
社員が新規事業に参加する意義を感じられるよう、成功事例や貢献の成果を社内で称賛し、広めます。
これらを通じて、動機付けを行い社員の理解と協力を得ることで、新規事業の推進力を高めることが可能になります。

社内コミュニケーションがうまくいかない原因を徹底究明!失敗しない社内コミュニケーション施策
社内コミュニケーションの改善には、言語化や数値化などが欠かせません。この記事は社内コミュニケーション活性化の…
成功のポイントは文化醸成と動機付け
新規事業を成功させるために挑戦を許容する文化醸成は必須です。
成功の影には、必ず失敗が存在します。失敗を避けるのではなく、失敗を受け入れ、そこから学ばなければなりません。失敗から学ばなければ、「損失」は「失敗」に過ぎません。赤字を招く結果になったとしても、他事業等で反省が活かされ、成功を収めることもあります。つまり、企業は新しい戦略を試すことに寛容でなければならず、正しい解決策を見つける前に複数の解決策を試すことを恐れてはならないのです。重要なのは、多少の損失を恐れずに新たな事業を推し進めるマインドと、それを是とする組織の風土・姿勢なのです。組織がそうした姿勢を取っていると自然と新規事業創出への心理的ハードルが下がり、参加者の分母を増やすことにもつながります。
組織文化の醸成に関わる要素は目に見えないものが多くを占めますが、既存事業部門と新規事業部門の連携を強化し、リソースや知識を共有できるようにしておくことも組織全体で新規事業を後押しする手段の一つになるでしょう。
また、失敗を恐れず挑戦するマインドを長期的に維持するには内発的動機付けが必要です。一般的に内発的動機付けには、「責任感」「充実感」「達成感」「自尊心」など、感情に紐づいた要素が関与しています。新規事業の推進を上層部等から阻害されるとこれらを欠いてしまう可能性があるため、動機付けには組織の姿勢が大きく関わっていることを意識しなければなりません。
ソフィアの考え、ご支援が可能なこと
一般的な新規事業開発プログラムでは、個人の能力開発に焦点が当てられており所属する組織の未来や事業計画が視野に入っていないものが多いです。
ソフィアでは、会社や経営の視点を持ち社会問題を捉え、個人としてではなく会社や組織、ひいては社会の一員としての事業開発能力を位置づけし実践に繋げる新規事業創出プログラムを薦めています。このプログラムでは自発的に行動出来ていない社員や新しいことにチャレンジしたい社員などへアプローチを行い、イノベーション風土の点火や人材の発掘を目標としています。
新規事業創出プログラム全体の流れ
では、ソフィアの考える新規事業創出プログラムとはどのようなものなのか、簡単な流れをご説明します。
大まかに以下の3つのフェーズに分かれています。
フェーズ1:設計/構築
従業員からのヒアリングやアンケートを通して、社員の体験マップ(エンプロイージャーニーマップ)を作成しコンセプトを立案、社員の動機付けや興味喚起を行う社員サイト・効果的な情報発信体制の構築。
フェーズ2:社員の巻き込み
特別研修や有識者を招いたセミナーなどのイベントを行い、社員の認知や興味喚起の促進。
フェーズ3:事業化
状況に合わせたアイデアコンテストのテーマ検討や応募要項の整理、応募後の絞り込みの支援。
その後、事業化に向けたブラッシュアップやスキルアップの支援を実施。
これらの支援を通して、社員の自立性や自発性の醸成、風土改革を促します。
まとめ
大企業は既存事業や、長年培ってきた成功体験に固執することが多く、新規事業においてはスキルや経験が必要となる業界で苦戦することがあります。成功には現場目線のコミュニケーション施策の設計したうえで、失敗を学びと捉える文化を醸成し、柔軟に戦略を調整することが重要です。
新規事業開発の難しさに共感いただけた方や、もう少し詳しく知りたい方はどうぞお気軽に、ソフィアまでご相談ください。

株式会社ソフィア
エディター
田中 佑季
主に社内報や社内コンテンツの編集を担当しています。原稿執筆、ディレクションといったひと通りのエディター業務が得意です。PhotoshopやIllustratorなどを用いたデザイン制作も対応します。
株式会社ソフィア
エディター

田中 佑季
主に社内報や社内コンテンツの編集を担当しています。原稿執筆、ディレクションといったひと通りのエディター業務が得意です。PhotoshopやIllustratorなどを用いたデザイン制作も対応します。