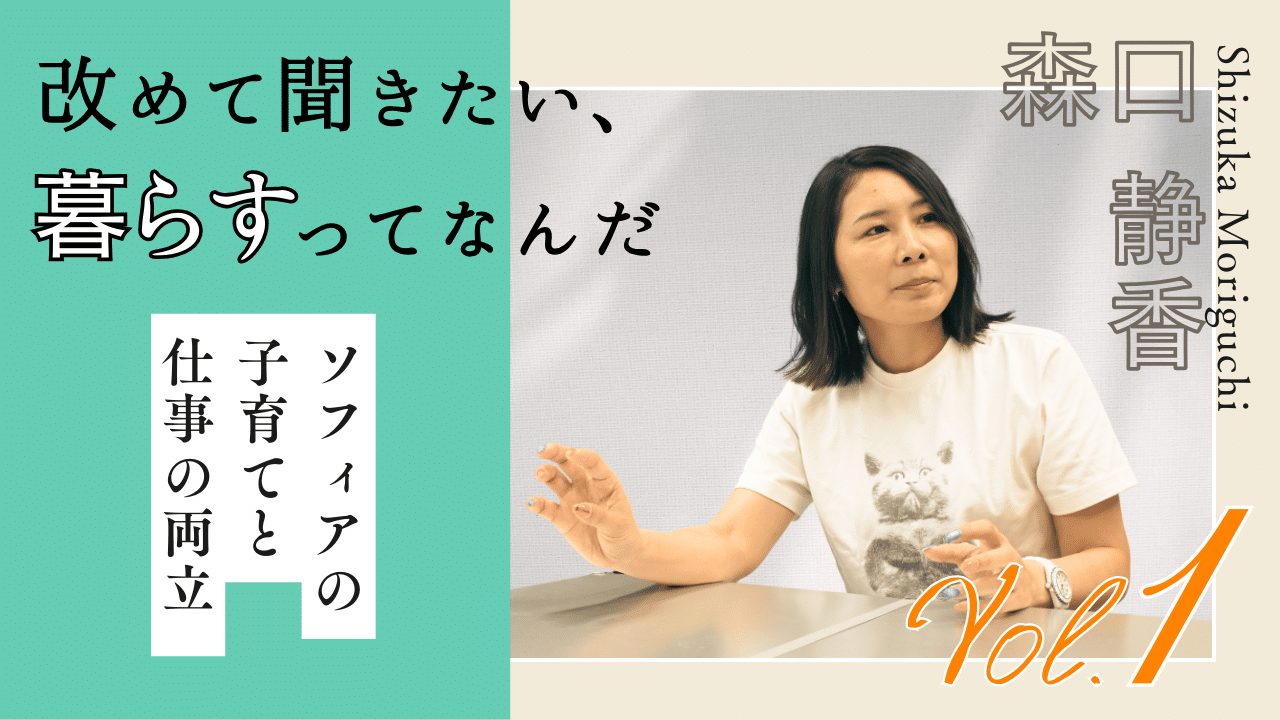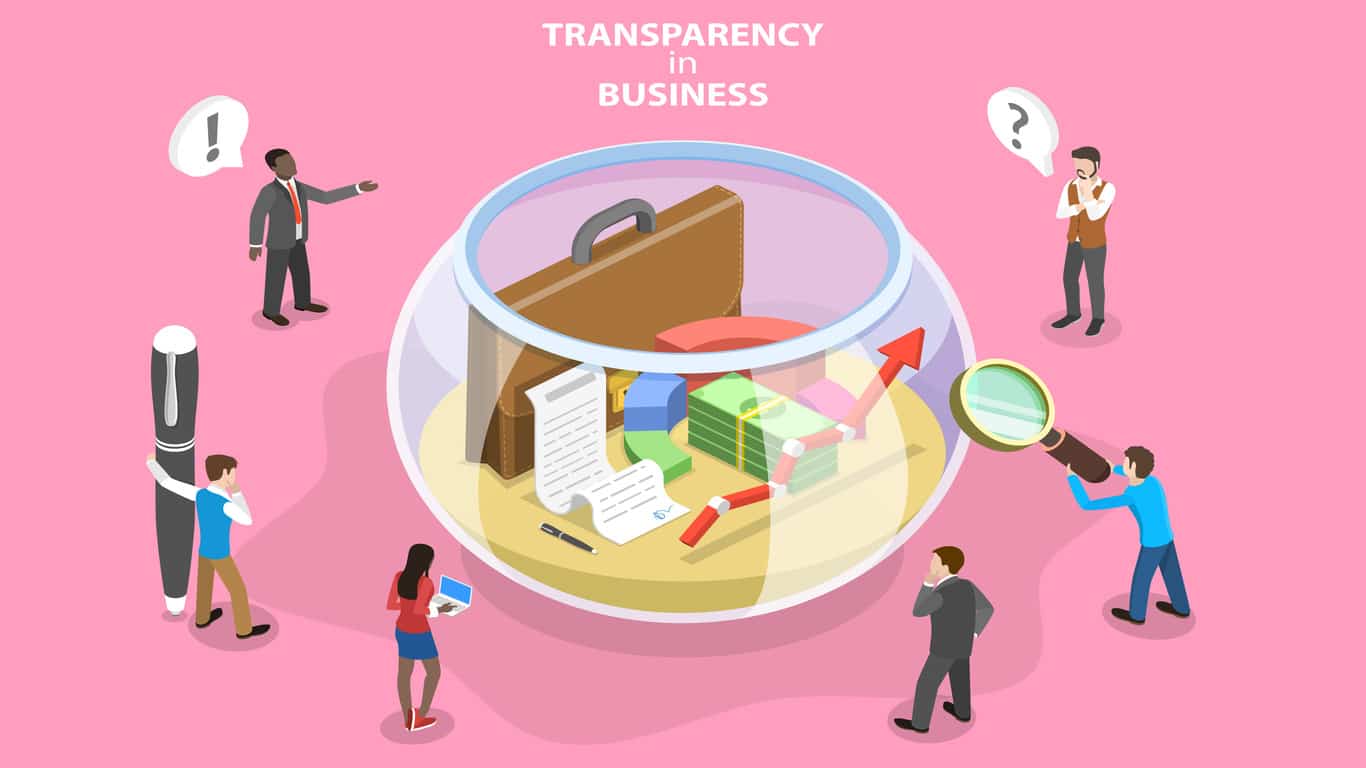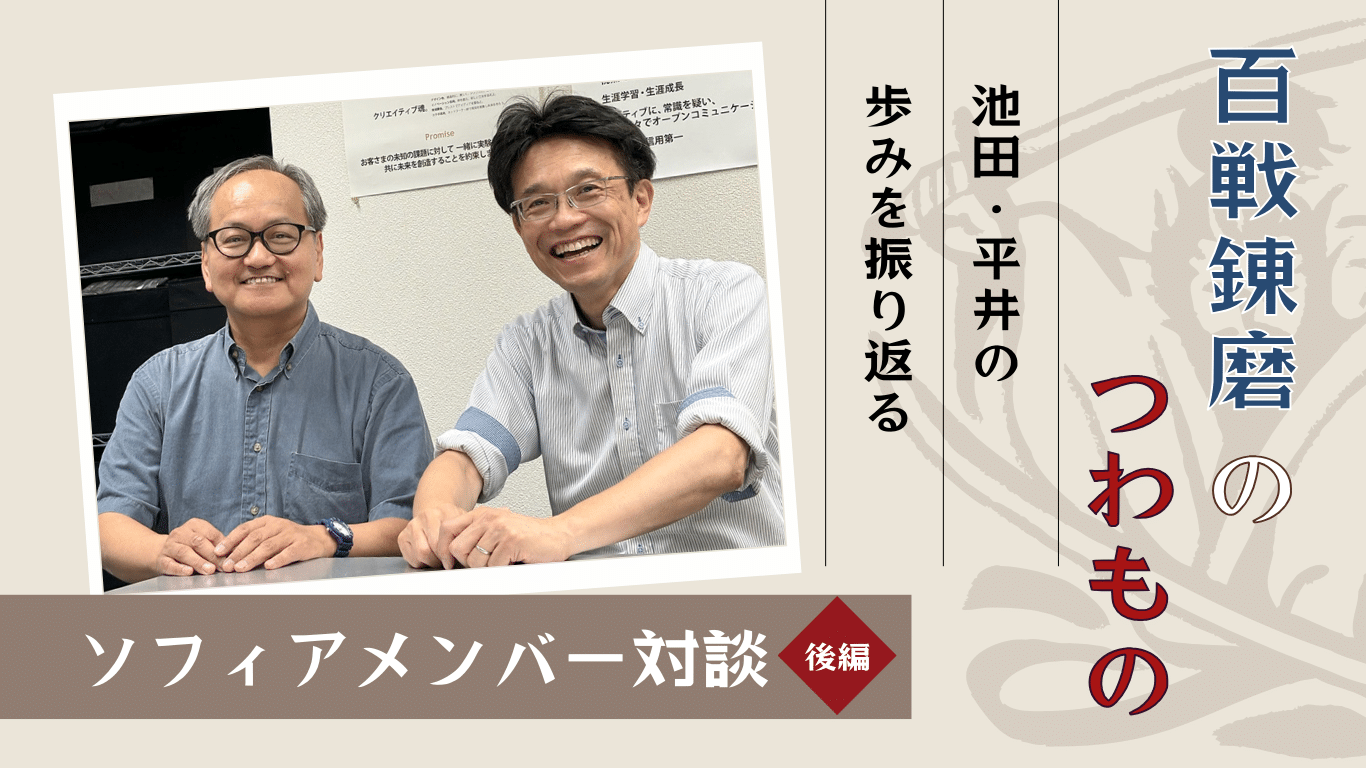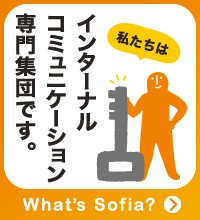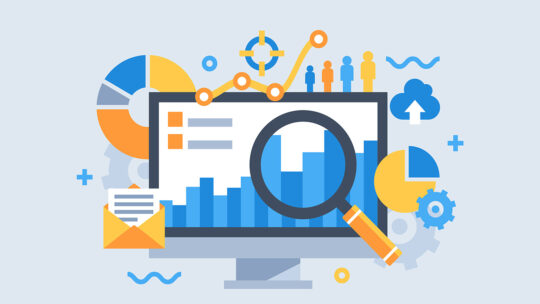2025.04.08
キャリアデザインとは? 意味や考え方、キャリアデザインが重要な理由を解説

目次
キャリアデザインとは、自分のキャリア(職業や人生の道筋)を計画し、目標達成に向けた行動を具体化する考え方です。現代は働き方の多様化や技術革新の進展により、一人ひとりが自分のキャリアを主体的に築くことが求められています。
しかし、「不確実な時代」と言われる現代において、個人が設計した人生や職業の未来は、本当に計画通りに進むのでしょうか? そもそも、設計主義的な人生は実現可能なのでしょうか?
本記事では、キャリアデザインの意味や基本的な考え方を詳しく解説し、どのような軸を持ってキャリアデザインをすべきか、その重要性について具体的に探っていきます。
キャリアデザインとは?
キャリアデザインとは、将来のなりたい姿や理想の自分を実現するために、自ら職業における人生を設計し、それを実現していくプロセスです。キャリアデザインを行うことで、目指すゴールを明確にし、必要な知識やスキル、経験を洗い出すことができます。
その結果、「いつまでに何をすべきか」が具体的になり、実現に向けた行動が取りやすくなります。自分のキャリアを主体的にデザインすることは、人生全体の充実度を高める重要なステップといえるでしょう。
また、キャリアデザインは、目指すゴールと今までの過去の経験やスキルの洗い出しをする振り返りと、変化の中で継続的にデザインを繰り返すことが重要です。
キャリアデザインとキャリアプラン・キャリアパスなどとの違い
キャリアデザインは、理想の将来像を描きながら自分のキャリアを主体的に設計する考え方を指します。一方で、キャリアプランやキャリアパスはその具体的な計画やステップを意味し、キャリアデザインの一部として位置づけられます。これらの違いを理解することで、自分にとって最適なキャリア形成の方法が見えてくるでしょう。
キャリアデザインとキャリアパスとの違い
キャリアパスは、企業内での昇進や目標とするポジションを目指す具体的な道筋を指します。これは、組織の中での成長を軸に考えられています。一方で、キャリアデザインは、特定の企業や組織に縛られることなく、自分自身の価値観や目指す将来像に基づいてキャリアを設計するものです。昇進や社内でのポジションに限定されない広い視点で、自分らしいキャリアを構築することを目的としています。
キャリアデザインとキャリアプランとの違い
キャリアプランは、今後やりたい仕事や理想の働き方を具体的にプランニングすることを指します。職業やスキルの獲得といった仕事に関する要素が中心です。一方で、キャリアデザインは、職業だけに留まらず、プライベートも含めた理想の人生を送るための全体的な行動計画を指します。つまり、キャリアプランが「仕事に焦点を当てた計画」であるのに対し、キャリアデザインは「人生全体を視野に入れた設計」といえます。
キャリアデザインとキャリア形成との違い
キャリア形成とは、自分のビジネスキャリアや目的を計画し、それ実現するために必要な知識やスキルの習得や、課題を克服しながら経験を積んでいく活動を指します。一方で、キャリアデザインは、そのキャリア形成を実現するために「どのような人生を送るのか」を設計することを意味します。つまり、キャリア形成が実際の行動や経験に重点を置くのに対し、キャリアデザインはその基盤となる全体的な人生設計に焦点を当てています。
しかし、これら全てに共通するのは、スキルや経験が計画通りに積み上げられるとは限らないという現実です。環境の変化や個人の価値観の変容、さらには予測不能な社会の動きによって、どれだけ綿密に設計しても思い通りにはならないことがほとんどです。キャリアデザインは重要な指針にはなりますが、それ自体が完全な設計図にはなりえないのです。
「キャリアは設計できる」という前提自体が、そもそも不確実な時代にはそぐわないのではないでしょうか?
キャリアデザインが重要視されている理由
では、なぜキャリアデザインが重要視されているのでしょうか?現代社会では、変化する社会や年功序列の崩壊に伴い、個人のスキルや価値観を軸にキャリアを形成する動きが加速しています。
また、人材の流動性が高まり、企業は「自律型人材」を求める傾向が強まっています。以下では、これらの背景とキャリアデザインの必要性について詳しく解説します。
変化する社会への対応
グローバル化が進む現代では、不透明な社会情勢が企業の業績や働き方に大きな影響を及ぼしています。しかし、一見変化が激しいように見えますが、スキルや知識が移り変わるのはどの時代でも当たり前のことであり、日本はむしろ変化が少ない方だとも言えます。
必要なスキルが移り変わるということは、求められる職業も常に変わり続け、稼げなくなる仕事が増えるということです。そのため、今の時代、1つのスキルに固執するのではなく、複数の分野を極めることが重要になっています。
もちろん、1つの専門性を深めることは大切ですが、3つや4つの専門分野を持つことで、希少価値が高まります。これが「H型人材」と呼ばれる考え方です。また、変化しているスキルの多くは比較的習得しやすいものも多く、学ぶこと自体のハードルは必ずしも高くありません。
1つのスキルの専門家になるには、長くても5年、大抵は3年もあれば充分です。ただし3年程度の勉強では、専門家になれたとしてもその道のプロまでは難しいかもしれません。ここで重要なのは「掛け算」という考え方です。たとえプロクラスになれなかったとしても、専門家として話ができる分野を3つ持っておけば、その掛け算の効果によって、自分にしかできない分野が自然に表れてきます。
たとえば、BtoBマーケティング業務とBtoBの法人営業業務の2つを専門的に3年以上経験し、専門家として実務を遂行できる人は少ないでしょう。さらに、これをビジネスレベルの英語でこなせる日本人となると、一気に希少性が高まります。
「H型人材」になるにあたり、今やっている仕事に近い業務のスキルを加えることが鉄則です。また、ここに外国語を加えるだけで希少性は上がります。とくに英語は、応用範囲が無限で学習方法が確立されているため、押さえておきたいスキルです。
重要なのは、「変化が怖い」と不安になるのではなく、小学生や子どものように「できることが増えていく楽しさ」や「成長する喜び」に目を向けることです。そうすることで、変化をポジティブに受け入れ、柔軟に対応できるようになります。
年功序列体制の崩壊
多くの企業が年功序列体制から成果主義へと移行し、1つの企業で定年まで働く終身雇用制度も崩壊しつつあります。ビジネスの変化に伴い、必要とされる専門性や技術も刻々と変化し、特定の業務を長期間続けることが難しくなっています。しかし、これは単に「仕事が不安定になった」という話ではありません。業務の複雑性が増すことは、言い換えれば仕事の種類が増えているということでもあります。
たとえば、かつて「百姓」という言葉は「百の姓(名字)」を持つ、さまざまな仕事ができる人を意味していました。日本では苗字や屋号が職業を表すこともあり、現代では、「百姓=農業に従事する人」という意味合いになりましたが、本来の意味は「一つの仕事に縛られず、多様なスキルを持つ人」というものです。
昔の農家は「田んぼをやるなら畑もしろ」「空いている時間は漁に出ろ」「冬は縄を編め」と言われていたように、一つの仕事に頼るのではなく、環境に応じてさまざまな仕事をこなしていました。農業は天候や気候に左右されやすく、1つの仕事だけでは生活が安定しなかったためです。
現代のビジネス環境もこれと同じです。企業や業界の変化が激しく、特定の仕事だけに依存することがリスクになりつつあります。だからこそ、一つのスキルを磨くだけでなく、複数の職種や分野に適応できる能力が重要になっています。
人材の流動性が高まっている
終身雇用の崩壊により人材の流動はもはや当たり前の状況となっています。これにより、個人が多様なキャリアを築くチャンスが増える一方で、自己責任でキャリアを設計する力がますます重要になっています。
転職は悪いことではなく、新たな知識や経験を得る手段となり、軽々と越境できる存在になることが重要です。企業にとっても、越境学習を経験した社員は独自性や専門性を高め、より大きな価値を生み出します。越境というと大きな変化を伴うように感じますが、小さな一歩でも視野を広げる機会になります。
たとえば、テレワークやプロボノ活動、兼業などを通じて、新しい環境に触れることも越境です。不安にとらわれるのではなく、変化の中で得られる気づきや成長に目を向けることが重要なのです。
人は一か所に留まり続けると成長が無くなり、進歩も止まります。やがて時代についていけなくなり、社内での生産性に貢献することも難しくなります。「使えない」と言われる中高年社員が生じてくる理由もここにあります。本来なら、経験と落ち着きを備えた50代こそキャリアの黄金時代であるが、その年齢に至ったところで生産性にはつながらず、評価がもらえないといった形になってしまうのは残念なことです。
中高年になっても必要とされる人材になるためには、20代、30代から多くの経験を積み、多くの場所にいき、多くの人と仕事をすることです。それによって、「優れた社員とはどういうモノか?」が、自ずと明らかになってくるでしょう。絶えず自分に新しい課題を課し、絶えず自分を新しい場所に置き、絶えず時代の流れに敏感であることが、今後の社員に求められるスキルではないでしょうか。そうなった際に転職の機会が表れた場合、非常に有利なスキルアップの機会として目に映るのかもしれません。
「自律型人材」が求められる
企業は、働き方や労働への価値観が多様化する中で、自ら考え主体的に行動できる「自律型人材」を求めています。職種やスキルの多様化が進み、プロンプトエンジニアのような新しい職種も生まれる中、自分の専門性を深めながら柔軟に対応できる力が重要です。
これまで、自律的に働きたくても、組織内の権限や情報へのアクセスが制限され、思うように動けない状況がありました。しかし、雇用の流動化が進み、副業やフリーランスなどの働き方が広がることで、こうした制限がなくなりつつあります。今や、自律できる環境が整いつつあり、個人が主体的にキャリアを築ける時代になってきています。
哲学的な視点から見ると、「自律した個人」の重要性に最も注目した思想がリバタリアニズムです。リバタリアニズムは1950年代のアメリカで生まれ、その後1980年代までに理論として体系化されました。
この思想の要点を一言で表すと、「個人が自律することで、その人自身だけでなく社会全体もより豊かに、より幸福になる」という考え方です。反対に、他人や企業に依存した生き方は不幸をもたらすと、リバタリアニズムでは主張します。
「独立独行」とも呼ばれるリバタリアンは、自らの能力を高め、さまざまな場面で活躍し、周囲にも良い影響を与える存在です。2025年1月にアメリカ大統領に再任されたドナルド・トランプ氏も、自他ともに認めるリバタリアンとして知られています。現在、時代は「自律した個人」へと確実に向かっています。
キャリアデザインの目的(社員側の視点)
キャリアデザインを行うことで、社員は自分の将来像を明確にし、目標達成に向けた具体的な行動を計画できます。また、「できること」や「やりたいこと」を整理しながら、自己実現を目指すことが可能です。さらに、組織から「期待されていること」に応える形でキャリアを築くことができれば、個人と企業の双方が成長できる環境を作り出せるでしょう。
これからの行動を明確にする(できること)
キャリアデザインの第一歩は、将来の「ありたい姿」に到達するため、どのようなステップを踏むべきかを明確にすることです。そのためには、今のポジションで達成すべき目標を設定し、自己研磨を重ねながら、具体的な道筋を描いていくことが重要です。また、自分の過去を振り返り、これまでの経験やスキルを整理し、現状を客観的に見つめ直すことも欠かせません。
一方で、変化の激しい時代においては、ただ目標を定めるだけでなく、「サバイバル戦略」を持つことも大切です。サバイバルという言葉には、不安やリスクを伴うイメージがありますが、決してネガティブなものではありません。むしろ、自由であることの裏返しであり、自分の選択肢を広げるための手段でもあります。しかし、日本では長年にわたり、「安定こそが正解」とされてきました。これは、30年間にわたる低成長や「未来は不確実だ」といった漠然とした危機感が刷り込まれてきたからかもしれません。その結果、多くの人が「変化を避けること」が安定につながると考えすぎてしまっています。
しかし、今の時代において本当の資産とは、「できること」そのものです。ここでいう「できること」は単なるスキルだけではなく、人とのつながりや経験、ビジネスコネクションといった人的資産も含まれます。つまり、サバイバル戦略とは「自分の資産をどこに投資するか」を見極めることでもあります。変化を恐れるのではなく、自分の持っている資産を整理し、自由な選択肢を持つことで、リスクをコントロールしながらキャリアを築いていくことができるのです。
これまで「資産(Asset)」と言えば、お金や不動産のことを指すのが一般的でした。つまり、目に見えたり、手で触れたりできるものが資産だと考えられていた時代です。しかし、そのような時代はすでに終わりを迎えています。
これからの時代における資産とは「人的資産」、すなわち自分が社会に対して何を提供できるのか、自分にはどのような仲間がいるのか、家族との間に信頼関係が築けているかといった、目には見えない価値のことを意味します。
「資産運用」とは株式や不動産への投資などのことを指していましたが、こうした考え方は今や時代遅れです。これからの資産運用は、目に見えず手に取ることもできない「インタンジブル(無形)」な資産、たとえば人間関係、信頼、スキル、経験といったものへの投資が主流になっていくでしょう。
自己実現を目指す(やりたいこと)
キャリアデザインは、単に会社内でのキャリアアップを目指すだけでなく、自己理解を深めるプロセスでもあります。自分の価値観や理想のライフスタイルを軸に、「自分らしい働き方」を追求しながら、自己実現を目指すことが重要です。これは言い換えれば、「個人の願望を形にするための設計図」を描くこととも言えます。しかし、多くの人にとって「やりたいこと」は漠然としており、それを明確にすること自体が難しく感じられるものです。
やりたいことは、必ずしも長期的なものである必要はなく、短期的な挑戦を繰り返すうちに、長期的な方向性が見えてくることもあります。深く考えすぎず、興味や関心、好き嫌いのレベルからスタートすることが大切です。現在のライフステージや環境によって制約があるかもしれませんが、それは本当に避けられないものか、ただの思い込みなのかを見極めることも重要です。
もし迷っているのであれば、まずは「お試し」で新しい経験をしてみるのも良いでしょう。興味のある職場やスキルを体験できる場に足を運ぶだけでも、新たな気づきが得られます。また、さまざまな人に相談し、意見を交わすことも有効です。やりたいことが明確になる瞬間は予測できませんが、何よりも「アクションを起こすこと」が思考を大きく変え、次のステップへとつながるきっかけになります。
自己実現を目指す(期待されていること)
自己実現とは、自分の願望を叶えることだけでなく、社会や組織からの「期待」に応えることも含まれます。現代では、社会の動向を理解し、それに基づいたマーケティング的な視点を持つことが求められています。つまり、自分のスキルやキャリアを市場価値の高いものにすることで、企業や社会に貢献できる存在になることが期待されています。
多くの人にとって、やりたいことよりも「期待されていること」を中心にキャリアを考える方が自然かもしれません。ビジネスの世界では、期待されていることに対して期待以上の成果を返すことで価値が生まれます。その積み重ねだけでも立派なキャリア設計となり、個人で無理にキャリアをデザインしなくても、豊かなキャリアを築くことは十分可能です。
「キャリアは設計すべきもの」という考え方は必ずしも正解ではありません。個人の成長は、周囲や環境との関わりの中で生まれるものだからです。しかし、もし期待に応え続けても自分が価値を感じられないとすれば、一度立ち止まり、環境や人間関係を見直すことも必要でしょう。キャリアは一方的に作るものではなく、環境との相互作用の中で自然に形づくられていくものなのです。
キャリアデザインの目的(会社・上司)
会社や上司がキャリアデザインを支援する目的は、社員一人ひとりが将来の目標を持ち、モチベーション高く働ける環境を作ることです。社員の動機付けを図ることで生産性が向上し、同時に部下のキャリア形成をサポートすることで、組織全体の成長を促進します。また、OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)を通じた実践的な育成や、情報共有を積極的に行うことで、個人と組織の成長を両立させる取り組みが重要です。
社員の動機付け
社員が仕事にやりがいや目的意識を持つことは、企業全体のパフォーマンス向上につながります。キャリアデザインを取り入れることで、社員一人ひとりが自身の目標や将来像を明確にし、それに向かって成長や挑戦できる環境を整えることが重要です。目標が明確になることで、仕事への意義を感じやすくなり、主体的に取り組む姿勢が生まれ、結果としてモチベーションの向上にもつながります。
一方で、企業と社員は利害関係にあり、個人の期待と会社の期待が常に一致するとは限りません。そのため、1on1などの対話を通じて相互理解を深め、双方の期待のすり合わせを行うことが必要です。企業が社員のキャリアや働き方を尊重し、適切なコミュニケーションを図ることで、より良い関係性を築き、組織全体の成長へとつなげることができるでしょう。
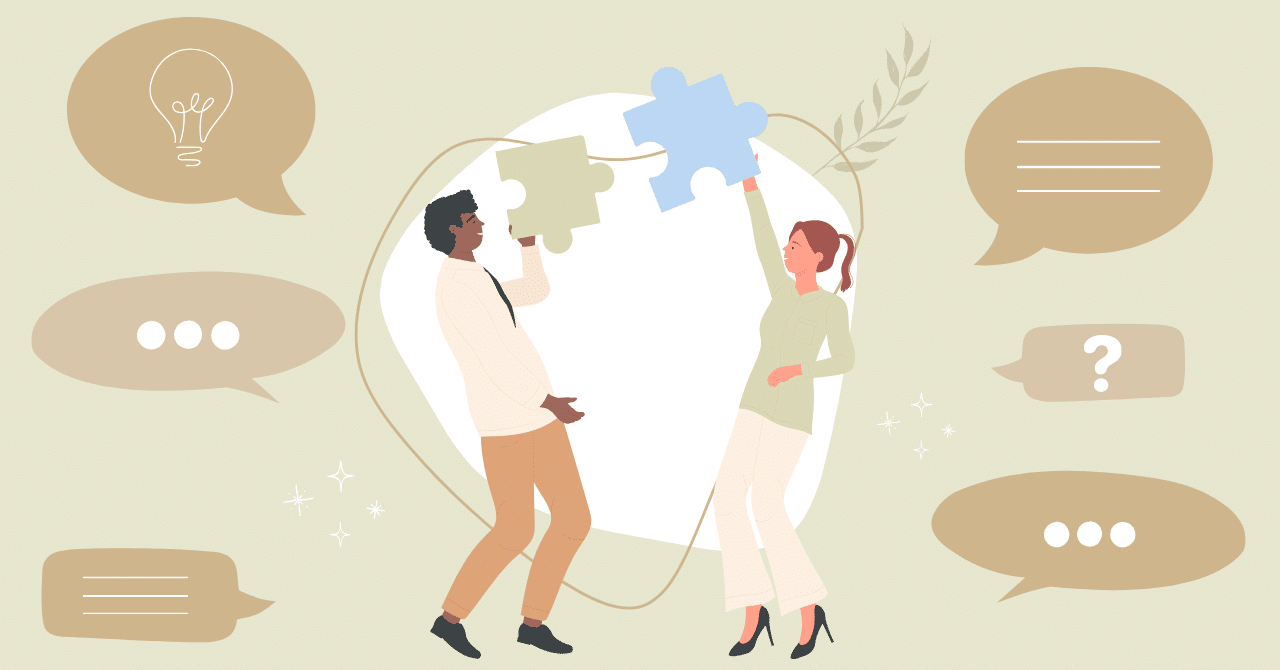
1on1(ワンオンワン)とは?目的やメリット、部下の成長を促すテクニックや話題例を紹介
最近は米国シリコンバレー由来の「1on1(ワンオンワン)」という新たなミーティングの手法がトレンドになっています…
部下のキャリア形成支援
上司には、部下が理想のキャリアパスを描き、それを実現するための支援を行う重要な役割があります。これには、適切な研修やプロジェクトを提供してスキルや経験を高める「キャリア形成支援」が含まれます。また、キャリア開発の機会を設けることで、部下が会社に対する満足感を得られるようにし、離職を防ぐ効果も期待できます。社員が自分のキャリアを築く過程で、上司が適切なガイド役を務めることは、組織全体の安定性や成長にもつながります。
先ほど述べたように、キャリアデザインは振り返りの連続です。キャリア形成支援は長期的な視点での振り返りであり、部下がこれまでの経験やスキルを整理し、将来に向けた方向性を定めるプロセスをサポートするものです。
OJT育成
OJT(オン・ザ・ジョブ・トレーニング)は、現場で実際の業務を通じてスキルを磨く教育方法であり、新人や若手社員を即戦力として成長させる重要な手段です。上司が部下に対して実践的な知識やスキルを提供することで、より早く業務に適応できる環境を整えられます。また、OJTを通じて上司と部下のコミュニケーションが深まり、信頼関係が構築されることで、モチベーション向上にもつながります。こうしたプロセスは、チーム全体の連携強化にもつながります。
キャリア形成支援が長期的な振り返りであるのに対し、OJTは個別の業務における振り返りです。どちらも、職場内での経験を通じて学びを深め、それをどのように解釈し、次の行動につなげるかが重要になります。この解釈のプロセスを適切に支援することこそが、会社や上司の大きな役割です。部下がただ業務をこなすだけでなく、経験から学び、成長できるような環境を整えることが求められます。
情報共有
多くの大企業では、社員が自身の職場や部門以外の業務に対する理解がなく、上司もまた自分の所属部門以外の動向や情報において乏しいことが一般的です。その結果、社内異動などにより、他部門で活躍できる可能性があったとしても、情報不足によってキャリアの選択肢が狭まってしまうことがあります。
この課題を解決するには、社内のインターナルコミュニケーションを円滑にし、情報を共有・提供する仕組みを整えることが重要です。上司が積極的に情報を提供し、社内の情報アクセスを向上させることで、社員はより広い視野でキャリアを考えられるようになります。また、組織や職場の情報をできる限りオープンにし、社員も胸襟を開いて情報を共有することで、会社の期待と個人の希望の合意形成がスムーズに進むようになります。
しかし、多くの企業ではこの情報の可視化が十分にできていないのが現状です。タレントマネジメントや社内ポータルの活用を進め、社内のリソースや機会を適切に共有することで、社員のキャリア形成をより効果的に支援できる環境を整えることが求められます。
会社は持続可能な生産性を、社員は持続可能な成長を求めている
企業は、社員に対して長期的な生産性を維持しながら働き続けてもらうことを望み、社員は自身の「やりたいこと」を追求しながら成長し続けられる環境を求めています。一見すると相反するように見えるこのニーズを調和させるために、上司や人事がキャリアコンサルティングの役割を担い、社員が社内で成長できる環境を整えることが求められています。とくに、生産性の高い社員には社内にとどまってもらいたいという企業の意図が背景にあります。
しかし、現代では社員が企業や職場を選択する権利が強まり、「ジョブ型」への移行が進んでいます。その結果、転職や離職が容易になり、社員は柔軟にキャリアを切り拓くことが可能となっています。とくに若手社員の早期離職が企業にとって大きな課題となる一方で、「出戻り社員」を受け入れるケースも増え、企業と個人の関係はより流動的になりつつあります。
社員をとどめるEVP
こうした環境の変化に対応するため、企業は単なる「雇用の場」ではなく、社員が成長し、キャリアを築くための「学びの場」としての価値を提供することが求められます。この流れの中で、企業がいかに魅力的な場を提供できるかを示すEVP(Employee Value Proposition)の重要性が増しています。EVPとは、企業が社員に対して提供できる価値のことを指し、ワークライフバランス、福利厚生、キャリア成長の機会など、社員がその企業にとどまる理由となる要素を明確にするものです。
企業にとって、優秀な人材を確保するためには、競合との差別化を図り、独自のEVPを策定することが不可欠です。とくに、スキルの高い人材が求める環境を提供できなければ、他社に流れてしまうリスクが高まります。そのため、EVPは固定されたものではなく、定期的に見直し、従業員の意見を反映しながら進化させるべきものです。
今後、企業はEVPを通じて、「この会社で働くことがいかに価値のある経験になるか」を伝え続けることが求められます。単なる雇用の場ではなく、個人の成長を支援し、魅力的なキャリアの選択肢を提供できる企業こそが、優秀な人材を惹きつけ、持続的な成長を実現できるのです。
「この会社にいたい」と思わせる「夢」の共有
では、福利厚生を充実させれば、優秀な社員を引き留めることができるのでしょうか。あるいは、給料を上げれば離職率を下げられるのでしょうか。本質的に大切なのは、福利厚生や給与よりも、その会社に「夢」があるかどうかです。そして、その夢が社会にとって価値があり、社員自身も「その夢の実現に関わりたい」と感じられるかどうかが、最大のポイントです。
企業の業績には波がありますし、社員一人ひとりの成果も毎年安定しているわけではありません。そうした変化や不安定さを乗り越えて、それでも社員が「この会社にいたい」と思えるのは、夢を共有できているからです。
企業が社員のキャリア形成を支援すればするほど、社員の可能性は高まり、同時に他社に移る可能性も高くなります。そんなときでも、社員が今の会社にとどまりたいと思う理由として最も強いのが、夢の共有です。経営者は夢を語り、ビジョンを示す。そして自社が社会の中でどのような役割を果たしているかを明確に伝えることが大切です。さらに、社員一人ひとりとの丁寧なコミュニケーションも欠かせません。
キャリアデザインは双方が自律するための合意形成
これまで、会社と社員の関係は、どこか「なぁなぁな関係」「ずるずるべったりな関係」に基づいていたと言えます。社員は会社に守られているという安心感から、多少の失敗や適当な対応でも「最終的には会社がなんとかしてくれるだろう」と考えがちでした。一方で、会社も社員を「家族」のように捉え、異動や転勤など無理を求めても大丈夫だろうという感覚が根付いていました。
確かに、日本企業の家族的な温かい組織文化には良い側面もあります。しかし、強い依存関係が生じることで、そのメリットを打ち消すほどのデメリットを生むことも少なくありません。たとえば、閉塞感や形だけの服従(面従腹背)といった、大企業病の典型的な症状が現れます。社員はリスクを取らず、新しい挑戦を避け、結果として組織の成長が停滞してしまうのです。
現在では、会社は「場」としての役割を強め、社員と企業が自律した関係を築くことが求められています。会社は社員が成長できる機会を提供し、社員はその場を活用してキャリアを築く。双方が「支配・依存」の関係ではなく、「合意・協力」の関係へとシフトすることで、組織と個人の成長が両立する新しい働き方が生まれつつあります。
家族的な組織の最大の弱点は、「他者」に出会ったときに、どうしてよいのかがわからなくなることです。これまで家族のような付き合いしかなかったため、他者との付き合い方がわからなくても当然でしょう。しかし、グローバル化された今、日本のどこにいても他者から影響を受け、他者と出会う事になります。しかし、その他者が顧客になってくれる可能性も考えると、他者との接触があることは大きなビジネスチャンスでもあります。
キャリアデザイン通りになったビジネスマンは少ない
成長しない会社に所属することは、個人の成長の機会が限られることを意味します。とくに日本では、成長している企業を見つけるのが難しいと言われる中で、自分のキャリアを実現するためには、成長可能性のある企業を選ぶ必要があります。しかし、成長企業に入ったからといって、それだけで成功が保証されるわけではありません。
成長企業では、成長意欲の高い人々と切磋琢磨する環境が待っており、自ら努力しなければ埋もれてしまいます。一方で、安定を求めて成長を諦める選択もありますが、どちらを選んだとしても、自分の市場価値を高め、競争を勝ち抜くことが求められます。
計画したうえでの経験や学習が重要
キャリアデザインをしっかり設計したからといって、ビジネスや人生が計画通りにうまくいくことはほとんどありません。むしろ想定外のできごとや紆余曲折を経るからこそ、サバイバルな物語が生まれ、豊かな経験が積み上がっていくのです。もし計画通りにすべてが進むのであれば、それは新しい学びや成長の機会が少ない証拠とも言えるでしょう。
重要なのは、経験と振り返りを繰り返しながら学習を積み重ねることです。その媒介として、ゴールや計画は仮説的に存在するに過ぎません。計画はあくまで「進む方向を定めるための仮説」であり、それに固執するのではなく、状況に応じて修正しつつ自らのキャリアを切り拓いていく姿勢が、何よりも大切です。経験と学びを繰り返すことで、結果として想定を超えた成長や自己実現が生まれていくのです。
思っても見なかった自分になる
「思い通りの自分になる」という言葉が、大学のキャリアデザインの場などで語られることがあります。しかし残念ながら、人は思い通りの自分にはなれません。たとえなれたとしても、その先に待っているのは、あまり面白くない人生かもしれません。
むしろ「思ってもみなかった自分になる」、これこそがキャリアデザインの本質です。最初から結末のわかっているゲームほど、つまらないものはありません。先が見えないからこそ、ワクワク感や不安、希望や恐怖といった感情が生まれます。そうした感情こそが、人生そのものではないでしょうか。
今の段階で、自分のゴールをはっきり決めても、あまり意味はありません。ゴールはあくまで仮説にすぎません。その仮のゴールに向かって進む過程で、思いがけない人と出会い、自分でも知らなかった才能に気づき、最終的にはまったく別のゴールにたどり着くことがあるのです。それこそが、本当のキャリアデザインなのです。
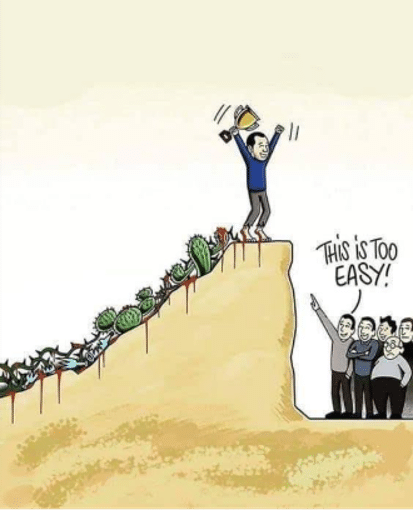
キャリアデザインのために必要な会社がすべきこと
キャリアデザインを効果的に進めるためには、会社が社員を支援し、自律的に成長できる環境を提供することが不可欠です。上司との1on1ミーティングや社内情報の共有、企業ビジョンの浸透など、具体的な取り組みを行うことで、社員が自身のキャリアを描きやすくなります。以下では、それぞれの施策について詳しく解説します。
1on1導入
上司と部下が定期的に対話を行う1on1ミーティングは、社員の目標や課題を共有する貴重な機会です。ただし、形骸化せず、実効性のある運用をすることが重要です。目的を明確にし、社員の課題解決やキャリア目標を達成するための具体的なアクションを話し合う場とすることで、双方にとって有益な時間となります。
社内・部門紹介
大企業では、社員が自部門のことしか知らず、他の部門や社内でのキャリア機会に気づけないケースが少なくありません。社内の情報を社員に提供し、適切に紹介することは、社員のキャリア形成を支援する上で非常に重要です。また、福利厚生の利用促進など、情報提供を強化することで社員の満足度を高めることもできます。
ビジョン浸透
企業が掲げる未来像や戦略を社員に十分伝えなければ、社員は自分の仕事との関連性を感じにくくなり、モチベーションが低下します。ビジョンの浸透は、社員が自分の仕事に意義を見出し、組織の一員としての目標を共有するための重要な取り組みです。
情報の透明化
情報や現在地をできる限り、共有化し、透明化していくことが必要です。個人のキャリアと会社のビジョンは、情報の非対称性によって残念な結果になっている場合も多く、個人にとっても会社にとっても不幸な状態を招いてしまう可能性もあります。労働市場は流動化していますが、社内の労働者は流動化していません。これにより、不幸な離職や退職が増加しています。社内の情報の透明性を徹底的に高めることで、柔軟な人材配置が可能となり、社員が望む経験、社員に適した経験につながります。
キャリアを構築する要素
キャリアデザインを実現するためには、以下の3つの要素を明確にすることが重要です。
- 知識・技能
業務を遂行するための具体的な能力やスキル - 行動特性・思考特性
物事への取り組み方や考え方の傾向性 - マインド・価値観
キャリアに対する意識や動機付け
これらを整理することで、現状の課題と目指すべき方向性が明確になり、より具体的なキャリア計画を立てることができます。
キャリアデザインの設計方法
キャリアデザインを成功させるには、明確なステップを踏むことが重要です。現状を把握し、目指す姿を描き、ギャップを埋める行動計画を立てることで、理想のキャリアに近づくことができます。
現状把握
まずは、自分の保有しているスキルや強み、弱みを把握することがスタート地点となります。これにより、自分の現在の立ち位置を客観的に理解し、キャリア設計の土台を作ることができます。過去の経験や達成した成果も洗い出し、今後のキャリアに活かせる要素を整理しましょう。
将来なりたい姿を書き出す
次に、過去の振り返りや現状把握をもとに、自分が目指したい「ありたい姿」や将来像を考えます。ここで重要なのは、具体的な目標を持つだけでなく、自分らしいキャリアに到達するためにどの道を選ぶべきかを考えることです。このプロセスは、キャリアデザインの核となります。
現状とのギャップを洗い出す
目指す将来像と現在の自分との間にあるギャップを洗い出します。スキルや経験、性格的な特徴など、達成に必要な要素を整理しましょう。また、自分の周囲にいる人々からフィードバックをもらうことで、客観的な視点を取り入れ、ギャップをより正確に把握できます。
キャリアを考える
将来像が明確になったら、その目標に到達するための具体的なキャリア段階を計画します。必要なスキルや経験をリストアップし、それを得るためにどのような業務に取り組むべきかを考えることが重要です。このプロセスを通じて、自分の成長に必要なステップが具体化されます。
行動する
計画を立てたら、それを実現するための具体的なアクションを起こします。たとえば、スキルを習得するための研修を受ける、関連するプロジェクトに参加するなど、自分に必要な経験を積む行動を実行しましょう。行動することが、キャリア実現への第一歩です。
まとめ
キャリアデザインは、社員と会社の双方にとって成長の鍵となる考え方です。社員にとっては自己実現を追求しながら成長する手段であり、会社にとっては社員の能力を最大限引き出し、生産性を向上させるための重要な施策です。
現代の変化するビジネス環境では、双方が自律した関係を築きながら、共に成長を目指すことが求められています。社員の目標をサポートし、企業ビジョンを共有する取り組みを強化することで、持続可能な成長と生産性向上を実現していきましょう。

株式会社ソフィア
先生
ソフィアさん
人と組織にかかわる「問題」「要因」「課題」「解決策」「バズワード」「経営テーマ」など多岐にわたる「事象」をインターナルコミュニケーションの視点から解釈し伝えてます。
株式会社ソフィア
先生

ソフィアさん
人と組織にかかわる「問題」「要因」「課題」「解決策」「バズワード」「経営テーマ」など多岐にわたる「事象」をインターナルコミュニケーションの視点から解釈し伝えてます。