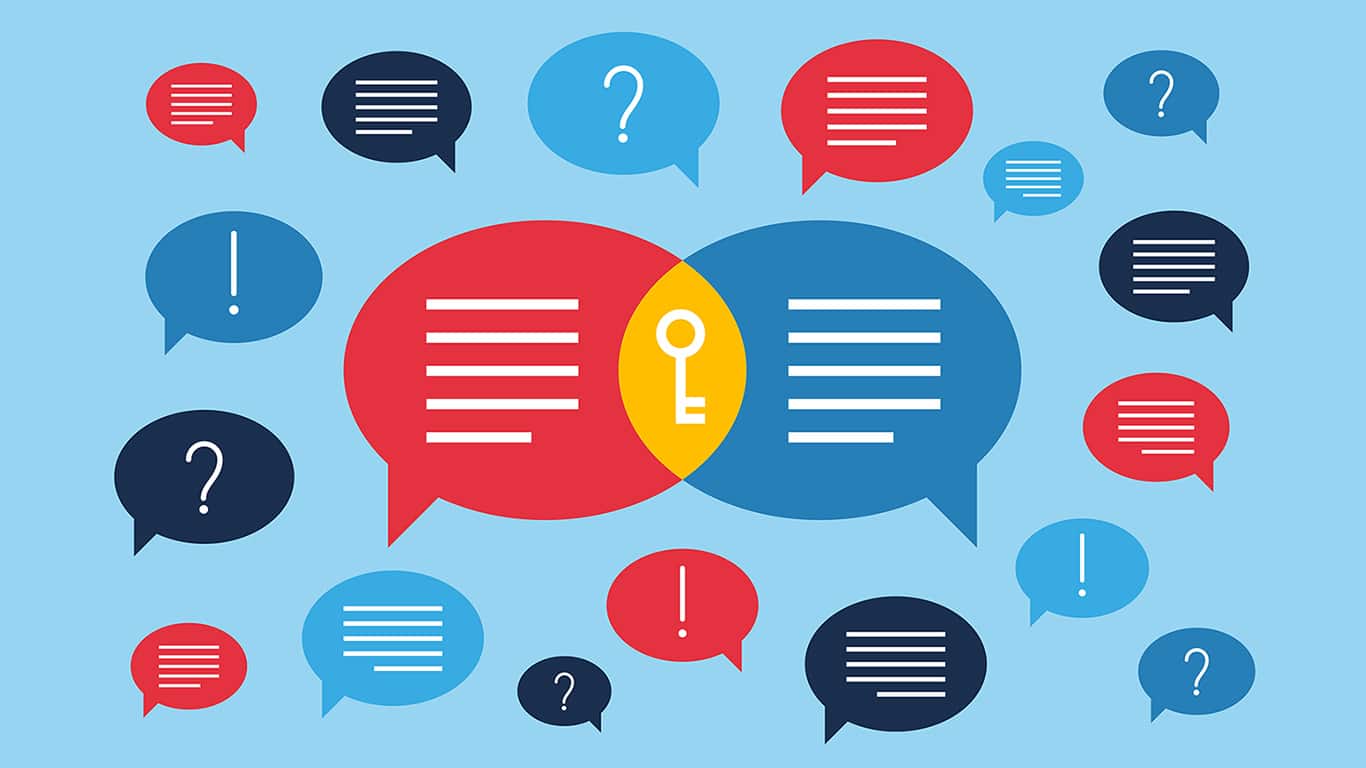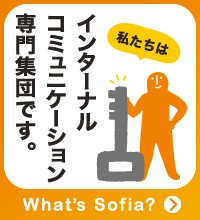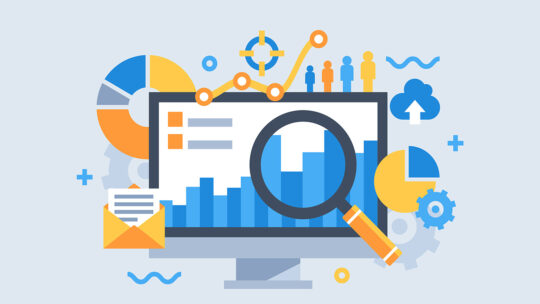若手のキャリアへの考え方が重要な理由!なぜキャリア研修が必要なのか解説

目次
現代のビジネス環境は急速に変化しており、若手社員には主体的にキャリアを設計し、成長し続ける力が求められています。しかし、実際には自身のキャリアを明確に描けていない若手社員も多く、モチベーションの低下や離職率の上昇といった課題に直面する企業も少なくありません。
特に、VUCAや低成長時代において、20代・30代のビジネスパーソンが長期的なキャリアを設計することは、経験的にも知識的にも容易ではなく、不安を感じることもあります。そのため、キャリアの必要性を認識しながらも、将来の展望を明確に持てず、漠然とした不安を抱えることが精神的な負担や生産性の低下につながるケースもあります。
こうした状況の中、企業が若手社員のキャリア意識を育てることは重要です。キャリア研修を通じて、社員が自身の強みを理解し、将来のビジョンを描くことで、個々の成長だけでなく企業全体の発展にもつながります。
本記事では、若手社員のキャリアデザインの重要性と、企業がどのような施策を講じるべきかについて解説します。
キャリアとは
キャリアという言葉は、一般的には「仕事」や「経歴」「就職」「出世」といったイメージで語られることが多いですが、厚生労働省では「時間的な持続性や継続性を持つ概念」として定義されています。
かつての日本では、一つの会社で定年まで勤め上げる終身雇用が当たり前とされていましたが、そうした時代はすでに過去のものとなりました。転職が一般的な選択肢として浸透してきたのは、ここ10年ほどのことです。
「ゆりかごから墓場まで」という言葉で象徴される日本の雇用慣行は、もともと第二次世界大戦後のイギリスの福祉政策を参考にしたものでした。しかし現在は、働き方そのものが欧米型へと移行しつつあり、転職の増加は避けられない時代の流れとなっています。こうした環境の中では、ただ一つの会社に長く勤めることだけではなく、自分自身でキャリアを考え、主体的に設計していく力がますます求められています。
とはいえ、「不確実な時代」と言われる現代において、個人が設計したキャリアや人生のプランが必ずしも計画通りに進むとは限りません。そもそも、人生を設計主義的に考えることは可能なのでしょうか。
キャリアとは、単に職業を選ぶことではなく、自分の価値観やスキル、ライフプランを踏まえた人生全体の設計を指します。しかし、スキルや価値観は、事業環境やライフステージの変化によって常に変わり続けるものです。そのため、柔軟に軸を持ちながらキャリアを考えることが重要になります。
以下では、キャリアの基本的な考え方や、どのような視点でキャリアを築くべきかについて詳しく解説します。
参考:厚生労働省『キャリア形成を支援する労働市場政策研究会』報告書
若手社員がキャリアへの考えを必要としている理由
若手社員は、これから約40年にわたる職業人生を見据え、自らのキャリアを設計する必要があります。特に、現代の企業環境は急速に変化しており、一つの仕事を続けるだけでは生き残れない時代となっています。
そのため、キャリア形成は単に安定を目指すものではなく、市場や社会の動向を意識しながら自己成長を続ける「サバイバル戦略」としての側面を持つようになっています。
日本国内だけを見ても、経済成長の停滞が続き、30年間にわたる衰退が指摘されています。この状況を踏まえると、これまでのように一つの企業に属し、社内のキャリアパスを順調に進めるだけでは、必ずしも安定した職業人生が保証されるわけではありません。一方で、広い市場を視野に入れたキャリア設計は、安定性こそ減るものの、可能性を大きく広げることができます。
重要なのは、戦い方の変化を理解し、適応することです。キャリア形成において、これまでの「組織内キャリア」だけに依存するのではなく、広い視野を持ち、柔軟に自分の市場価値を高めることが、これからの時代において求められるスタンスと言えるでしょう。
ここからは、若手社員がキャリアへの意識を高める必要性と、新しい時代に求められる考え方について詳しく解説します。
労働力不足と変化する社会への対応
現代のグローバル社会では、企業の業績や経済全体に大きな影響を与える社会情勢の変化に柔軟に対応する力が求められます。日本では少子高齢化により労働力不足が懸念される一方で、雇用の機会自体は依然として存在しています。若手社員にとって「キャリア」は単なる仕事の選択肢ではなく、自分に適した仕事を見つけ、成長し続けるための戦略となります。このような環境下で、自分自身の価値やスキルを磨き、競争力を高めることが重要です。
日本の労働力不足は今に始まったことではなく、健康なシニア層も活躍できる環境が整っています。産業の中心も肉体労働から精神労働へ移行しており、加齢による影響は以前ほど問題視されなくなっています。
一方で、技術やスキルの賞味期限が短くなり、最先端を追うだけでは競争力を維持できません。そこで重要なのは「希少性」を高めることです。専門性を1つに絞らず、2つ、3つと組み合わせることで他にはない価値を生み出し、市場での競争力を高めることができます。 今後は、多様なスキルを柔軟に活かし、自らのキャリアを設計する力が求められる時代となるでしょう。
日本型雇用慣行の変化
年功序列や終身雇用といった日本型の雇用慣行は、すでに崩壊しつつあります。かつては、若い頃の低賃金が50代以降に補填され、退職金でバランスを取る長期的な仕組みが成り立っていました。しかし、ビジネス環境の急激な変化により、一つの業界や職場で30年間安定して働くモデルは時代遅れとなりつつあります。これに伴い、人事制度も成果主義や短期的な賃金体系へと移行しています。日本企業の経営能力を批判するのは簡単ですが、実際にはそれほど単純な話ではありません。1990年代以降、多くの日本企業が急速な変化に対応するため、人事部門を中心にさまざまな改革や調整を進めてきたという事実も見逃せません。
若手社員がキャリア形成に積極的に取り組むことは、こうした変化に適応しながら離職を防ぎつつ、企業の成長にも貢献する重要な要素となっています。
若年層の仕事に対する考え方の変化
近年、新卒市場では求人数が求職者数を大きく上回り、若年層にとって多くの選択肢がある状況が続いています。さらに、転職に関する情報が容易に得られるようになったことで、若年層の間で離職に対する抵抗感が薄れ、「第二新卒」という概念が一般化しました。これにより、キャリアの考え方も変化し、従来の「安定志向」ではなく、より市場価値を高める方向へとシフトしています。
現在の20代・30代は、縮小均衡が続く日本経済の世界しか知りません。単純な競争社会のレッドオーシャンで戦うよりも、希少性や模倣困難性を追求することが生存戦略として必然となっています。個人は社会や企業・経済の中で弱い存在だからこそ他者と差別化し、自らの価値を高めることが求められる時代になっているのです
情報が多すぎてキャリア設計が困難
現代社会では、AIや最先端技術、ESGなどの新しいトレンドが次々と登場し、キャリア設計が複雑化しています。情報過多の中で、どの方向に進むべきかを判断するのは容易ではありません。確実性が求められる一方で、未来は不確実な要素に満ちています。
技術や事業の進化は加速し、個人の能力開発のスピードがそれに完全に追いつくことは困難です。さらに、情報過多の時代において選択肢が多すぎることで、本質を見抜くことが難しくなっています。
特に、技術やスキルの賞味期限が短くなり、一つの専門分野に固執するだけでは持続的な競争力を維持できません。そのため、単にスキルアップを目指すのではなく、希少性や模倣困難性を意識したキャリア形成が不可欠です。
個人が市場の変化に適応するためには、複数のスキルを組み合わせ、自身の独自性を高めることが求められます。選択肢が多い中で本質を見極め、自らの価値を最大化することが、これからの時代を生き抜く鍵となるでしょう。そのため、長期的なキャリア計画よりも、短期的で実践的な行動を重視し、自身の価値を高めることが重要になっています。
若手社員のぼんやりとした不安
AIや新しい技術に従事する若手社員であっても、将来のキャリアに対して漠然とした不安を抱える人は少なくありません。技術が伸び続ける可能性がある一方で、競争も激化しており、自分のキャリアがどうなるのか予測がつかない状況が続いています。こうした環境下で、若手社員が30年以上の職業人生を見据えて行動する必要があるため、不安は避けられない現実となっています。
AIが日本企業に浸透すれば、まず新卒者の仕事が減少します。雑務や定型業務といった新卒に求められる業務は機械化され、必然的に新入社員の役割も変化するでしょう。この変化に対する漠然とした不安は自然なことです。
将来を見通すのが難しい時代だからこそ、長期的な視点ではなく、10年単位で区切って考えるのも有効です。20代、30代、40代と段階的にキャリアを捉え、社会や経済の変化をその都度見極めながら適応することが重要です。
AI時代を生き抜くには、短期間で市場価値を高めるスキルと希少性を意識したキャリア設計が不可欠になります。
やりたいことを仕事にしたい
多くの若手社員は、「食べるために働く」という考えを超え、好きなことや得意なことを生かした仕事を求めています。ユニークなスキルや興味に基づくキャリア形成は、自己実現の一環として重要視されています。
しかし、単に「好きだから」という理由だけで仕事を成立させるのは難しく、例えば映画鑑賞を続けているだけでは収入にはつながりません。ここで大切なのは、「好きなこと」「できること」に加えて、「社会に求められていること」とのバランスを取ることです。
市場価値を意識しながら、自分のスキルを活かせる分野を見極めることで、好きなことを仕事にする道も開けます。自己満足だけでなく、社会での需要を考えたキャリア設計が不可欠です
長期的キャリアに必要なのは「腕」と「コネ」
一つの職種で専門家になるためには、通常3~5年の経験が必要ですが、単一のスキルだけでは競争力を維持するのが難しくなっています。そこで重要なのが「かけ算」の考え方です。トップレベルに到達しなくても、専門的な知識を持つ分野を3つ以上持てば、それらの組み合わせによって希少性が生まれ、自分にしかできない領域が見えてきます。
たとえば、データ分析のスキルに加えて、UXデザインの知識があり、さらにプロジェクトマネジメント経験を持っている人は、それだけで市場価値が高まります。さらに、これをプログラミングの知識と組み合わせることで、データに基づいたユーザー体験の改善を主導できる専門家としての希少性が増します。今の仕事に関連するスキルを追加することがポイントです。
そこに外国語、特に英語を加えるだけで、さらに希少性が高まります。英語は応用範囲が広く、習得方法も確立されているため、グローバルなビジネスパーソンとしての競争力を強化する有力なスキルの一つになります。
また、「コネ」という言葉は、日本では単なる人間関係や友人関係と混同されがちですが、ビジネスの世界において重要なのは「一緒に仕事をした経験のある関係」です。単に知り合いであることや、価値観が近いことではなく、実際に成果を共に生み出した経験があるかどうかが、本当の「コネ」になります。
ビジネスの場では、旅行に行ける友達や気の合う仲間も大切ですが、それ以上に重要なのは「組める相手」の存在です。過去に一緒に仕事をし、互いの強みを理解し合い、信頼関係を築けた相手こそが、キャリアを支える最大の財産となります。
極端に言えば、社会に出た後に必要なのは、こうした「実績のあるビジネスパートナー」であり、単なる友達ではありません。共に仕事をし、結果を出した経験のある相手こそが、キャリアを切り拓く上での本当の「コネ」となるのです。
社員は会社や職場を自分で選択する時代
現代では、社員が自分で働く場所や環境を選ぶ時代となっています。企業は生産性を高めるために優秀な人材を求める一方で、社員は自分のキャリアや成長を見据えて職場を選ぶ傾向が強まっています。こうした中で、転職がより簡単になり、若手社員が企業を再選択する「出戻り」も一般化しています。この変化に伴い、企業は単なる雇用主ではなく、社員にとって「場」としての価値を提供する必要があります。
会社は出会いの場である
かつての日本企業では、社員を家族のように捉え、終身雇用を前提とした曖昧な関係性が特徴的でした。しかし現代では、企業は社員にとって「出会いの場」としての役割を担うようになっています。
企業での経験や成果を通じて築かれる人間関係は、ビジネスにおける信頼や大切な資産として重視されるようになりました。共通の目的に向かって成果を上げた経験は、やがて「コネクション」としての人脈となり、長期的なキャリアを築くうえでの基盤となっていきます。
キャリアデザインは不可能に近い
成長しない企業に所属することは、個人としての成長機会が限られてしまうことを意味します。特に日本では、継続的に成長している企業を見つけること自体が難しくなってきています。
成長の可能性が高い企業で働くには、激しい競争を勝ち抜かなければなりません。仮にそうした企業に入社できたとしても、成長意欲の高い仲間たちと切磋琢磨する中で、さらに努力を重ねることが求められます。
一方で、成長しない企業にとどまっていれば安定が得られるという時代でもありません。むしろ、自分自身の市場価値を高め、より良い選択肢を得るためには、リスクを取って挑戦する姿勢が求められています。
年齢別の若手社員の状況
若手社員の状況は年齢によって異なり、それぞれのキャリアステージに応じた課題や取り組みが必要です。以下では、20代と30代に焦点を当て、それぞれの特徴と重要なポイントを解説します。
20代
20代のキャリア形成は、将来の選択肢を増やすための基盤を作る時期です。この時期は「死ぬほど働け」と言われることもあるほど、スキルを磨き、できることを増やすことが重要視されます。特に、社内外で自分の名前で仕事を依頼されるようになる「バイネーム案件」を増やすことがキャリアアップの鍵となります。また、学び方を学ぶ姿勢を持つことが、将来のキャリア選択に大きな影響を与えます。
30代
30代はキャリアの転換点となる時期です。この時期には多くの社員が転職を検討し始めます。特に入社後7~10年目で、ある程度自走的に仕事をこなせるようになった社員は「賃金が低い」「やりがいがない」といった不満を感じやすくなります。
成長が停滞している企業では昇給や昇格の機会が限られ、不満が離職につながることも少なくありません。一方で、昇進や新しい役割を得ることで、この時期の不満を解消することができます。
成長しない大企業から若手は離職するのか?
成長しない大企業から若手社員が離職する理由は、業務の固定化や成長機会の欠如が大きな要因です。一方で、ベンチャー企業は裁量や挑戦の場を提供するものの、安定性に欠けるというリスクがあります。 そのため、若手社員が離職するかどうかは「成長」と「安定」のどちらを優先するかに左右されます。
最近では、タレントマネジメントや研修制度の充実により、社内でのキャリア形成を模索する若手も増えており、大企業も人材流出を防ぐための取り組みを強化しています。
若手社員向けキャリア研修に効果的なフレームワーク
若手社員向けのキャリア研修には、「Will」「Can」「Must」という3つのフレームワークが効果的です。
Will(意志): 自分が実現したいことを考える。
Can(能力): 自分の強みやできることを整理する。
Must(責任): 周囲や会社から求められることを明確にする。
このフレームワークを活用することで、社員は自分の強み(Can)を活かしながら、会社や周囲から求められること(Must)を満たし、最終的には自分の目指す方向性(Will)を実現するための行動計画を明確化することができます。これにより、若手社員のキャリア形成を支援し、企業全体の成長にもつながります。
若手社員向けキャリア研修を設計するときのポイント
若手社員向けキャリア研修を効果的に設計するには、会社の方針だけでなく、社員一人ひとりの目標や希望に配慮する必要があります。ここでは、若手社員が主体的にキャリア形成を進められるよう、研修設計時に考慮すべきポイントを解説します。
全体像の「見える化」を行う
若手社員が自身のキャリアを具体的に描くためには、会社内でのキャリアパスや業務の全体像を把握できることが重要です。研修では、会社でどのように成長していけばよいのか、何に取り組むべきかを明示するキャリアアップモデルや事例を提示することが効果的です。これにより、社員は自身の役割や進むべき方向性を理解しやすくなり、成長意欲を高めることができます。
若手社員主体のプログラムを作成する
研修プログラムは、若手社員自身が主体的にキャリアを振り返り、将来像をイメージできる内容で構成することが大切です。会社側の理想や期待を押し付けるような形式は、社員の反感やモチベーション低下を招く恐れがあります。個々の目標や意欲に寄り添いながら、社員自身が主体的に参加できるプログラムを設計することが重要です。
研修後のフォローが重要
研修は一度きりで終わるものではなく、その後のフォローアップが社員のキャリア形成に大きな影響を与えます。社員が将来の目標を達成するために必要なスキルや経験を考えられるよう、研修後も相談できる体制を整えることが重要です。
たとえば、キャリア相談担当者を設けたり、定期的な面談を実施したりすることで社員が継続的にキャリアについて考えられる仕組みを提供できます。
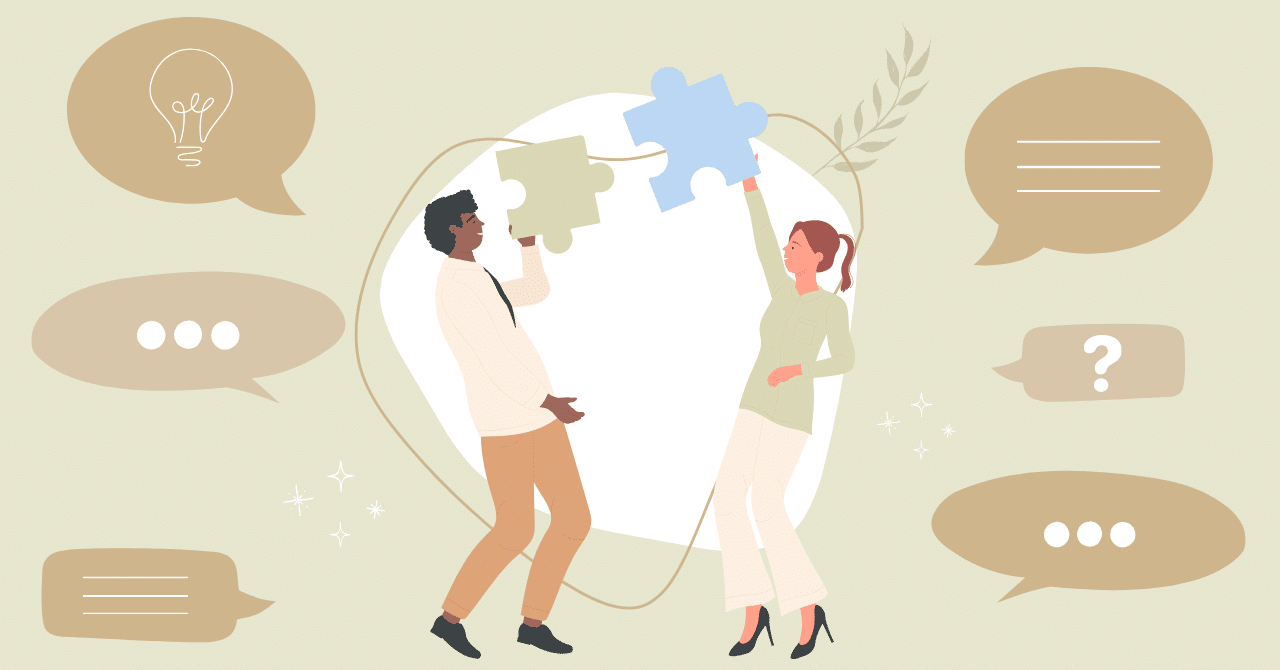
1on1(ワンオンワン)とは?目的やメリット、部下の成長を促すテクニックや話題例を紹介
最近は米国シリコンバレー由来の「1on1(ワンオンワン)」という新たなミーティングの手法がトレンドになっています…
柔軟な人事異動制度を取り入れる
若手社員が理想のキャリアを実現するには、柔軟な人事異動制度が欠かせません。特定の部署に縛られることなく、多様な経験を積める環境を整えることで、社員の成長と満足度を高め、離職防止にもつながります。会社としても、異動を通じて社員が新たなスキルや視点を得ることで組織全体のパフォーマンス向上が期待できます。
まとめ
若手社員向けキャリア研修を成功させるためには、研修内容の設計から実施後のフォローまで丁寧な計画と対応が必要です。全体像を明確化し、社員主体のプログラムを構築することで、社員の意欲を高めることができます。
また、研修後の継続的なフォローや柔軟な人事異動制度を取り入れることで、若手社員のキャリア形成を全面的に支援できる体制が整います。このような取り組みは、若手社員の離職防止や企業全体の成長に貢献する重要な施策となるでしょう。

株式会社ソフィア
先生
ソフィアさん
人と組織にかかわる「問題」「要因」「課題」「解決策」「バズワード」「経営テーマ」など多岐にわたる「事象」をインターナルコミュニケーションの視点から解釈し伝えてます。
株式会社ソフィア
先生

ソフィアさん
人と組織にかかわる「問題」「要因」「課題」「解決策」「バズワード」「経営テーマ」など多岐にわたる「事象」をインターナルコミュニケーションの視点から解釈し伝えてます。