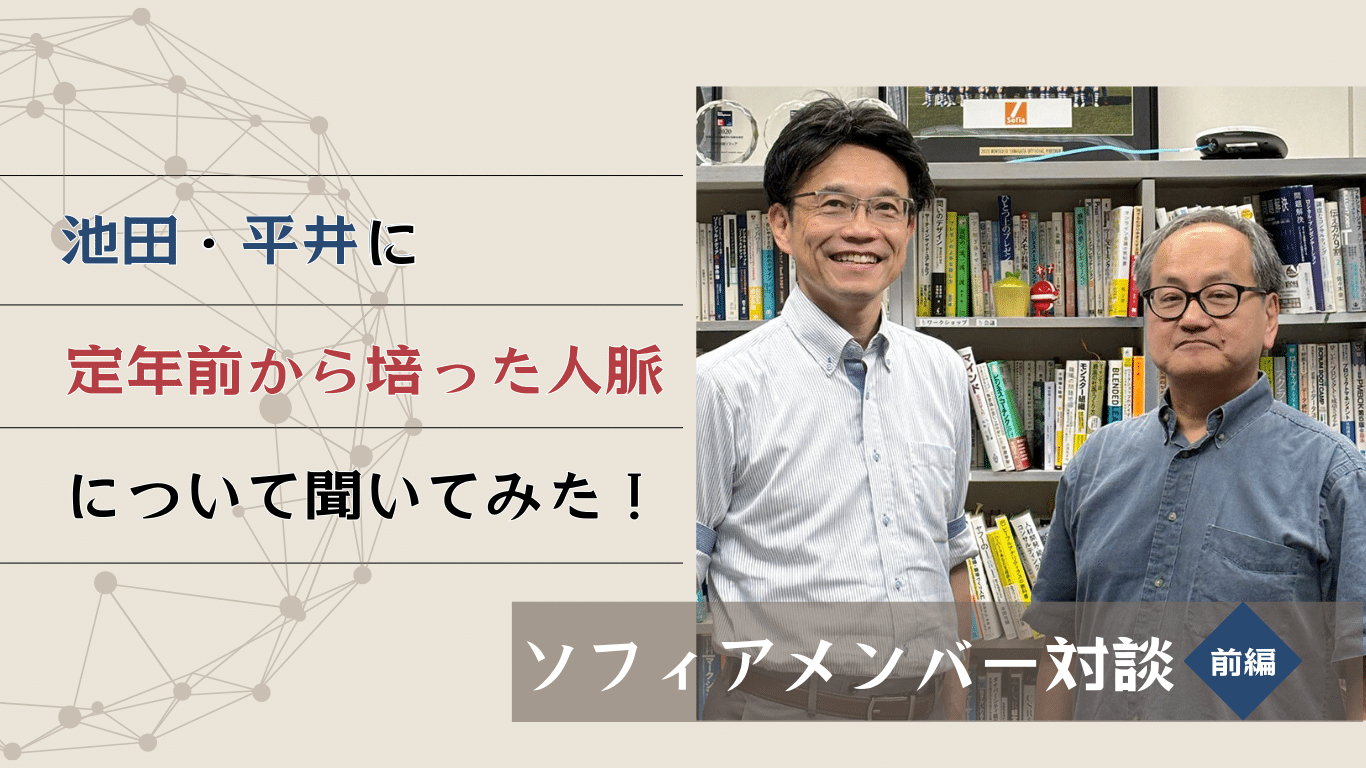組織開発とは?人材開発との違いやその手法をご紹介
最終更新日:2025.10.28

目次
社会の変化が激しい現代、企業が生き残るためには組織力の強化が欠かせません。しかし、ただ社員のスキルを高めるだけでは不十分です。社員同士の関係性や組織風土を変革する「組織開発」に、今あらためて注目が集まっています。組織開発とは何か?どのように実践すれば効果が出るのでしょうか。本記事では、人材開発との違いや組織開発の代表的な手法、実践のメリットなどを、人事部門長や現場マネージャーの皆様にわかりやすく解説します。
組織開発とは何か?
「組織開発」とは、その名の通り組織に対して働きかける取り組みです。企業でいえば社員同士の関係性を改善し、組織全体の活性化を図ることを目的としています。よく似た言葉に人材開発がありますが、こちらは個々の社員のスキルや知識を向上させることで人材を育成する取り組みです。組織開発は人ではなく組織そのものや、その中の人間関係・風土にアプローチする点が人材開発との大きな違いです。
もちろん、個人の能力開発と組織環境の開発はどちらが欠けても十分な効果は得られません。組織のパフォーマンスは、個々人の特性(能力や意欲)とその人を取り巻く職場環境(人間関係や文化)の相互作用によって決まります。したがって個人のスキルアップ(人材開発)と職場の関係性改善(組織開発)は車の両輪であり、両方をバランス良く進めていく必要があります。
人材開発との違い
改めて人材開発と組織開発の違いを整理してみましょう。人材開発が対象とするのは個々の従業員であり、研修やOJT、eラーニング、コーチングなどを通じて個人の能力やキャリアを伸ばすことを目指します。一方、組織開発が対象とするのは組織全体やチームであり、組織風土や構造、コミュニケーションの状態などをより良い形に変えることを目指します。前者が「人を育てて組織力を高める」アプローチだとすれば、後者は「環境を整えて人と組織を双方に成長させる」アプローチと言えるでしょう。
具体的には、人材開発では社員一人ひとりのスキルアップや意識改革にフォーカスします。それに対し組織開発では、部署間の連携や風通しの良さ、リーダーシップの発揮しやすい文化づくりなど、人と人との関係性や組織全体の仕組みに働きかけます。どちらも最終的な目的は「組織パフォーマンスの向上」ですが、そのアプローチの視点が個人単位か組織単位かで異なっているのです。

伝統的に日本企業は人材開発には力を入れても組織開発はないがしろにする傾向がありました。そこには、個々のスキルを高めておけば、組織は自然に良くなって行くという暗黙の了解があったと思われます。しかし、組織に手を付けずに人財だけを、伸ばそうと思っても、限界があります。
人財ならば、単位は個々の社員ですから、一人一人がやる気を出し、変化を恐れず、挑戦をし続けるなら、個人のスキル向上という目標を達成することはそう難しい事ではありません。
一方で組織は、一人や二人が変わっただけでは、動いてくれません。これまでの伝統、習慣、しきたりが、強固な見えない力となって、組織の変化を邪魔してきたりするものです。個々の社員の意識を変えることは比較的簡単でも、職場の風土を変えることは至難の業です。この困難な作業にどう立ち向かうか?が本記事の目的です。
組織を開発するとは、何を開発する事なのか?
では、開発の対象となる「組織」とは、一体なんなのでしょうか?多くの人が長時間を過ごす業務遂行の場であると同時に、従業員同士の人間関係が築かれる社会的空間が組織であり、直観的に認識できるのは職場です。そこには、成果や効率を追求する機能的・合理的側面と、感情や人間関係が絡む情愛的・精神的側面の二面性が共存しています。
ドイツの社会学者テンニースは、人間集団を情愛的なつながりによる「ゲマインシャフト(共同社会)」と、目的や利益で結ばれた「ゲゼルシャフト(利益社会)」に分類しました。家族や友人、創業期のベンチャーのような精神的な結びつきが前者、国家機関や企業の部署などの合理的集団が後者に該当します。同様の分類はクーリーやマッキーバーらも提唱しており、社会学における基本的枠組みです。職場は一見ゲゼルシャフト的ですが、日常的な対面と濃密な人間関係が形成される点でゲマインシャフト的性質も併せ持っています。すなわち、職場は機能性と情愛性が共存する複合的集団なのです。職場は生産性向上の場である一方、人間関係による悩みや葛藤の種ともなり得ます。そこで、職場の二面性とそれを均衡させるコミュニケーションの重要性を考察します。
ただし、きれいに完全に二分類される組織は実際にはなく、わかりやすく整理するための枠組みとして考えてください。重要なことは、職場はこの両側面が絡み合って存在しているという事です。
私たちは経済合理性において、「ゲマインシャフト(共同社会)」を劣位に置き、目的や利益で結ばれた「ゲゼルシャフト(利益社会)」を優位におくことによって、失敗することが多いです。
ある上場企業を例に挙げましょう。その企業は、売り上げも利上げも着実に伸ばしている、外から見れば問題のない企業に見えました。しかし、社内では、利益追求のために法律すれすれの事が頻繁に行われており、道徳的に悪いとされる行為が社内の高評価に変化し、非道徳な行為を良しとする風潮さえありました。ここではゲゼルシャフトではあっても、ゲマインシャフトの側面が軽んじられ、人材が繋がりあう仲間ではなく、利益を上げるための寄せ集めになってしまっていました。当然、離職者は増え、違法すれすれの業務に対して内部告発者も現れます。このような利益だけを追求するゲゼルシャフトでは、その組織は早晩立ち行かなくなるでしょう。
職場の二面性とコミュニケーション
職場は少人数で構成され、日々顔を合わせて協働する対面集団です。そのため合理的な業務目標で結ばれた組織(ゲゼルシャフト)でありながら、家族的な情愛で結びつく共同体(ゲマインシャフト)的な性格も併せ持っています。この複合的性質ゆえに、職場では表向きの合理性と内心の感情のギャップから摩擦や誤解が生じやすくなります。困難に直面した際には、公式な役割を超えて仲間同士で助け合う場面も見られ、合理性だけでは解決できない問題があることを示しています。したがって日々のコミュニケーションによって機能面と情愛面のバランスを取ることが不可欠です。
職場の単位が大きくなり、関わりあう人数が100名を超えてくると、どうしても利益中心のゲゼルシャフトになりがちです。一方で、数人単位で仕事をしている職場なら、ゲマインシャフトの雰囲気が優勢となるでしょう。とはいえ、大きな単位の職場でも、日々の会話や声掛け、緊密なコミュニケーションというゲマインシャフトは必要であり、少人数の職場でも、企業であるからにはゲゼルシャフトを重視するときはもちろん出てきます。大事なことはどんな組織にもゲゼルシャフトとゲマインシャフトの二面性があり、そのバランスに上に成り立っていることを忘れないことです。
人間関係とエンゲージメント
職場で合理性と感情のバランスが崩れると、表面上の従順さと内心の不満が募ってコミュニケーション不全に陥り、メンタル不調や離職といった問題が生じます。これらは一見業務上の問題に見えても、その背景には人間関係のもつれが潜んでいます。
経営陣は企業理念やビジョンを浸透させる努力も必要ですが、最後の決め手となるのは職場内の人間関係です。社員が離職を思い留まる理由として「尊敬できる上司がいる」「信頼できる同僚と働いている」など身近な人への情緒的な結びつきがよく挙げられます。人は会社そのものよりも、そうした絆によって職場に留まる傾向があるのです。良きリーダーが小さな成功体験やチームの物語を共有してメンバーの心を動かすことで、「この職場に貢献したい」「この上司について行きたい」という意欲が引き出されます。逆に温かみや物語のない職場では、社員のエンゲージメント(仕事への熱意)は生まれにくいでしょう。
実際、米ギャラップ社の調査では2024年時点で世界全体の従業員エンゲージメント率が21%に低下しており、熱意欠如による生産性ロスが指摘されています。しかし裏を返せば、職場内の良好な人間関係や共有されたビジョンで社員の心に火を付け、本当の意味でエンゲージした状態に導くことができれば、組織全体の活力向上につながるのです。
ここで、重要になってくるのがリーダーシップです。且つて、ローマ帝国のカエサルは、戦場のあらゆる場所で、即興の演説を行い、その演説によって下級兵士の心を奮い立たせ、この司令官のためなら、死んでもいいと思わせました。組織開発のためには、よきリーダシップが欠かせません。そのテーマを次のパートで深堀してみましょう。
柔軟なリーダーシップと多様性の活用
現代の職場はテレワークの普及やダイバーシティ推進、人材流動化など急速な変化にさらされ、機能面と情愛面のバランス維持が一層難しくなっています。それでも相互理解を深めるコミュニケーションを軸に、生産性向上と良好な人間関係の両立を図ることが重要です。
業務プロセスや役割分担を見直してタスクを分担し、各人に裁量を与えることで効率と自主性を高めます。一方で、メンバー同士が互いを理解し、困ったときに支え合える関係を築くことも欠かせません。そのためリーダーは意識的に絆を深める機会を設け、チームに信頼関係を醸成する必要があります。
またリーダー役を固定せず、得意なメンバーが主導する柔軟さを持たせることも有効です。多様な人材に活躍の場を与えればチームは活性化し、多様性の高いチームは新市場を開拓する可能性が高まるとの調査結果もあります。
関係性や空気を開発する組織開発
職場は単なる物理的な作業場ではなく、人と人との関係性が紡がれる場です。高い成果を持続的に生み出すには、業務プロセスなど見える部分の整備と同時に、信頼関係や雰囲気といった見えない部分をおろそかにしないことが肝心です。結局のところ、職場を開発するということは、関係性や空気という目に見えないものを開発することに他なりません。そうした見えない要素を大切に育む職場こそが、社員の熱意を高め組織の活力を持続させる原動力となるのです。
では、その目に見えない信頼関係や雰囲気というものは、どうやって創り出すべきでしょうか?単に、上司が目標やノルマを一方的に話すだけでは、信頼も忠誠心も生まれません。そこに「感動」があってこそ、社員は職場の場所に愛着を持ち、そこで時間を費やしていこうと決意するものです。
感動のない職場は面白みのない職場です。いくら大企業でも、優秀な人材は耐えられなくなるでしょう。いつも新鮮な感動がある職場なら、収入に関係なく次もやってみよう、もっと儲けられる職場にしようと思うはずです。カエサルの言葉に下級兵士が「感動」したからこそ、彼らは命がけで戦ったのです。「感動」こそ、組織をつなぐ絆です。

関係性の可視化が重要な理由
では、職場で社員同士の関係性を深めると、企業にはどのような良い影響がもたらされるのでしょうか。まず、社員のエンゲージメント(参画意識)やモチベーションが高まります。これは業務の生産性向上や効率化、離職率の低下、さらには企業ブランドの向上につながります。
また、職場の人間関係が良好になると部署や職位を超えた協力体制が生まれ、社員同士のシナジー(相乗効果)が発揮されます。現場からイノベーティブなアイデアが創出されたり、チーム間の協働がスムーズになるといったメリットも期待できるでしょう。
しかしここで注意しなければならないのは、「関係性」は目に見える部分だけではないということです。社員の行動や会話など表面に現れるものは氷山の一角にすぎません。その水面下には、その組織特有の風土や暗黙のルール、忖度(遠慮)、普段は見えにくい感情や人間関係の網の目が存在しています。言語化・可視化されていないこれら「水面下の関係性」も、実は社員の働きぶりや組織全体の成果に大きな影響を与えているのです。
だからこそ、組織開発ではこの見えない関係性をあえて可視化し、共有していくプロセスが重要視されます。普段は意識されない本音の思いや人間関係の状態を明白に共有する中で、組織の変革や新たなイノベーションの種が生まれてきます。言い換えれば、関係性の可視化こそが組織変革を進める原動力となるのです。
組織開発の理論的背景と特徴
組織開発が生まれた背景には、20世紀中頃の米国における行動科学とシステム理論の発展があります。クルト・レヴィンはグループダイナミクス(集団力学)やアクションリサーチ(行動科学的な調査と実践循環)の考え方を提唱し、これらは現在の組織開発の基本プロセスを支える概念となりました。レヴィンは第二次大戦中に、コンサルタント(第三者)とクライアント(組織メンバー)が協働して計画・実行・結果測定を行う参加型の変革手法を試行し、これが後に組織開発の中核となるアクションリサーチ循環(現状診断→行動介入→効果検証→次の行動へ反映)につながっています。
また、1950年代にはダグラス・マグレガーとリチャード・ベックハードが企業の現場で従来のコンサル手法に当てはまらない新しい組織変革の試みを行い、これを「オーガニゼーショナル・デベロップメント(組織開発)」と名付けたと言われます。当時の経営学者たちは、組織文化が人々の行動に与える影響や、職場での人間関係の重要性に着目し始めており、そうした組織行動科学の発展が組織開発という概念を生み出したのです。
組織開発の理論面でもう一つ重要なのがシステム理論(System Theory)です。組織をひとつの「開かれたシステム」と捉え、組織を構成する部署・チーム・個人といった要素が相互に関連し合い、外部環境とも影響を及ぼし合うという視点です。システム理論の観点では、組織は部分の集合以上の全体性(ホールネス)を持ち、ある部門での意思決定や行動は他の部門や組織全体に波及効果をもたらします。たとえば営業部門の施策の変化は、製造部門やサポート部門にも影響を及ぼし、組織全体の成果に跳ね返ってくるという具合です。そのため、組織開発では部分最適ではなく全体最適の発想が重要でもあり、組織を相互依存のネットワークとして捉えて変革をデザインします。
ある部門で、改善が行われるとき、その影響が必ず会社全体に広がっていきます。この意味で会社は生き物だと言っても過言ではありません。ちょうど、胃の病気を治すときに、糖尿病や高血圧の診断を最初にするように、全体を見る視点がないと部分だけの改善では、効果的とは言えません。絶えずに自分の部署だけではなく、会社全体や、できれば業種業界全体の動向をいつもここに止めておくべきです。
さらに、組織開発は単なる手法の集合ではなく、「価値観」や「原則」に裏打ちされた実践である点も特徴です。たとえば、北米の組織開発ネットワーク(OD Network)のメンバーによる定義では、「ODは組織パフォーマンスと個人の成長を高める知識と実践の体系であり、組織を複雑なシステムの集合(しかもより大きなシステムの中に存在する)と見なしながら、戦略策定、組織設計、リーダーシップ開発、変革管理、業績管理、コーチング、ダイバーシティ&ワークライフバランスなど包括的な手法を含むもの」だと説明されています。また同時に、「人間システム(個人・グループ・組織・社会)に介入しその健康と有効性を高めることを目指す応用行動科学の一分野」であり、実践においては対話や参加、コラボレーションを重視し、倫理観と人間尊重の価値観を持って行われるべきとされています。要するに、組織開発は心理学や社会学などの科学的知見に裏付けられつつも、人間性や多様性を尊重するバリューを大切にしたアプローチなのです。
このセクションでは組織開発を支える理論と考え方について見てきました。行動科学の祖クルト・レヴィンのグループダイナミクスやアクションリサーチの発想は、組織開発の「計画的な変革→効果検証→更なる変革」という循環型プロセスの原型となりました。また、システム理論の視点から組織を全体として捉え、部分ではなく全体の最適化を図るのが組織開発のアプローチです。組織開発は単なるノウハウではなく、科学的知見と人間的価値観の双方に支えられた包括的な実践哲学と言えるでしょう。これにより、組織開発は戦略・構造から人材・文化に至るまで幅広いテーマを扱い、最終的には組織全体の健全な成長と人々のエンパワーメントを目指すものとなっています。
組織開発が注目される理由:見えない関係性と組織の健康
前章でふれたように、組織は生き物であり、部分と全体の微妙なバランスの上に成り立っているものです。人生の節目で健康診断を受け、自分の体の状態をチェックするように、組織にとっても、健康状態のチェックは必ず必要です。
たとえば、改善すべき点があるのにそれを「言い出せない」。うまくいくかもしれないアイディアが浮かんだが「切り出せない」。このような職場が良い組織であるはずはありません。血管の中が詰まっていたり、消化器官がうまく消化できなかったりするとき、体はそれを不調と訴えてきます。
同じように、風通しがよい自由闊達に意見が言える職場を創っておかないと、いつか業績は低下していきます。自分の体をケアするのと同じ注意深さで、組織の健康についても気を配るべきです。特に経営者側の立場であるなら尚のこと、組織の健康を意識しおきましょう。
また、日々の会議・ディスカッションでの背景や関係性にも注目する必要があります。話されている言葉だけではなく、社員の顔色や会議の空気など、ほぼ感覚的に感じられる部分の方に重要な改善点が隠れていることが多いのです。
この感覚的な、もしくは直観的な違和感に対して、タイミングをずらさずに違和感を言語化し、その場に提出することは、組織の健康を維持する上で必要なフィードバックになります。「目に見える活動や出来事」である業務上の発言やコミュニケーションと集団を構成する人々の「感情」や「相互作用」などの信頼関係や人間関係といった見えない部分の両面に気を配るという事になります。
組織開発のアプローチ:診断型と対話型
それでは、組織開発にはどのようなアプローチがあるのでしょうか。大きく分けて「診断型組織開発」と「対話型組織開発」という2つの手法が知られています。
診断型組織開発(Diagnostic OD)では、医師が患者を診断するように組織外部の専門家(組織開発コンサルタント等)が調査と分析を行い、課題と解決策を導くのが特徴です。アンケートやインタビュー、行動観察などで客観的なデータを収集し、「望ましい組織像」に照らして現在の問題点を洗い出します。多くの場合、外部の専門家の知見を借りながら、組織構造や文化、人事制度、コミュニケーション状況などを総合的に分析し、組織改革プランを提示します。定量データに基づく客観分析や、組織内の力関係にとらわれない中立的な視点が得られる点がメリットですが、その反面、分析結果が現場感覚と乖離した机上の空論になってしまうリスクもあります。また、トップダウン的なアプローチになりやすく、社員の納得感や主体性が生まれにくいという指摘もあります。
一方、対話型組織開発(Dialogic OD)は、調査や診断ありきの進め方にとらわれず、組織の当事者である社員自身が対話を重ねるプロセスによって現状を把握し、課題を顕在化・解決していこうとする手法です。ここで言う「対話」とは、単なる打ち合わせや討論ではなく本音で語り合う対話を指します。社員それぞれが持つ仕事上の背景や経験、価値観、感じていること、想いをお互いに伝え合い、相手の話を受け入れて理解することです。その上で「私たちの組織はどうありたいか?」という理想の姿を全員で模索し、「そのために今から何ができるか」を考えて自ら実践していきます。対話型は組織メンバーの主体性を引き出し内発的な変革を促す、極めて参加型・自律型のアプローチと言えるでしょう。
診断型が問題を細かく分析して原因を突き止めるロジカルシンキング(論理的思考)に基づくのに対し、対話型ではシステムシンキング(体系的思考・全体思考)が重視されます。システム思考とは、複雑に絡み合った状況の中で物事のつながりや因果関係、背景にある要因を俯瞰して捉え、表面的な現象にとどまらず根本的な問題にアプローチしようとする考え方です。市場環境の変化が激しく、「昨日の成功パターンが明日の成功を保証しない」現代においては、分析ありきで理想の組織像を描く診断型だけでは限界があります。自社にとってのベストプラクティスやイノベーションの種を現場の人間が主体的に創造していく対話型アプローチの重要性が増しているのです。
対話型組織開発の進め方(ステップ例)
では、対話型組織開発は具体的にどのように進めていけば良いのでしょうか。ここでは対話型アプローチによる組織開発の一般的な流れを5つのステップでご紹介します。
1. 現状の把握(As is)
まず組織の現状を明らかにします。アンケート調査やワークショップ、対話の場を設け、普段は表に出にくい社員の感情や相互作用(人間関係の動き)を引き出し、可視化していきます。この段階では、社員が胸襟を開いて本音を語れる心理的安全性の高い雰囲気づくりが重要です。たとえばAI(アプリシエイティブ・インクワイアリー)と呼ばれる対話型手法では、ペアインタビューでお互いの「(この職場で)これまでで最高の瞬間」を語り合い共有するワークを行います。ポジティブな体験を他者に語ってもらうこのプロセスを経ると、参加者全員が「自分が受け入れられている」という安心感を得ることができます。その結果、場の心理的安全性が高まり、現状について率直に語り合う土壌が整います。
2. 目標設定と課題の明確化(To be & Gap分析)
次に、理想とする将来の姿や組織のビジョンを全員で思い描き、目指すゴールを設定します。現状と理想のギャップを洗い出し、そこから解決すべき課題を明確にしていきます。ここで言う課題とは、「理想の状態に近づくのを妨げている要因」のことです。「現状は○○であり、本来あるべき姿との間に△△というギャップがある。その原因・障害となっているのは何か?」といった問いを立て、対話を通じて参加者自身が気付きを得られるよう、ファシリテーター(進行役)が促します。
3. 小規模からの施策実行
抽出された課題を解決するための具体的な施策プランが固まったら、まずは小さな範囲で試行してみます。いきなり全社一斉に展開しようとすると現場が追いつかず計画倒れになりがちなため、まずは部署内の1チームなどミニマムな単位で始め、徐々に実施範囲を広げていくのがポイントです。せっかく対話によって意識が変化し始めても、実行段階で元の状態に戻ってしまうケースも少なくありません。そうならないよう、施策の実行フェーズにおいても定期的に対話による振り返りやフォローアップを行い、組織開発の介入を継続していきます。
小さく始めることよって、リスクを抑えることができます。良いアイデアなのに、実行の仕方に問題があって、つぶれてしまう事もよくあります。
小さく始めて、うまくいけば徐々に広げていきましょう。うまく行かなった場合、アイデアそのものが失敗だったのか?実行の仕方が悪かっただけなのか?を、検証する必要があります。失敗してもアイデアに問題がなければ継続するべきです。そのためにも、最初のリスクはできるだけ小さく抑えておき、何回でもチャレンジできる土台を創りましょう。
4. 効果検証
施策を実行したら、必ず効果測定を行います。設定した目標に対してどの程度変化があったのか、定量的・定性的なデータを集めて検証しましょう。組織開発の取り組みは「やりっぱなし」にしてしまうと一時的な盛り上がりで終わってしまう恐れがあります。特に組織風土や関係性の変化は継続的にフォローしないと元に戻りやすいため、数値で見える成果と現場の声の両面からしっかりと評価することが大切です。
また、経営層への報告時には、具体的な数字や事例を示すことで理解と支持を得やすくなるでしょう。
5. 成功事例の共有・展開
組織開発の取り組みで得られた成功事例や良い変化は、社内報や社内SNS、朝会など様々な場を通じて組織全体に共有します。ポイントは、成果を社内に浸透させてノウハウを蓄積することです。うまくいった事例を全社員に共有すれば、「こんな風に現場が変わった」「対話を続ければ成果が出る」というポジティブな認識が広がります。それが社内のさらなる対話促進につながり、日常的に意見を言い合える風通しの良い組織風土が醸成されていきます。最終的には、特別なワークショップの場だけでなく日常のコミュニケーションの質そのものが変化し、組織全体の関係性が向上していくことが理想です。
対話型組織開発を支える主な手法
上記のような組織開発を進めるにあたり、現場で活用できる手法やプログラムも数多く存在します。ここでは対話型組織開発でよく用いられる代表的な手法をいくつかご紹介します。
アクション・ラーニング(Action Learning)
実際の業務課題に社員がチームで取り組み、そのプロセスで生じた実際の行動や結果を振り返ることで組織の関係性を学習・改善していく手法です。上下関係にとらわれない自由闊達な雰囲気の中で対話し合うことで、自発性の向上や課題解決力の強化につながります。
グループ・コーチング(組織開発文脈における)
マンツーマンの指導だけでなく、組織全体に経営層の理念やビジョンを浸透させることを目的としたコーチング手法です。対話を通じて社員の行動変容を促し、組織文化や価値観の共有を進めます。経営トップが描く理想の姿に向けて組織を変革したいときに有効です。
ワールド・カフェ(World Café)
カフェのようにリラックスした雰囲気で少人数のグループ対話を繰り返し行う対話手法です。4~6人程度のテーブルに分かれ、一定時間ごとに席替えをしながら課題やテーマについて語り合います。立場や部署を超えた多数の人々と同じ課題やテーマについて対話することで、多様なアイデアや相互理解が生まれます。参加人数が多い場合は専門のファシリテーターの支援を仰ぐと良いでしょう。
アプリシエイティブ・インクワイアリー(Appreciative Inquiry)
問題点ではなく成功経験や強みに焦点を当て、組織のポジティブな変化を引き出す対話手法です。人は課題を解決しようとするとき、つい「何ができていないか?」に目が向きがちですが、アプリシエイティブ・インクワイアリーでは「何がうまくいっているか?」からスタートします。参加者同士で過去の成功体験を共有し合い(Discover)、理想の未来像を描き(Dream)、それを実現するための計画を立て(Design)、みんなで実行に移す(Destiny)という4Dサイクルで進行します。組織の強みを活かし前向きに変革を進めるこのプロセスは、社員のモチベーションやエンゲージメントを高める効果が高いと言われています。
ここで挙げたもの以外にも、組織開発の手法は他にも数多く存在します。それぞれの組織課題や目的に応じて適切な手法を選定し、必要に応じて専門家の助言を得ながら進めると良いでしょう。重要なのは、どんな手法を用いるにせよ、「目的(何のために組織を変えたいのか)」をぶらさずに据えることと、「対話と行動」をバランス良く繰り返すことです。単なる話し合いで終わらせず行動につなげ、かつ行動して出た結果をまた対話で共有・学習する――このサイクルを回すことが組織開発成功のカギとなります。
只、「意見を述べなさい」だけでは、良い意見やアイデアが出たりはしません。言いにくい事であったり、恥ずかしい事であっても、それが本当に大事なことならば、言えるようにしていく場所創りが必要です。それが難しいのであれば外部のファシリテーターを利用するのも一手でしょう。
世界的に注目される組織開発
最後に、近年海外を中心に注目されている組織開発分野のトレンドをいくつか見てみましょう。ビジネス環境の変化や価値観の多様化に伴い、組織開発のアプローチも進化を続けています。特にここ数年で耳にすることが増えたキーワードとして、分散型リーダーシップ、DEI(Diversity(ダイバーシティ:多様性)Equity(エクイティ:公正性)Inclusion(インクルージョン:包含性)があります。
分散型リーダーシップ
従来のヒエラルキー型ではなく、組織内の複数の人にリーダーシップを分散させる考え方です。Distributed Leadership(DL)とも呼ばれ、特定の肩書きを持つ上司だけでなく平社員を含めた複数メンバーが協力し合ってリーダーシップ機能を発揮する仕組みを指します。
リーダーとフォロワーの役割が固定化されず、状況に応じて誰もが主体的に組織を牽引する点に特徴があります。このアプローチでは、現場の知見を活かした自律的な意思決定が促され、環境変化への俊敏な対応が可能になります。また社員一人ひとりがエンパワー(権限委譲)されることでエンゲージメントも向上しやすいと言われます。MITスローンのデボラ・アンコーナ教授も「リーダーシップはもはや一握りの人だけでなくネットワーク全体で発揮されるべきだ」と述べており、分散型リーダーシップはこれからのマネジメントの主流になります。
多様性と組織開発・DEI(Diversity、Equity、Inclusion)
多様性・公平性・包摂性を意味するDEIは、近年企業が重視するテーマの一つです。組織開発の文脈でも、多様な人材が活躍できるインクルーシブな組織文化づくりが重要視されています。事実、2022年に産業・組織心理学者数千人を対象に行われた調査では、「インクルーシブな職場環境と文化の確保」が職場トレンドの第2位に挙げられました。これは、多様性を受け入れる風土が人材獲得やエンゲージメントに直結し、さらには創造性や意思決定の質向上につながると考えられているためです。
現代の組織開発トレンドとして、リーダーシップの在り方はトップダウンから全員発揮の分散型と多様性へ変化しています。これらはいずれも、急激な環境変化に適応し、創造性と公正さを両立する強い組織を作るためのキーワードです。組織開発は時代とともに進化し続けており、今後もテクノロジーの活用や新しい理論の登場によってそのアプローチは深化していくことでしょう。重要なのは自社の課題や目的に照らして、これら新潮流を上手く取り入れ、自律的で多様性に富んだ健全な組織づくりに活かしていくことです。
まとめ
組織開発を成功させるには、組織の中の「人」に変化を起こす必要があります。その際のポイントは、人材開発のようにスキル(能力)を伸ばすだけでなく、価値観や行動様式に働きかけることです。個人のスキル習得よりも価値観を変えることの方が、はるかに難易度が高いため、社内に専門知識がない場合はノウハウを持つ外部の専門家に相談しながら進めるのが良いでしょう。第三者が介入することで客観的な視点が得られますが、同時に外部では踏み込み切れない領域もあります。組織開発コンサルタントはあくまで伴走者であり、最終的に組織を変えていくのは内部の人間自身だという点を忘れないようにしましょう。
また、昨今は市場や技術の変化が早く、組織のタスク(業務課題)もコミュニケーションの在り方も刻一刻と変化していきます。組織開発は一度やって終わりではなく、継続的な取り組みとして社内に定着させることが重要です。一時的に外部の力を借りることは有効ですが、同時に社内にナレッジを蓄積し、自走できる力(組織開発力)を養っていくことが求められます。
幸い、組織開発のプロセスを通じて社員同士の対話が活性化し、成功体験が共有されていけば、組織は自ら変化し続ける力を獲得していきます。それこそが持続的に成長する強い組織の姿と言えるでしょう。人事部門長や現場マネージャーの皆様も、自組織の課題に合わせてぜひ組織開発に取り組んでみてください。組織開発の実践を通じて、組織が一段と活力に満ち、社員がいきいきと働ける職場へと変わっていくことでしょう。
関連サービス
- 調査・コンサルティング ―さまざまなデータから、課題解決につながるインサイトを抽出―
- 業務プロセス最適化 ―インターナルコミュニケーションの視点で業務を再設計―
- ICTシステム活用支援 ―課題解決や目的達成に最適なシステム導入のお手伝い―
- メディア・コンテンツ ―読者と発信者、双方の視点に立った企画、設計―
- 研修・ワークショップ ―実践型研修とアフターフォローで学習効果を高める―
- イベント企画運営 ―企画力と事務局サポートで記憶に残るイベントを実現―